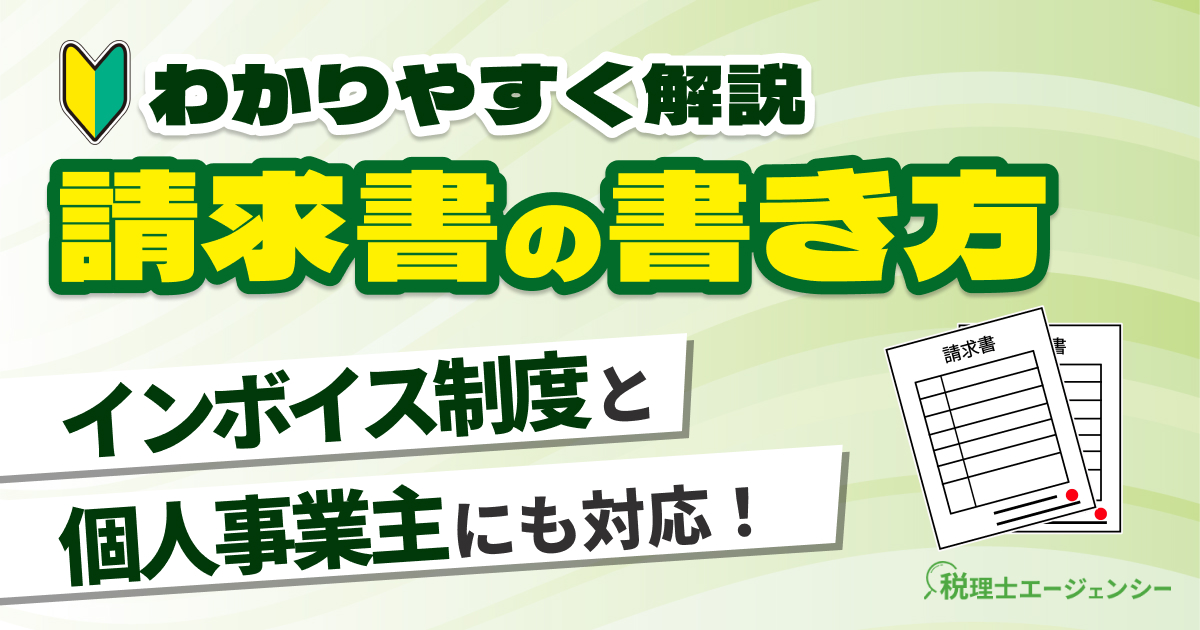請求書は取引を証明し、取引先に対して支払いを促す書類です。ビジネスシーンにおいて円滑に業務を進めたり、報酬を確定したりするためには請求書の活用が欠かせません。
しかし、「請求書と納品書や領収書の違いが知りたい」「請求書の書き方や作成を効率化する方法を知りたい」と考えている人も多いでしょう。
そこで本記事では、請求書の概要や他書類との違い、請求書の書き方・必須項目を解説します。請求書作成を効率化する方法や発行後の実務対応についてもまとめているため、気になる人はぜひ参考にしてください。
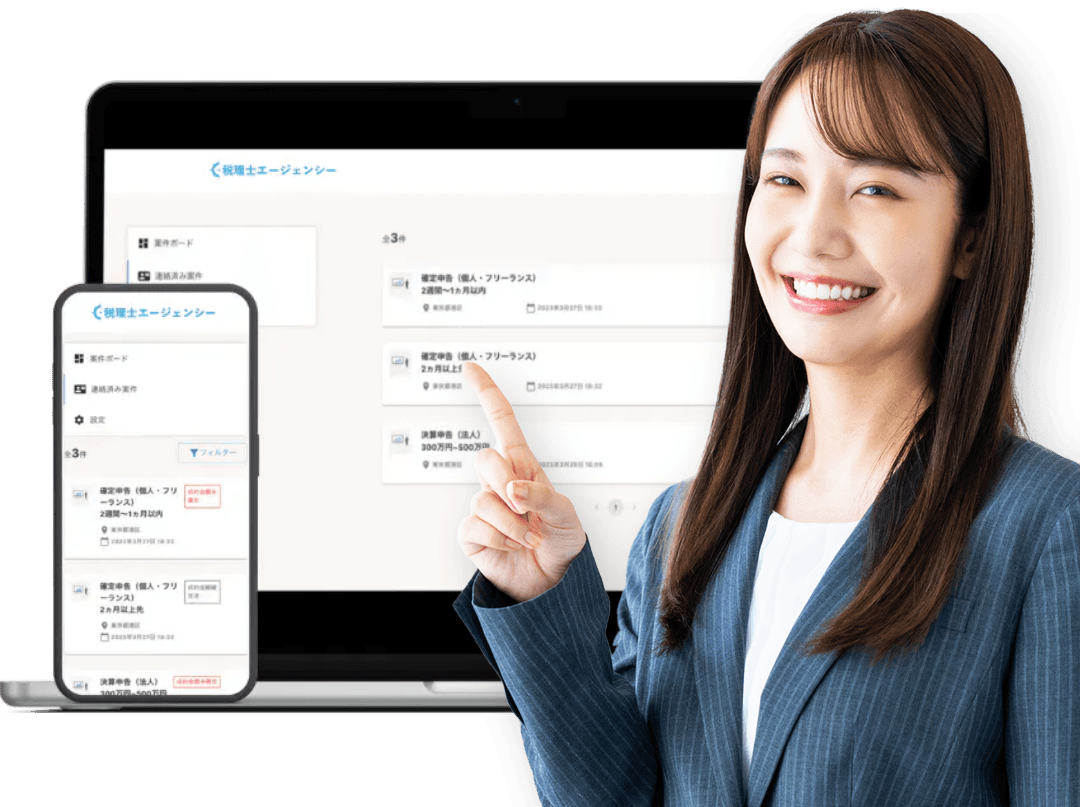
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
請求書とは支払いを促し取引を証明する重要な書類
請求書とは、商品やサービスの提供を行った後に代金を請求するために発行する重要な書類です。単に支払いを求めるだけではなく、取引内容を証明し、取引先と自社の合意を裏付ける役割も果たします。記載内容として取引日や取引先名、商品やサービスの明細、数量や単価、合計金額や消費税額などが一般的です。複数の項目を記載することで、後のトラブルを防止し、スムーズな資金回収につなげられます。特に法人間の取引では、請求書が会計処理や税務申告の裏付け資料としても重要な役割を果たします。
また、請求書は企業の信頼性を示すビジネス文書でもあるため、書式やレイアウトにも一定の配慮が求められます。取引先に安心感を与えるためにも、整ったフォーマットで発行が必要です。さらに、2023年10月から開始されたインボイス制度により、請求書に記載すべき内容が増えているため、発行時にはフォーマットやインボイス制度に則っているか確認しましょう。
- 見積書・納品書・領収書との違いを整理しよう
- インボイス制度対応で必要となる記載要件を理解する
それぞれ順に解説します。
見積書・納品書・領収書との違いを整理しよう
請求書と混同されやすい関連書類として、見積書・納品書・領収書が挙げられます。見積書は、取引前に発行される書類で、提供予定の商品やサービスの内容や金額を示します。契約を結ぶ前に取引条件を確認する役割を持ちます。納品書は商品やサービスの提供時に発行され、何が納品されたかを証明する文書です。請求書と類似点も多いですが、金額を記載しない場合も多く、主に取引内容を確認する目的で用いられます。
領収書とは、支払いが完了した後に発行され、代金を受け取ったことを証明する書類です。見積書は取引前、納品書は取引中、請求書は取引後の支払い請求、領収書は取引完了を示す書類と言えます。それぞれの違いを理解し、適切な場面で適切な書類を使い分けることで、取引上の信頼性を高められるでしょう。
インボイス制度対応で必要となる記載要件を理解する
インボイス制度では、従来の請求書や領収書に加え、詳細な記載要件が求められるようになりました。インボイスの正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼び、消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先から発行された適格請求書の保存が必須条件となっています。
具体的な記載要件には、取引年月日、取引内容、税率ごとの消費税額、登録番号、取引金額が含まれます。これまでの請求書では消費税額を一括で記載するだけでも認められていましたが、インボイス制度下では軽減税率の有無や税率ごとの金額区分も記載する必要があるため、より正確で詳細な記載が求められます。
事業者にとっては事務負担が増える一方で、適切に対応することで仕入税額控除が認められるため、経営に直接関わる重要な要素と言えます。請求書を発行する企業側だけではなく、受け取る側も内容を精査する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録番号を必ず記載する
インボイス制度に対応した請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」として登録を受けている必要があります。登録を受けると国税庁から登録番号が発行され、番号を請求書に必ず記載しなければなりません。登録番号が記載されていない請求書は、適格請求書として認められず、取引先は仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。登録番号未記載の請求書は取引先に不利益を与える可能性があるため、作成時に確認しておくべき重要なポイントです。
記載方法としては、事業者名や住所と並んで明記するのが一般的で、請求書フォーマットを作成する際には項目として固定しておくことが最適です。また、登録番号はWeb上で公開されており、登録業者以外の誰でも検索可能となっています。そのため、請求書を受け取った側も記載番号が正しいか確認でき、取引の透明性が高まります。結果的に適切な番号記載は企業間取引の信頼関係を守る上で不可欠と言えるでしょう。
軽減税率対象商品の表示と税率区分ごとの金額表示
インボイス制度では、消費税率が複数存在する点に対応が必要です。標準税率10%と軽減税率8%の商品が混在する場合、それぞれを区分して記載が必須です。従来の請求書では、単に合計金額と一括消費税を記載するだけでも認められていましたが、制度導入後は税率ごとに明細を分け、課税対象額と消費税額を明確に表示する必要があります。特に飲食料品や新聞など、軽減税率が適用される取引では、請求書に「軽減税率対象」である旨を示すとともに、8%区分の金額を分けて記載しなければなりません。
これらの対応を怠ると、受け取った側が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引先に迷惑をかける可能性があります。そのため、会計ソフトや請求書発行システムを活用して自動的に税率ごとに区分する仕組みを導入する企業も増加しています。正確な税率区分表示は、制度適用後の請求書作成における最重要ポイントです。
インボイス制度対応で求められる消費税額の記載方法
インボイス制度では、消費税額の記載方法にも従来とは異なる厳格なルールが設けられています。従来の請求書では総額表示の中に消費税を含めるだけでも問題ありませんでしたが、制度導入後は税率ごとに消費税額を明確に区分して記載が求められます。
例えば、標準税率10%の商品と軽減税率8%の商品が混在する場合、それぞれの税率ごとの課税標準額と消費税額を分けて表示が必要です。取引先は仕入税額控除の対象となる消費税を正確に把握できるようになります。記載漏れや誤りがあると、仕入税額控除が認められず、実質的に取引先に損害を与えるリスクがあるため注意が必要です。
そのため、消費税額の計算や記載には、会計ソフトやクラウド請求書サービスを活用し、自動計算機能を用いるのが一般的です。インボイス制度対応の正しい請求書作成は、税務リスクを回避し、信頼性の高い取引を維持するために欠かせない取り組みと言えるでしょう。
請求書の書き方と必須項目をわかりやすく解説
請求書には宛名・氏名だけでなく、請求日や取引内容、数量・単価・金額など、費用請求に関連するさまざまな情報の記載が必要です。記載情報に抜け漏れがあると適切に取引を完了させられなかったり、スムーズな対応に支障が出てしまったりします。特に2023年10月から始まったインボイス制度によって、登録番号などの記載も必要となるため、あらかじめポイントを抑えておく必要があります。
具体的な請求書の書き方や必須項目は、以下のとおりです。
- 請求先(宛名・氏名・敬称)を正確に記載する
- 請求日・請求書番号・タイトルを明確に記載する
- 取引内容と取引年月日は具体的に記載する
- 数量・単価・金額を整理した取引明細を記載する
- 消費税や複数税率の区分を正しく表示する
- 住所・登録番号・連絡先の発行者情報を必ず記載する
- 請求金額・振込期日・振込先口座を正しく記載する
それぞれ順に解説します。
請求先(宛名・氏名・敬称)を正確に記載する
請求書を作成する際は、請求先の情報である宛名・氏名・敬称を正確に記載が必要です。請求書の宛名は、取引相手に請求内容を正確に伝えるための情報であり、ビジネスマナーの基本を示す重要な項目です。宛名の記載が不正確だと、相手の経理担当者に届かなかったり、支払いが遅延したりする原因になりかねません。会社宛てに送る場合は、正式名称を省略せずに記載しましょう。
「株式会社」を「(株)」と略すのは避け、前株か後株かも正確に確認が必要です。部署宛てに送る際は「会社名+部署名+御中」と記載します。「御中」は組織や団体に対する敬称であり、担当者名が不明な場合に用います。特定の担当者宛てに送る場合は、「会社名+部署名+役職名+氏名+様」のように記載します。「様」は個人に対する敬称です。ただし、「御中」と「様」の併用は認められません。例えば「経理部御中 田中様」といった書き方は、誤りで担当者名が分かっているなら「経理部 田中様」と記載しましょう。
請求先が個人事業主の場合は、屋号と氏名を併記し、「屋号+氏名+様」とします。請求先の組織形態や誰に確認してもらいたいのかに合わせて敬称を正しく使い分けることで、請求先の情報を正確に記載できます。
請求日・請求書番号・タイトルを明確に記載する
請求書には、いつ、どの取引に関する書類なのかを明確にするための情報が不可欠です。まず、書類の冒頭には「請求書」というタイトルを大きく、分かりやすく記載します。これにより、受け取った側が一目で何の書類かを判断でき、他の書類と混同されるのを防ぎます。
次に「請求日」ですが、これは請求書を発行した日付を指します。一般的には、取引先の締め日に合わせるケースと、自社で請求書を作成した日付を記載するケースがあります。どちらの日付を記載するかは、事前に取引先と確認しておくのが最も確実です。もし特に指定がなければ、自社の経理処理のルールに従って発行日を記載すると良いでしょう。
そして、管理上非常に重要になるのが「請求書番号」です。これは、請求書を一枚一枚識別するためのユニークな番号で、発行者側が任意に設定します。例えば「20251001-001」のように、発行年月日と連番を組み合わせる方法が一般的です。請求書番号を付けておくことで、後から問い合わせがあった際に、どの請求書に関する話なのかを迅速に特定できます。
また、売上管理や入金確認の際にも、番号で照合できるため業務効率が大幅に向上します。これらの項目は、請求書の信頼性と管理効率を高めるために、必ず正確に記載しましょう。
取引内容と取引年月日は具体的に記載する
請求書を作成する際は、取引内容と取引年月日を正確に記載しましょう。取引内容はどのようなサービスや商品に対して代金を請求しているのかを示します。取引内容が曖昧だと、取引先は何の支払いなのかを正確に把握できず、経理処理が滞ったり、問い合わせの手間が発生したりする原因となります。そのため、取引内容は誰が見ても理解できるよう、具体的かつ明確に記載が求められます。記載時は「商品代として」や「コンサルティング料」といった漠然とした表記は避け、「商品名(型番など)」や「〇〇に関するコンサルティング業務(10月分)」のように、具体的な品目やサービス内容を明記しましょう。
また、取引が行われた「取引年月日」の記載も重要です。売上がいつ計上されるべきかを判断するための基準日となります。商品が複数ある場合や、継続的なサービス提供の場合は、それぞれの品目ごとに納品日やサービス提供日を記載するとわかりやすくなります。例えば、ウェブサイト制作の案件であれば、「トップページデザイン制作 2025/09/15」や「下層ページコーディング 2025/09/30」のように、工程ごとに日付を分けると、取引の実態がより明確になります。取引内容と年月日を具体的に示すことで、取引先への配慮であると同時に、自社の売上管理を正確に行う上でも不可欠なポイントと言えるでしょう。
数量・単価・金額を整理した取引明細を記載する
請求書において、請求金額の根拠を明確に示す内容として取引明細が挙げられます。取引明細には「数量」「単価」「金額」を品目ごとに整理して記載します。詳細が正確に記載されていることで、取引の透明性が高まり、相手方も安心して支払い手続きを進められます。数量には、提供した商品やサービスの量を記載します。例えば、商品を10個納品したのであれば「10」Web記事を5本制作したのであれば「5」と記入します。単位も併記するとより丁寧で「10個」「5本」「2時間」と記載するケースが多いです。
また、単価とは商品一つあたり、またはサービス1単位あたりの価格を指します。時間単位で業務を請け負う場合は、時給や時間単価を記載します。金額の欄には、「数量 × 単価」で算出した小計を品目ごとに記載します。例えば、単価5,000円の商品を10個納品した場合、金額は50,000円となります。複数の品目がある場合は、リスト形式で分かりやすく並べ、最後にすべての金額を合計した「小計」の欄を設けます。明細を記載することで、請求金額がどのように算出されたのかが一目瞭然となり、計算間違いなどのトラブルを防ぐ効果もあります。Excelや請求書作成ソフトなどを利用して、見やすい表形式で作成すると良いでしょう。
消費税や複数税率の区分を正しく表示する
現在の消費税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数存在するため、請求書における消費税の正しい表示は重要です。特に2023年10月から開始されたインボイス制度では、税率ごとの区分経理が求められており、請求書の記載方法も厳格化されました。請求書を作成する際は、取引明細の小計を算出した後、適用される税率ごとに合計金額を区分して記載する必要があります。例えば、標準税率10%対象の商品と軽減税率8%対象の商品(飲食料品など)が混在する取引の場合、「10%対象合計金額」と「8%対象合計金額」をそれぞれ明記します。その上で、各税率で計算した消費税額も個別に記載し、最後に全体の合計金額(税込)を示すのが正しい書き方です。
インボイス制度に対応した適格請求書では「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が義務付けられています。これらの記載がないと、買い手側は仕入税額控除を受けられなくなってしまう可能性があるため、取引相手にリスクを与えないためにも抑えておきましょう。消費税の計算で端数が出た場合の処理(切り捨て、切り上げ、四捨五入)についても、事前に取引先とルールを確認しておくと、よりスムーズに請求書を発行できます。
住所・登録番号・連絡先の発行者情報を必ず記載する
請求書には、取引内容だけでなく「誰がこの請求書を発行したのか」を明確に示すため、住所・登録番号・連絡先などの発行者情報の記載が欠かせません。発行者情報がなければ、受け取った側はどこに支払いをすれば良いのか分からず、正式な書類として認められない可能性があります。記載すべき基本的な情報は、氏名または名称(法人の場合は会社名、個人事業主の場合は屋号や氏名)、住所または本店所在地、電話番号やメールアドレスなどの連絡先です。
これらの情報を記載することで、請求内容に不明な点があった場合でも相手方がスムーズに問い合わせできます。インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者の登録を受けている課税事業者にとっては「登録番号」の記載が新たに義務付けられました。登録番号は、法人番号を持つ法人の場合は「T + 法人番号」、個人事業主などの場合は「T + 13桁の数字」で構成されます。番号が記載された請求書を適格請求書と呼び、原則として買い手は消費税の仕入税額控除を受けることができません。そのため、登録事業者は必ず番号を請求書に明記する必要があります。発行者情報は、自社の信頼性を示すとともに、取引を円滑に進めるための重要な要素と言えるため、ミスなく正確に記載すると良いでしょう。
請求金額・振込期日・振込先口座を正しく記載する
請求書で重要な部分として、最終的にいくらを、いつまでに、どこへ支払ってもらうのかを明確に伝える項目となる請求金額・振込期日・振込先口座です。請求金額は、取引明細で算出した小計と、それぞれにかかる消費税額を合算した最終的な支払総額を記載します。金額が最も目立つように、太字にしたりフォントサイズを大きくしたりする工夫も有効です。
振込期日(支払期限)は取引先との契約や取り決めに従って設定します。「月末締め翌月末払い」など、商慣習に沿った期日を設定するのが一般的ですが、トラブルを避けるためにも「2025年11月30日」のように具体的な日付の明記が必要です。期日が明確でないと、入金が遅れる原因となります。
支払いを実行してもらうための「振込先口座情報」も必須項目です。記載すべき項目は、「金融機関名」「支店名」「預金種別(普通・当座など)」「口座番号」「口座名義(カタカナ)」です。特に口座名義は、会社名や屋号、個人名が正式名称と一字一句違わないように正確に記載する必要があり、情報に一つでも誤りがあると、振込エラーが発生し入金が大幅に遅れてしまいます。請求書を発行する前には、必ずこれらの項目を複数回見直し、間違いがないかを確認した上で取引先へ届けましょう。
振込手数料の負担者を明記してトラブルを防ぐ
請求と支払いの流れで見落とされがちですが、金銭的なトラブルに発展しやすい点として「振込手数料」の負担に関する問題が挙げられます。数百円程度のこととはいえ、取引のたびに積み重なると決して無視できない金額になるケースがあります。どちらが負担するかについて法律で明確な定めがあるわけではありませんが、民法の原則では「債務(支払い)の履行にかかる費用は、債務者(支払う側)が負担する」とされています。原則としては支払いを行う側、請求書の受け取り手が負担する可能性が高いです。
しかし、ビジネスシーンでは、契約内容や当事者間の合意が優先されるため、必ずしもこの原則通りとは限りません。そのため、後々のトラブルを未然に防ぐために、請求書に振込手数料の負担者を明記しておくことが非常に重要です。具体的には、請求書の備考欄や振込先情報を記載する欄の近くに、「誠に恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願い申し上げます。」といった一文を添えておくと良いでしょう。
一方、発行者側が手数料を負担する場合は、その旨を記載する必要はないものの、請求金額から手数料分を差し引いて振り込んでもらうなどの取り決めを事前に行っておく必要があります。細かい確認や配慮が、取引先との良好な関係を維持するポイントと言えるでしょう。
個人事業主は源泉徴収の有無を必ず確認する
個人事業主やフリーランスが報酬を受け取る際に、注意が必要な点として「源泉徴収」が挙げられます。源泉徴収とは、特定の報酬を支払う側(企業など)が、報酬から所得税等をあらかじめ天引きし、本人に代わって国に納付する制度です。すべての報酬が対象になるわけではなく、原稿料、講演料、デザイン料、弁護士や税理士など特定の資格を持つ人への報酬などが対象となります。自身が提供したサービスが源泉徴収の対象となるかどうかを、事前に確認が必要です。
もし対象となる場合、請求書の書き方にも工夫が必要で、請求金額の内訳として、報酬の総額(税抜)、消費税、源泉徴収税額、最終的な請求金額(差引支払額)を明確に分けて記載する方法が一般的とされています。源泉徴収税額の計算方法は、原則として支払金額(消費税込みの金額が明確に区分されていれば、税抜きの報酬額)が100万円以下の場合は10.21%、100万円を超える部分は20.42%となります。
例えば、税抜10万円の原稿料(消費税1万円)を請求する場合、源泉徴収税額は10万円 × 10.21% = 10,210円です。請求書には、請求総額11万円から源泉徴収税額10,210円を差し引いた99,790円が最終的な振込金額であることを明記します。記載を怠ると、取引先が混乱したり、入金額に齟齬が生じたりする可能性があるため、必ず確認しましょう。
請求書作成を効率化するテンプレートとツール活用法
請求書にはさまざまな項目を正確に記載する必要があるため、請求書作成を効率化するテンプレートやツールの活用が欠かせません。テンプレートや専用ツールを上手く活用すれば、ミスなく素早く請求書の作成が可能になるため、業務が効率化されスムーズに取引を完結させられます。具体的に請求書作成を効率化するテンプレートとツール活用法は、以下のとおりです。
- 請求書テンプレートを利用して初心者でも記載漏れを防ぐ
- 請求書作成ソフトやクラウドサービスで効率化する
それぞれ順に解説します。
請求書テンプレートを利用して初心者でも記載漏れを防ぐ
請求書の作成は、個人事業主やフリーランスとして独立したばかりの事業者にとって戸惑うことの多い項目と言えます。何から手をつけて良いかわからず、ゼロから作成しようとすると、請求先、発行日、請求書番号、取引内容、合計金額、振込先といった必須項目の記載漏れが発生しやすくなります。
これらのミスは、入金の遅延や取引先からの信用低下につながりかねません。そのため、請求書テンプレートの活用がおすすめです。ExcelやWord、Googleスプレッドシートなどで利用できるテンプレートには、請求書に必要な項目があらかじめ網羅されているため、フォーマットに沿って入力するだけで、誰でも簡単に体裁の整った請求書を作成できます。記載漏れといった初歩的なミスを防げます。
また、Web上では、インボイス制度に対応したテンプレートも無料で数多く配布されています。デザインもシンプルなものから、自社のロゴを入れられるカスタマイズ性の高いものまで多岐にわたるため、事業のイメージに合ったテンプレを選べます。テンプレートを利用することで、単なる時短ではなく、ビジネスの基本となる正確な書類作成をサポートし、取引先に安心感を与える重要な活用法と言えるでしょう。
請求書作成ソフトやクラウドサービスで効率化する
毎月の請求書発行枚数が多い事業者や経理業務全体の効率をさらに高めたい場合、請求書作成ソフトやクラウドサービスの利用が効果的です。ツールには単にテンプレートを提供するだけでなく、請求書作成にまつわる一連の作業を自動化・効率化する多彩な機能を備えています。
例えば、一度取引先の情報や商品・サービスの単価を登録しておけば、次回からはリストから選択するだけで自動的に請求書が作成され、入力の手間とミスを大幅に削減できます。請求書番号の自動採番、消費税や源泉徴収税の自動計算といった機能により、手作業で起こりがちな計算間違いも防げます。
さらに、作成した請求書はワンクリックでPDF化され、そのままメールで送付できるため、印刷や封入、郵送といった手間とコストもかかりません。多くのクラウドサービスでは、請求書ごとの入金状況を管理する機能も搭載しており、どの案件が未入金なのかを一目で把握できます。確定申告ソフトと連携できるサービスを選べば、請求書データが自動的に売上として計上され、決算や申告作業の負担を抑えられます。月額費用がかかる場合もありますが、それ以上に得られる時間的コストの削減効果が大きいケースも多いため、請求書作成件数が多い場合は導入を検討しましょう。
請求書の送り方と発行後の実務対応を正しく管理する
請求書作成後も控えを保存してトラブルや税務調査に備える必要があります。正確な請求書が作成できていても、送り方や発行後の実務対応が誤っていると取引先へ悪い印象を与えてしまったり、トラブルに発展する可能性があります。請求書には封筒郵送のマナーや表記の基本ルールが存在します。
- 封筒郵送のマナーと請求書在中表記の基本ルール
- 添え状を付けた送付方法とビジネスマナーの注意点
- 電子請求書・PDF送付時の注意点と電子帳簿保存法対応
- 請求書の控えを保存してトラブルや税務調査に備える
ここでは、請求書の送り方や発行後の実務対応について解説します。
封筒郵送のマナーと請求書在中表記の基本ルール
請求書を郵送する際は、内容だけでなく、封筒の選び方や書き方といったビジネスマナーを守ることで取引先との良好な関係を築けます。封筒はA4用紙を三つ折りにしてちょうど収まる「長形3号(なががたさんごう)」が一般的で、色は清潔感のある白や淡い色のものを選びましょう。
宛名は、相手の会社名、部署名、担当者名を正確に記載します。会社名は「(株)」などと略さず、正式名称で書くのがマナーです。請求書を送る上で欠かせないポイントとして「請求書在中」の表記が必要です。封筒の表面左下に記載することで、受け取った相手は開封せずとも重要書類であることが一目で分かり、社内の経理担当者へスムーズに届けられます。
この表記がないと、他のダイレクトメールなどに紛れてしまい、開封が遅れ、結果的に支払いの遅延につながる可能性もあります。表記は市販のスタンプを使用するのが最も手軽で綺麗ですが、手書きでも問題ありません。手書きの場合は、文字を四角い枠で囲むとより目立ちやすくなります。スタンプの色は青色が一般的とされていますが、黒や赤でもマナー違反ではありません。細かい配慮やマナーを守ることで、自社の印象向上にもつながるでしょう。
添え状を付けた送付方法とビジネスマナーの注意点
請求書を郵送する際、封筒に請求書だけを入れて送るのはビジネスマナーとしてミスマッチとされています。丁寧な印象を与え、円滑なコミュニケーションを図るためには「添え状(送付状)」を同封しましょう。添え状は、誰が、誰に、何を、どれだけ送ったのかを明確に伝える役割を担います。基本的な構成要素としては、以下のとおりです。
- 発行年月日
- 宛名(会社名、部署名、担当者名)
- 差出人情報(自社の会社名、住所、連絡先)
- 頭語と結語(「拝啓」と「敬具」など)
- 件名(「請求書ご送付の件」など)
- 本文
本文では「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記の通り請求書をお送りいたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。」といった挨拶と共に、送付内容を伝えます。さらに、本文の下に「記」と中央に書き、その下に「請求書 1通」のように同封書類の内容と部数を箇条書きで記載すると、相手が内容物を確認しやすくなります。
封筒に入れる際は、添え状が一番上になるようにし、次に請求書を重ねて三つ折りにします。ひと手間かけて添え状を付けることで、正しいビジネスコミュニケーションを実現します。
電子請求書・PDF送付時の注意点と電子帳簿保存法対応
近年ではコスト削減や業務効率化の観点から、請求書をPDF化してメールで送付する電子請求書が主流となっています。手軽な一方で注意すべき点が存在します。メールの件名は「【株式会社〇〇】2025年10月分請求書のご送付」のように、送信元と内容が一目で分かるようにしましょう。本文には、郵送時の添え状と同様に、宛名、挨拶、請求書を添付した旨なども記載します。
セキュリティ対策として、PDFファイルにパスワードを設定することも重要です。パスワードを記載したメールと、請求書を添付したメールを別々に送るのがマナーです。電子請求書を発行・受領する上で重要な点が「電子帳簿保存法」への対応です。2024年1月からは、電子的に受け取った請求書などの国税関係書類は、電子データのまま保存することがすべての事業者に義務化されました。保存する際は、以下の2点を抑えている必要があります。
- 改ざんを防止するための措置(タイムスタンプの付与など)をとる「真実性の確保」
- 日付・金額・取引先で検索できるようにするなどの「可視性の確保」
上記2点の要件を満たす必要があり、発行側・受領側双方に求められるため、適切なファイル名で管理するなどの社内ルールの整備が不可欠です。
請求書の控えを保存してトラブルや税務調査に備える
請求書は発行して相手に送付したら終了ではなく、発行したすべての請求書について、必ず「控え」を適切に保存しておくことが法律で義務付けられています。控えは将来起こりうるさまざまな事態に備えるための重要な証拠書類となります。取引先との間で「請求書を受け取っていない」「金額が違う」といった支払いトラブルが発生した際に、控えがあれば取引内容を正確に証明することができます。
また、税務調査が行われた際には、売上の計上漏れがないことを証明するための根拠資料として提示する必要があります。控えが保存されていなければ、売上を証明できず、追徴課税などのペナルティを受けるリスクがあります。請求書の保存期間は、法人の場合は原則としてその事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間、個人事業主の場合は青色申告で7年間、白色申告で5年間と定められています。
保存方法は、紙で出力してファイリングする方法のほか、電子帳簿保存法の要件を満たした上で電子データとして保存することも可能です。いずれの方法でも後からすぐに参照できるよう、取引先別や年月別など、自社で管理しやすいルールを決めて整理しておくことが、健全な事業運営の基本と言えるでしょう。
請求書の書き方に関するよくある質問に回答
手書き請求書でもインボイス要件を満たせますか?
インボイス制度においては、請求書の作成方法が手書きかデジタルかは問われません。重要なのは、制度で定められた「適格請求書」としての記載要件を満たしているかが重要です。例えば、登録番号、取引内容、取引年月日、税率ごとの金額や消費税額などが正しく記載されていれば、手書き請求書でも問題なく有効となります。
ただし、手書きは誤記や修正が増えるリスクがあり、業務効率の面でも不利なため、クラウド請求書サービスの利用が最適です。
個人事業主が請求書を発行する際に注意することは?
個人事業主が請求書を発行する場合、自身がインボイス制度に対応した「適格請求書発行事業者」に登録しているかどうかを確認する必要があります。登録していない場合、取引先は仕入税額控除を受けられないため、取引に影響を与える可能性があります。
また、請求書には必ず登録番号を記載し、取引内容や税率ごとの金額区分を明確にすることが求められます。さらに、屋号や連絡先をきちんと記載しておくことで、信頼性の高い請求書となり、トラブル防止にもつながります。
建設業や請負業に特有の請求書ルールはありますか?
建設業や請負業では、長期工事や大口取引が多いため、一般的な請求書とは異なる点があります。工期に応じて「着手金・中間金・完成金」といった分割請求を行うことが多く、その都度「第◯回請求分」「出来高○%」などの明記が必要です。
また、工事契約との整合性を示すため、工事件名や工事場所、契約番号を記載するのが一般的です。下請法の観点から支払期日や条件を明確にする必要があり、インボイス制度に基づく登録番号や消費税額の記載も忘れずに行いましょう。