ファイナンスリースは機械や車両、IT機器など高額な設備に用いられるケースが多く、長期利用を前提とした契約方法です。初期投資を抑えて支払額を平準化したり、会計処理の明確化ができたりします。
しかし、「ファイナンスリースの具体的なメリットって何?」「ファイナンスリースの仕訳方法を知りたい」と考える人も多いでしょう。
そこで本記事では、ファイナンスリースの概要から利用するメリット・デメリット、仕訳方法をわかりやすく解説します。よくある質問もまとめているため、ファイナンスリースの利用を検討している人はぜひ参考にしてください。
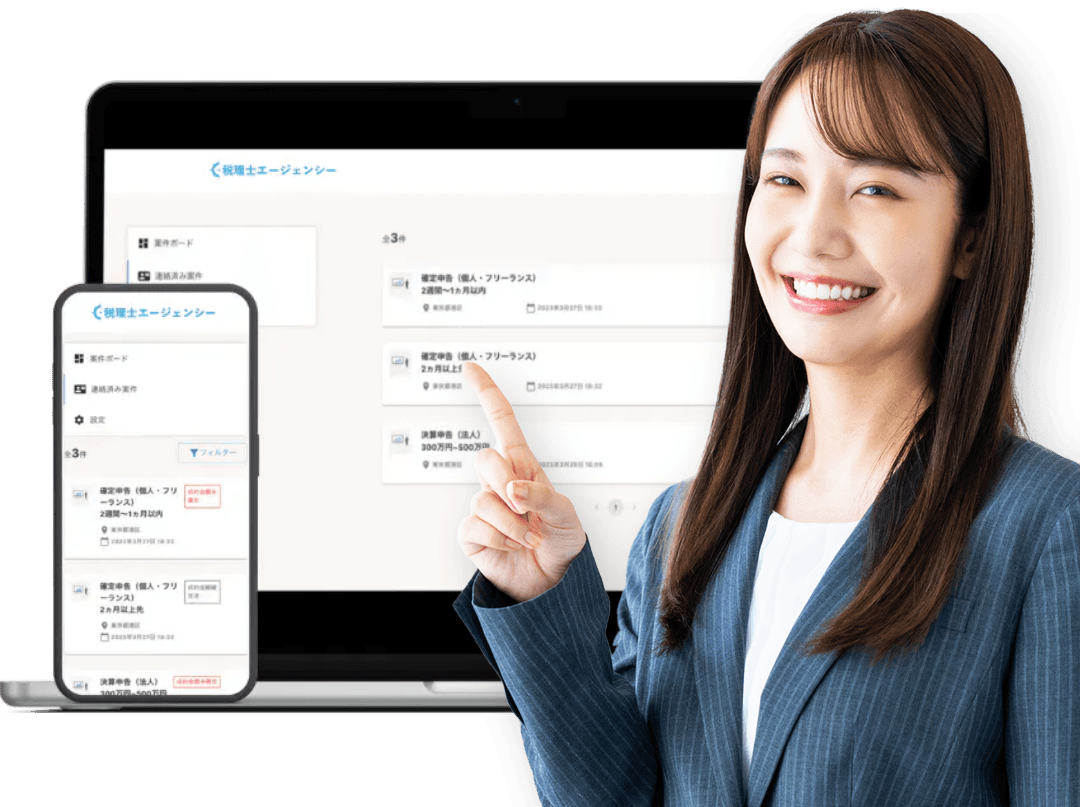
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
ファイナンスリースとは長期利用を前提としたリース契約
ファイナンスリースとは、企業が事業に使う設備などをリース会社から長期間にわたって借りる契約形態です。長期利用を前提としているため、実質的に設備を購入するのと似た性質を持っています。リース期間中に発生する設備の維持費用や固定資産税、保険料などの負担を借りる側が全て負う点が特徴です。
さらに、契約の中途解約は原則として認められていません。リース会社が設備購入にかかった費用を、リース料として全額回収できるようにするためです。例えば、新しい製造機械を導入したいが、一度に多額の資金を投じるのは避けたい場合、ファイナンスリースを利用すれば、初期費用を抑えつつ、必要な設備をすぐに使えます。
また、リース料は原則として資産計上と減価償却が必要ですが、中小企業の特例処理を用いる場合には、リース料を全額経費として計上でき、税務上のメリットも期待できます。資金繰りを安定させながら、企業の設備投資を効率的に進めるための選択肢となるのがファイナンスリースです。
- 不動産や自動車など高額資産と相性が良い契約形態
- ファイナンスリースの契約種類をわかりやすく解説
それぞれ順に解説します。
不動産や自動車など高額資産と相性が良い契約形態
ファイナンスリースは、特に高額な資産と非常に相性の良い契約形態です。資産を一括購入する場合に比べて初期の資金負担を大幅に軽減することが可能です。例えば、オフィスビルや工場などの不動産、トラックやバスなどの大型車両を自社で購入しようとすると、多額の資金が必要になります。
しかし、ファイナンスリースを利用すれば、これらの資産をリース会社が購入し、長期にわたって賃貸する形で利用できます。企業は多額の現金を一度に手放すことなく、事業に必要な高額資産を導入できるため、資金の流動性を保てます。さらに、リース料は固定されているため、将来のキャッシュフローを計画しやすくなるメリットもあります。
また、所有権移転外リースで中小企業特例を適用する場合には、減価償却や固定資産税の処理を行う必要がなく、経理負担を軽減できます。ただし、通常の会計基準に基づく処理ではリース資産として計上し、減価償却を行う必要があります。そのため、リース契約に関する煩雑な資産計上を気にすることなく、本業に集中できるという点も特徴です。
ファイナンスリースの契約種類をわかりやすく解説
ファイナンスリースには、大きく以下の2つの種類に分けられます。
- 所有権移転ファイナンスリース
- 所有権移転外ファイナンスリース
それぞれの代表的な違いは、リース期間終了後に資産の所有権が借り手側に移るか否かという点です。所有権移転ファイナンスリースは、リース期間が終了すると同時に、契約した資産の所有権が借り手側に移転する契約です。実質的に分割払いでの資産購入と非常に似ています。
一方、所有権移転外ファイナンスリースは、リース期間が終了しても、資産の所有権はリース会社に残る契約です。借り手は資産を返却するか、再リース契約を結ぶか、買い取るかの選択をする必要です。
どちらの契約を選択するのが最適かは、企業の事業計画や税務上の戦略によって異なります。例えば、将来的にその資産を自社のものとして長く使い続けたい場合は所有権移転型を、新しい技術や設備に随時更新していきたい場合は所有権移転外型を選ぶと良いでしょう。ここでは、ファイナンスリースの契約種類についてわかりやすく解説します。
所有権が移転するファイナンスリース契約の特徴
所有権が移転するファイナンスリース契約は、リース期間の満了時に資産の所有権が借り手側に移転する契約です。資産を最終的に自社の資産としたい場合に最適です。リース期間中に支払うリース料は、実質的に資産の購入代金を分割で支払っているのと同様の性格を持っています。
所有権移転ファイナンスリースは、長期間にわたって安定して同じ資産を使い続けたい場合に有利と言えます。例えば、長期にわたって使用する予定の大型機械や建物などの資産を導入する際に選択されます。所有権が最終的に借り手側に移転するため、リース終了後も追加の費用を支払うことなく、その資産を自由に使用・売却・処分できます。
ただし、所有権が移転すると借り手は資産を保有する義務や責任を負うことになります。固定資産税の支払い、減価償却費の計上、将来的な売却や処分の際の管理が含まれます。自社の資産とする場合のリスクも把握した上で契約すると良いでしょう。
所有権が移転しない移転外ファイナンスリース契約の特徴
所有権が移転しない、所有権移転外ファイナンスリース契約は、リース期間が終了しても資産の所有権はリース会社に帰属し続ける契約方法です。そのため、借り手側は資産を返却する義務があります。所有権移転外ファイナンスリース契約は、最新の設備や技術を柔軟に導入できる点が特徴です。例えば、IT機器や製造機械のように技術革新が早い分野では、数年後には陳腐化してしまう可能性があります。
所有権移転外リースを利用すれば、リース期間満了時に新しいモデルに切り替えやすくなり、常に最新の状態を保てます。
また、資産を自社で所有しないため、固定資産税の支払いや減価償却費の計算といった複雑な資産管理業務を行う必要がありません。さらに、リース料は全額が経費として計上できるため、税務上のメリットもあります。会計上の煩雑さやリスクを避けたい場合は、所有権移転外ファイナンスリース契約が最適と言えるでしょう。
ファイナンスリースを利用する企業のメリット
ファイナンスリースは、企業が設備投資を行う際の有効な資金調達手段の一つです。銀行借入や自己資金による購入とは異なり、リース会社が代わりに設備を購入し、企業はリース料を支払って利用できます。初期費用の負担を軽減できるだけでなく、契約期間にわたって支出を均等化できるため、資金繰りの安定につながります。
また、リース契約は原則として解約不能であるため、長期的な計画のもとで安定した利用が見込めます。さらに、会計や税務の観点からもメリットがあり、リース料を損金算入できることで節税効果が期待できます。担保や登記を必要としないため、資金調達の効率化や事務負担の軽減にも寄与します。具体的にファイナンスリースを利用する企業のメリットは、以下のとおりです。
- 初期投資を抑えて支払額を平準化し資金繰りを安定させる
- 会計処理が明確になり税務上の損金算入が可能となる
- 担保や登記を不要にして契約事務と資金調達を効率化
それぞれ順に解説します。
初期投資を抑えて支払額を平準化し資金繰りを安定させる
ファイナンスリースを利用するメリットは、初期投資を抑えながら設備を導入できる点です。一般的に機械や車両、IT機器などを購入する場合、多額の資金を一括で準備する必要があります。しかし、リースを利用すれば、必要な設備を即時に導入でき、支払いは月額リース料として分割されるため、資金繰りが大幅に楽になります。
また、支払額が契約期間中一定に設定されることが多いため、毎月のキャッシュフローを予測しやすく、計画的な資金管理が可能になります。景気変動や売上の波に影響されにくくなる点も大きなポイント。特に中小企業やベンチャー企業のように資金に余裕がない場合、リースを活用することで事業拡大や新規プロジェクトの開始をスムーズに進められます。このように、ファイナンスリースは成長段階にある企業にとって資金繰りの安定は大きなメリットと言えるでしょう。
会計処理が明確になり税務上の損金算入が可能となる
ファイナンスリースのメリットとして、会計処理や税務対応が明確になる点です。通常の設備購入では減価償却資産として処理する必要があり、耐用年数に基づいた複雑な会計処理が求められます。しかし、リース契約であれば、リース料を毎期の費用として計上できるため、損益計算がシンプルになります。
さらに、法人税の計算においてもリース料を損金に算入できるため、課税所得の圧縮が可能です。資金繰りの改善にも直結し、結果として節税効果を期待できます。
また、税法上もファイナンスリースに関する取り扱いが明確に定められているため、企業側としても安心して利用できます。特に設備投資額が大きくなりがちな製造業や運輸業、IT関連企業においては、リースの会計上・税務上のメリットが大きいでしょう。
担保や登記を不要にして契約事務と資金調達を効率化
ファイナンスリースの利点として、契約に際して担保や登記が不要な点も挙げられます。通常、銀行融資で資金を調達する場合、資産を担保に差し入れたり、登記手続きを行ったりする必要があります。時間とコストがかかり、事務作業の負担も大きくなります。しかし、リース契約では、リース会社が設備の所有権を持ち、利用者は使用権を得るだけの仕組みであるため、担保や登記の手続きは不要です。結果的に契約から導入までのスピードが速く、必要な設備を迅速に利用できます。
また、担保を差し入れないことで企業の信用枠を温存でき、追加の資金調達余力を確保できます。金融機関からの借入と並行して柔軟に資金計画を立てられる点も大きなメリット。効率的な資金調達と事務負担の軽減を実現するファイナンスリースは、経営のスピード感を重視する企業に最適な手法と言えるでしょう。
ファイナンスリース導入時の企業デメリット
ファイナンスリースの利用はメリットだけではなく、中途解約ができないことによる負債を抱えるリスクや金利や手数料によるコストの圧迫があります。契約時には資産と負債を計上する必要もあるため、財務負担や残価設定・耐用年数などの税務処理が必要になります。具体的なファイナンスリースを導入する際のデメリットは、以下のとおりです。
- 中途解約が難しく長期的に負債を抱えるリスク
- 金利や手数料を含むため総支払額が購入より割高
- 契約時に資産と負債を計上し財務負担が増える可能性
- 残価設定や耐用年数など税務処理が複雑になりやすい
それぞれ順に解説します。
中途解約が難しく長期的に負債を抱えるリスク
ファイナンスリース契約は、原則として中途解約が認められていない点が大きなデメリットです。解約不能の性質は、企業にとって長期的なリスク要因と言えます。一度契約を締結するとリース物件が事業内容の変化や技術の陳腐化によって不要になったとしても、契約期間が満了するまでリース料を支払い続けなければなりません。仮にリース会社の合意を得て解約できたとしても、通常は残りのリース料全額に相当する高額な違約金や規定損害金の支払いが発生します。
実質的に、一括で将来の負債を清算するようなものであり、企業のキャッシュフローに深刻な影響を与える可能性があります。例えば、最新のIT機器をリースで導入したものの、数年でより高性能な新モデルが登場し、業務効率の観点から入れ替えが必須となった場合、旧機器のリース契約が残っていると、新旧両方のコストを二重で負担するか、多額の違約金を支払って旧契約を解消するかの厳しい選択を迫られます。将来の事業環境の変化に柔軟に対応できない点は、ファイナンスリースを利用する際に最も慎重に検討すべきデメリットと言えるでしょう。
金利や手数料を含むため総支払額が購入より割高
ファイナンスリースは初期投資を抑えられる一方で、物件を現金で購入する場合と比較して総支払額が割高になるというデメリットがあります。リース料の内訳として、物件本体の取得価額だけでなく、リース会社が設定する金利、固定資産税、動産総合保険の保険料、手数料などが含まれています。企業は物件そのものの価値に加えて、リース会社が提供する金融サービスや各種手続きの代行費用を分割で支払っていることになります。特に金利は、リース期間が長期にわたるほど、市場の金利水準が高い時期ほど、総支払額を押し上げる大きな要因となります。
例えば、1000万円の工作機械を導入する場合、自己資金で購入すれば支払いは1000万円で済みますが、リースを利用すると、リース期間中の金利や手数料が上乗せされるため、総額で1100万円や1200万円といった金額を支払うことになります。月々の支払いを平準化でき、購入資金を他の成長投資に回せるといったメリットはありますが、長期的なコスト意識を持つことは不可欠です。導入を検討する際には、単純な月額料金だけでなく、リース期間全体での総支払額を算出し、購入した場合のコストと冷静に比較検討することが重要です。
契約時に資産と負債を計上し財務負担が増える可能性
ファイナンスリース契約を締結すると、リース物件を資産として、将来支払うべきリース料の総額を負債としてバランスシートに計上する必要があります。リース会計に関する会計基準によって定められており、実質的に借入金で資産を購入したのと同じような会計処理が求められます。オンバランス化が企業の財務状況に直接的な影響を及ぼす可能性があり、負債の部に多額のリース債務が計上されることで、自己資本比率や負債比率といった財務の健全性を示す経営指標が悪化するリスクがあります。
例えば、自己資本が1億円、総資産が5億円の企業が、5000万円のリース契約を結んだ場合、資産と負債がそれぞれ5000万円ずつ増加し、自己資本比率は18.2%から16.7%へと低下します。金融機関は融資審査の際にこれらの財務指標を重視するため、指標の悪化は企業の信用格付けに悪影響を与え、将来の資金調達が困難になったり、借入金利が上昇したりする可能性があります。
リースは初期費用を抑える手段ではありますが、会計処理の結果として企業の財務基盤を圧迫し、資金繰りを悪化させるなどの予期せぬ財務的負担を招くリスクを抱えていると言えます。
残価設定や耐用年数など税務処理が複雑になりやすい
ファイナンスリースは、会計処理および税務処理が複雑になりやすいデメリットがあります。特にリース契約終了時の資産の価値である残価を設定する契約や資産の法定耐用年数とリース期間が一致しない場合、非常に複雑な税務処理が発生します。
会計上リース資産は自社で購入した資産と同様に資産計上し、減価償却を行う必要があります。減価償却の計算方法が難しく、所有権移転リースでは法定耐用年数を、所有権移転外リースではリース期間を償却期間として定額法で計算するのが原則ですが、税務上の法定耐用年数との兼ね合いを考慮する必要があり、専門的な知識が求められます。
さらに、残価が設定されている場合、減価償却の対象となる金額は「リース料総額から残価を差し引いた金額」となり、計算がより一層複雑化します。契約終了時に市場価格が想定残価を大きく下回った場合、差額の処理も発生します。
また、税務申告の際には、会計上の利益と税法上の課税所得を調整するための申告調整が必要になるケースも少なくありません。さまざまな複雑な処理は、経理担当者の業務負担を増大させるだけでなく、専門知識が不足していると誤った処理をしてしまい、後日、税務調査で指摘を受けるリスクも高まります。税理士などの専門家への相談費用が発生することも含め、管理コストの増加はデメリットとして把握しておきましょう。
ファイナンスリースの仕訳方法をわかりやすく解説
ファイナンスリースの仕訳は残価設定や耐用年数の設定などの影響で、複雑化しており難しいと感じる人も多いでしょう。しかし、契約時の計上方法や毎月の処理方法、オンバランス処理などを把握しておけば、スムーズにファイナンスリースの仕訳方法を認識できます。
- 契約開始時に資産とリース債務を同額で計上
- 毎期の支払リース料を元本と利息に分けて処理
- 資産を耐用年数に応じて減価償却費として費用化
- 新リース会計基準ではオンバランス処理が原則
ここでは、ファイナンスリースの仕訳方法をわかりやすく解説します。
契約開始時に資産とリース債務を同額で計上
ファイナンスリースの会計処理は、契約開始時の仕訳が重要です。リース取引を「資産の購入と、そのための資金調達」と見なす考え方に基づいており、リースする製品を企業の「資産」として、将来支払うべきリース料の総額を「負債(リース債務)」として、同額で貸借対照表に計上します。原則として「リース料総額の割引現在価値」と「リース物件の現金購入価額」のいずれか低い方の金額を採用します。
割引現在価値とは、将来の支払いを現在の価値に換算したもので、金利の要素を考慮した合理的な計算方法です。例えば、500万円の価値がある機械をリース契約した場合、借方に「リース資産 500万円」、貸方に「リース債務 500万円」と仕訳します。企業がその資産を使用する権利を得たことと、それに対応する支払い義務を負ったことが財務諸表上で明確に表現されます。
毎期の支払リース料を元本と利息に分けて処理
ファイナンスリース契約に基づき、毎月または毎年リース料を支払う際の仕訳は、単なる経費計上とは異なります。支払うリース料は、借入金の返済と同様に元本の返済部分と利息の支払部分の二つの要素で構成されています。そのため、仕訳もこの二つに分けて処理する必要があります。
具体的には、リース債務の残高に一定の利率を掛けて、その期の支払利息を計算します。実際に支払ったリース料の総額から、支払利息を差し引いた金額が「リース債務(元本)」の返済額となります。
例えば、年間リース料60万円を支払い、計算上の支払利息が8万円だった場合、仕訳は借方に「リース債務 52万円」と「支払利息 8万円」、貸方に「現金預金 60万円」となります。負債であるリース債務が着実に減少していく様子と、資金調達のコストである利息が費用として損益計算書に計上される過程が正確に記録されます。利息の計算方法には「利息法」という方法を用いるのが一般的で、期首の負債残高に基づいて計算するため、返済が進むにつれて利息部分は減少し、元本返済部分が増加していくことになります。
資産を耐用年数に応じて減価償却費として費用化
ファイナンスリースで導入した資産は、自社で購入した固定資産と同様に、価値の減少を会計に反映させるための減価償却を行う必要があります。契約開始時に資産として計上したリース資産の取得価額を、一定の期間にわたって規則的に費用として配分していく手続きです。費用化された金額を減価償却費と呼び、損益計算書に計上します。減価償却を行う期間は、原則としてそのリース契約で定められたリース期間となります。
例えば、リース期間が5年の機械であれば、5年間にわたって減価償却を行うのが基本です。計算方法としては、毎期均等額を費用化する定額法が一般的に用いられます。ただし、リース契約に割安購入選択権が付いている場合や所有権が最終的に企業に移転する条件になっている場合は、資産本来の経済的な使用可能期間である法定耐用年数を基に減価償却期間を設定します。減価償却というプロセスを通じて、資産の使用による収益と資産価値の減少を適切に対応させることができ、より実態に即した損益計算が可能になります。
新リース会計基準ではオンバランス処理が原則
近年の会計基準の大きな変更点として、新リース会計基準の適用が挙げられます。これまで貸借対照表に計上しない処理であるオフバランス処理が認められていた一部のリース契約についても、原則としてオンバランス処理を求めるようになりました。オンバランス処理とは、すべてのリース契約について借手に使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上する方法を指します。
以前の基準では、ファイナンスリースはオンバランス、オペレーティングリースはオフバランスと区別されていましたが、区別が原則として撤廃されました。投資家などが企業の隠れた債務を把握できず、財務実態を正確に評価できないことから、新リース会計基準が設けられています。
新基準の適用により、企業がどれだけのリース契約を結び、将来にわたってどれだけの支払い義務を負っているのかが財務諸表上で一目瞭然となり、財務の透明性が格段に向上しました。企業側はリース戦略を見直す必要に迫られる一方、投資家はより精緻な企業分析が可能です。ファイナンスリースの会計処理は近年の会計ルールを理解する上で必須と言えるでしょう。
ファイナンスリースに関するよくある質問に回答
オペレーティングリースとの違いはどのような点ですか?
ファイナンスリースとオペレーティングリースの代表的な違いは、金融取引に近いか、賃貸借取引とされています。ファイナンスリースは、実質的にリース会社が企業の代わりに設備を購入し、その代金と金利、諸経費を分割で回収する金融取引の性格が強い契約です。
そのため、契約期間中の解約が原則として認められない解約不能の条件と、リース料総額で物件の取得価額の大部分を賄うフルペイアウトの要件を満たすものと定義されています。会計処理上も、資産を購入した場合と同様に、リース資産とリース債務を貸借対照表に計上するオンバランス処理が求められます。
一方、オペレーティングリースは、純粋なレンタルに近い賃貸借取引です。契約期間は物件の耐用年数より短く設定されることが多く、リース料総額も物件価額の一部に留まります。会計処理も、支払ったリース料を賃借料などの費用として計上するだけで、貸借対照表には資産や負債として記載されません。
ファイナンスリースは個人事業主でも利用できますか?
ファイナンスリースは法人だけでなく、個人事業主やフリーランスでも利用が可能です。多くのリース会社は、事業規模を問わず設備投資を検討している事業者向けにサービスを提供しています。特に個人事業主にとって、事業を開始する際や拡大する際に必要な高額な機器を、多額の初期投資なしで導入できる点は大きなメリットです。
自己資金を運転資金として手元に残しつつ、事業に必要な資産を確保できるため、キャッシュフローの安定化に繋がります。月々の支払額が一定であるため、経費の管理がしやすいという利点もあり、計画的な事業運営を目指す個人事業主にとって、ファイナンスリースは非常に有効な資金調達手段の一つと言えるでしょう。
ファイナンスリースに節税効果は本当にあるのですか?
ファイナンスリースには条件付きで節税効果があると言えます。ファイナンスリースは会計上で売買があったものと見なされ、リース資産を自社の資産として計上し、減価償却費として複数年にわけて費用化します。
しかし、中小企業の場合、「中小企業の会計に関する指針」に基づき、所有権が移転しない所有権移転外ファイナンスリースを、通常の賃貸借取引と同様に処理することが認められています。毎月支払うリース料をそのまま全額経費として計上できるため、会計処理がシンプルになり、節税につながりやすくなるでしょう。
契約終了後に資産を購入することは可能ですか?
ファイナンスリースの契約が満了した際、契約内容によってはリース資産を自社のものとして購入できる場合があります。ただし、自動的に認められる権利ではなく、当初のリース契約の内容によって選択肢が定められています。一般的に、リース期間終了後の選択肢には、以下が挙げられます。
- 資産をリース会社に返還する
- 格安のリース料で契約を更新する再リース
- 資産を買い取る
購入を選択できるかどうか、購入価格がいくらになるかは、契約書にどのように記載されているかで決まります。例えば、契約時に将来の購入を前提として、名目的な価格や市場価格より著しく有利な価格で購入できる権利を付帯させておくケースがあります。契約終了時にその定められた価格で資産を買い取ることができます。
一方で、特約がない場合は、契約終了時点での市場価格や、リース会社との協議によって購入価格が決定されます。将来的にその資産を所有したいという意向が強いのであれば、リース契約を締結する段階で、購入の可否やその際の条件についてリース会社と明確に取り決め、契約書に盛り込んでおきましょう。

