今回は「オペレーティングリース」という経営手法について解説します。自社が高額の設備投資をして、事業を展開していくことが重要な経営戦略になります。しかし、高額な設備投資は当然ハイリスクです。うまくいき、事業が伸びれば設備投資した高額の機材は大切な財産、資産になりますが、うまくいかなかった場合、高額の不良債権を抱えることになってしまいます。
設備投資で購入する場合、このようなリスクがありますが、リース契約ならば「借りる」ので自社の負債になる可能性は低く、ダメだと思えばリース契約を解消すれば良いわけです。
このリース契約には「オペレーティングリース」と「ファイナンスリース」と言うものがあります。今回はそのうち「オペレーティングリース」を中心に解説していきます。重要な会計処理の方法もぜひ覚えていただき、みなさまの会社で役立つ経営手法として身に着けていただければと存じます。
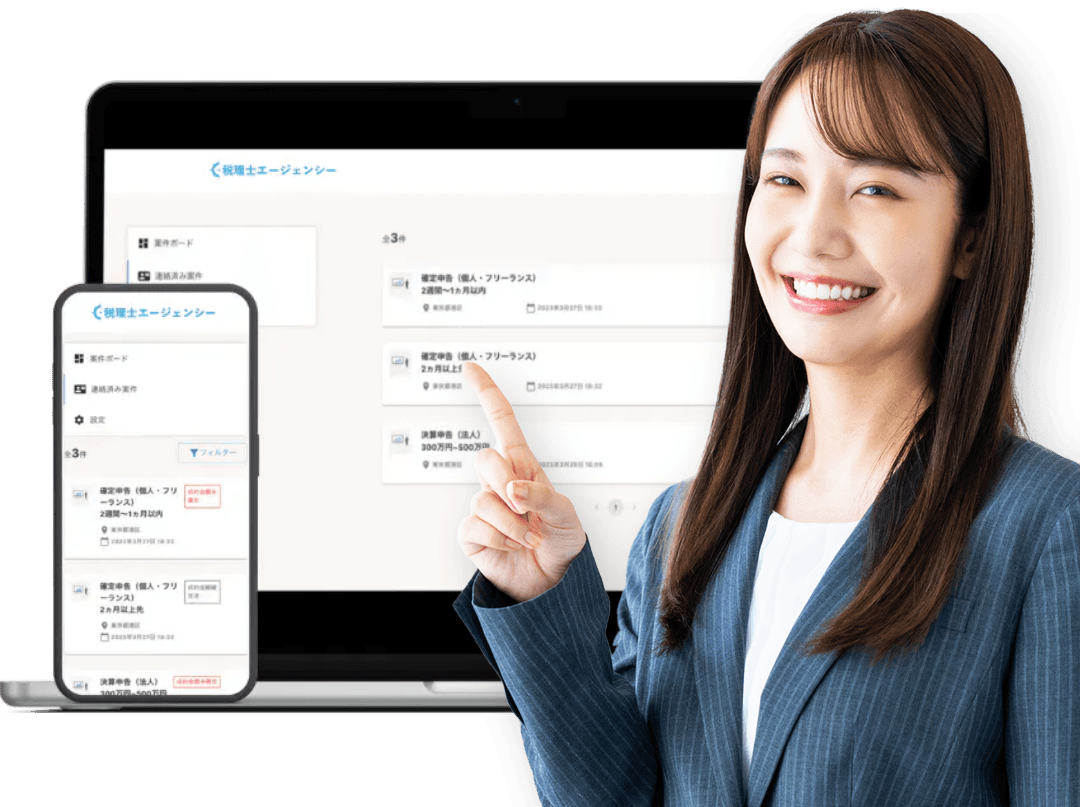
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
オペレーティングリースとは資産を所有せず利用する契約形態
オペレーティングリースとは、企業が資産を自ら購入・所有するのではなく、一定期間だけ利用することを目的とした契約形態です。通常、リース会社が機械設備や車両、航空機、不動産などの資産を保有し、利用者はその資産をレンタル料にあたるリース料を支払うことで使用できます。高額なものも購入せずリースで済ませる経営手法です。
オペレーティングリースの特徴は、資産を所有しないため貸借対照表に計上されず、資産の購入に伴う多額の初期投資や残存価値のリスクを避けられる点にあります。そのため、資金繰りを圧迫せず柔軟に経営資源を活用できるメリットがあります。さらに、契約期間終了後は資産を返却するだけで済むため、価値がなくなってしまうリスクや維持管理負担も軽減されます。設備投資の選択肢として、財務戦略や資金効率の観点から多くの企業に利用されている仕組みです。
住宅でたとえると「デザイナーズマンションを所有しているオーナーから賃貸で借りて住む」みたいなイメージになります。賃貸マンションより豪華だが、災害などで建物の価値が減るリスクや修繕費はオーナー負担になるような感じです。
- 航空機・船舶・建設機械・IT機器など高額資産で活用される
- オペレーティングリースとファイナンスリースの違いを解説
ここではオペレーティングリースの概要について解説していきます。
航空機・船舶・建設機械・IT機器など高額資産で活用される
オペレーティングリースは、航空機や船舶、大型の建設機械、さらにはIT機器などの高額な資産に広く用いられる契約形態です。企業が自社で購入するには多額の初期投資が必要となるこれらの資産を、所有せずに利用できる点が大きな特徴です。
リース会社が資産を保有し、利用者(事業主様)はリース料を支払うことで一定期間だけ使用する仕組みのため、資金負担を抑えつつ必要な設備を導入できます。また、契約終了時には返却すれば良く、資産価値の下落や陳腐化リスク(経済的価値や希望的価値を失うという経済用語)を回避できるのもメリットです。
特に航空機や船舶は、技術革新や市場環境の変化が速く、保有リスクが大きいためリース活用の需要が高まっています。高いお金を払って購入しても、その返済が終わらないうちに高性能な新型が出てしまい、せっかくのお金が無駄になってしまいます。高額資産の効率的利用と財務の柔軟性確保の観点から、多くの企業がオペレーティングリースを積極的に導入しています。
オペレーティングリースとファイナンスリースの違いを解説
オペレーティングリースとファイナンスリースは、どちらも資産をリース会社から借り受けて利用する仕組みですが、その性質には明確な違いがあります。
オペレーティングリースは「所有せずに利用する」形態であり、契約期間も資産の耐用年数より短く設定されるのが一般的です。契約終了後は返却が基本で、残存価値リスクや資産管理の負担はリース会社が負います。そのため、利用企業は資金負担を軽減しつつ、柔軟に設備を導入できます。
一方、ファイナンスリースは実質的に「分割払いで購入する」性質が強く、解約ができず、契約期間中に支払うリース料で資産の取得価額と利息相当分をすべて回収する仕組みです。資産や負債として貸借対照表に計上され、経営上の責任は利用企業側にあります。
オペレーティングリースとファイナンスリースの比較表
| 項目 | オペレーティングリース | ファイナンスリース |
|---|---|---|
| 契約期間 | 短期(耐用年数未満) | 長期(耐用年数に近い) |
| 中途解約 | 可能なこともある | 原則不可 |
| 残存価値リスク | リース会社が負担 | 利用者が負担 |
| 会計処理 | 費用・損金計上(オフバランス化可能) | 資産・負債計上 |
オペレーティングリースは所有権を移転せず短期利用に適する
オペレーティングリースは、資産の所有権を利用者に移転せず、一定期間だけ使用することを目的とした契約形態です。契約期間は資産の耐用年数よりも短く設定されるのが一般的で、利用が終われば資産を返却するだけで済むため、長期的な保有リスクを避けられます。
購入するときのように多額の初期投資を必要とせず、また残存価値や老朽化による資産価値の減少もリース会社が負担するため、利用企業はコスト予測を立てやすい点が特徴です。特に航空機や船舶、建設機械、IT機器など高額で陳腐化しやすい資産において活用されるケースが多く、資金繰りの安定や設備更新の柔軟性を確保する手段として選ばれています。
資産を所有することにこだわらず、必要なときに必要な設備を導入できるため、変化の激しい経営環境に適した方法と言えます。
ファイナンスリースは実質的に購入と同じ扱いとなる契約形態
ファイナンスリースは、形式上はリース契約ですが、実質的には資産を分割払いで購入するのと同じ性質を持つ契約形態です。リース会社が利用者の希望する資産を購入し、それを長期間にわたり貸し出す仕組みで、契約期間中に支払うリース料には資産の取得価額と利息相当分が含まれています。
そのため、契約期間終了までにリース会社の投資が全額回収される点が特徴です。中途解約は原則として認められず、利用企業は資産の維持管理や残存価値リスクも負うことになります。会計上は、資産と負債の両方を貸借対照表に計上する必要があり、減価償却や利息費用として処理されます。つまり、ファイナンスリースは資金調達の一形態であり、資産を購入した場合とほぼ同じ責任と義務を伴う契約だと言えます。
財務・税務上の影響を踏まえてどちらを選択するかを検討する
リース契約を選ぶ際には、オペレーティングリースとファイナンスリースの特徴を踏まえ、財務・税務上の処理を考慮することが重要です。オペレーティングリースは資産を所有せず短期間だけ利用するため、貸借対照表に計上されず、初期投資や残存価値リスクを抑えられます。資金繰りへの影響が小さく、費用としてリース料を損金算入できるため、税務上のコスト計上がシンプルである点もメリットです。
一方、ファイナンスリースは実質的に資産を購入する扱いとなり、貸借対照表に資産・負債として計上されます。減価償却や利息費用の計上が必要で、長期的な財務負担や資産管理責任が発生します。したがって、手持ち資金改善や単年度の節税を重視する場合はオペレーティングリースを利用、高額な資産を長期的に使用し、購入した場合と同等の会計処理を望む場合はファイナンスリースを選択する、と言うように両者を上手に使い分けてください。
オペレーティングリースを利用する企業のメリット
オペレーティングリースを活用することは、企業にとって効率的な経営手法のひとつです。自社で資産を購入・所有せずに、必要な期間だけ利用できるため、多額の初期投資を回避しつつ最新の設備や機器を導入できます。
契約満了後は返却すれば良いため、資産価値の下落や維持管理に伴うリスクを負わずに済む点も魅力です。さらに、リース料を費用として処理できるケースが多く、財務面での支払い負担軽減や指標の改善にも寄与します。
- リース料の損金算入により減価償却が不要になる
- 資産価値の減少リスクを避けバランスシートを軽くできる
- 設備更新を柔軟に行い競争力を長期的に維持できる効果
それぞれ順に解説します。
リース料の損金算入により減価償却が不要になる
オペレーティングリースを利用する大きな特徴のひとつが、リース料の損金算入によって減価償却が不要となる点です。通常、企業が資産を購入した場合、その取得価額を耐用年数に応じて毎期減価償却費として計上しなければならず、会計処理が煩雑になるうえ、貸借対照表にも資産・負債が増加します。その年に100%経費にできず、数年~数十年にわたって均等に減価償却費として経費計上します。
しかし、オペレーティングリースでは資産を所有せず、単に利用するだけの契約となるため、毎期支払うリース料をその期に全額費用として処理できます。その結果、減価償却計算や固定資産管理の手間が不要となり、経理業務の簡素化につながります。また、資産や負債として計上しないため、財務諸表上の総資産を抑え、自己資本比率などの財務指標を良好に保てる効果もあります。資金効率を重視しつつ、会計・税務処理をスリム化したい企業にとって、オペレーティングリースは有効な選択肢と言えるでしょう。
資産価値の減少リスクを避けバランスシートを軽くできる
オペレーティングリースによって企業は資産価値の減少リスクを回避しつつ、バランスシートをスリム化することが可能となります。通常、資産を購入すると取得時点から市場価値の下落や老朽化による陳腐化リスクを自社で抱え込む必要がありますが、リース契約では所有権がリース会社にあるため、利用企業がそのリスクを負うことはありません。
さらに、会計上は資産や負債として計上せず、支払ったリース料を費用処理できるため、総資産や負債を増やさずに済みます。その結果、自己資本比率や総資産利益率といった財務指標を良好に維持でき、財務内容を健全に見せやすいメリットがあります。特に資産規模の拡大を避けつつ機動的な事業運営を進めたい企業にとって、オペレーティングリースはリスク分散と財務戦略の両面から有効な手段と言えます。
設備更新を柔軟に行い競争力を長期的に維持できる効果
オペレーティングリースには設備更新を柔軟に行える点もあります。契約期間が資産の耐用年数より短く設定されるため、契約終了後には返却して新しい設備へと入れ替えることが容易です。特に、技術革新のスピードが速いIT機器や、年々厳しくなる環境規制への対応が求められる建設機械・輸送機器などでは、常に最新仕様を導入できることが競争力の維持につながります。
また、資産を保有しないため、必要に応じて最適な設備に更新できる点もメリットです。新しい画期的な設備ができれば、そちらのリースに切り替えることで、柔軟かつ機動的な経営が可能になります。
オペレーティングリースを導入する際のデメリットと注意点
オペレーティングリースはメリットばかりではありません。オペレーティングリースは、初期投資を抑えつつ設備を利用できるメリットがありますが、導入にあたってはデメリットや注意点も押さえておく必要があります。普通にリースではなく購入した方が自社にとってメリットが大きいケースも当然存在します。
オペレーティングリースの契約期間中はリース料の支払い義務が発生するため、長期的には購入よりも総コストが高くなる場合があります。また、リース資産は所有権が移転しないため、自由に改造や売却ができない点も制約となります。
さらに、契約条件や残存価格の設定によっては、契約終了後の資産取得や再リースに柔軟性が欠けることがあります。会計面では、国際会計基準の適用によりオンバランス化が求められる場合があり、貸借対照表や損益計算書への影響を確認する必要があります。そのほか、税務上の処理や契約内容の細部も慎重に確認し、資金繰りや事業計画との整合性を考慮したうえで導入判断を行うことが重要です。
- 中途解約が難しく契約期間の柔軟性が制限される
- 為替変動や残価設定によるコストリスクを抱える可能性
- 税制や会計基準改正によって将来影響を受けるリスク
それぞれ順に解説します。
中途解約が難しく契約期間の柔軟性が制限される
オペレーティングリースは資産を所有せずに利用できる利点がある一方で、デメリットとして次に挙げるのが、中途解約の難しさです。契約期間中に利用をやめたい場合でも、原則として途中解約は認められず、解約する場合には違約金や残存期間のリース料をまとめて支払う必要が生じるケースがあります。ファイナンスリースよりは中途解約はできますが、それでも一定の要件、手続きを必要とします。
そのため、契約時に利用期間を慎重に見極めることが不可欠です。また、長期間にわたってリース料を支払うことになるため、総支払額が資産を直接購入した場合より高くなる可能性もあります。さらに、利用できる資産や契約条件はリース会社が提示する内容に合わせるため、自社の希望に完全に沿わない場合もある点に注意が必要です。コスト面や契約の柔軟性を十分に検討したうえで導入を判断することが求められます。
為替変動や残価設定によるコストリスクを抱える可能性
資産を所有しないことで得られるメリットがある一方、為替変動や残価設定に伴うコストリスクを抱える可能性もあります。特に航空機や船舶など海外から調達される高額資産の場合、契約通貨が外貨建てとなるケースが多く、為替レートの変動によってリース料の実質的な負担額が変わるリスクがあります。
また、契約時に設定される残存価値(リース終了時の資産価値)によってリース料水準が決まるため、実際の市場価値が想定より下落した場合には、リース会社がリスクを転嫁し、利用料に上乗せされる可能性も否定できません。こうしたリスクは利用企業の財務負担に直結するため、契約条件の妥当性や為替ヘッジの有無を慎重に確認する必要があります。リスク管理を意識した導入判断が欠かせないと言えるでしょう。
税制や会計基準改正によって将来影響を受けるリスク
税制や会計基準の改正によって将来的に影響を受けるリスクです。従来、オペレーティングリースは資産や負債を貸借対照表に計上せず、リース料を単純に費用処理できる点が大きな魅力とされてきました。しかし、国際会計基準(IFRS)や日本基準においてもリース会計の見直しが進められており、一定の条件下ではオペレーティングリースであっても利用権資産やリース債務として計上が求められる可能性があります。
こうしたルール変更が行われ、それに従うことになった場合、財務指標への影響や資産規模の肥大化が避けられず、経営戦略の再検討を迫られるケースも考えられます。オフバランス化の逆で、バランスシートが大きくなってしまいます。
さらに、税制改正によって損金算入の範囲や方法が変われば、コスト計上のメリットが薄れる懸念もあります。そのため、導入企業は制度改正の動向を常に把握し、長期的な影響を見据えたリース活用を検討する必要があります。
オペレーティングリースの仕訳方法は費用処理が中心
オペレーティングリースは、資産を所有せず一定期間使用することを目的としたリース契約であり、会計上の仕訳も基本的に「費用処理」が中心となります。従来の日本基準では、リース資産やリース債務を貸借対照表に計上せず、支払ったリース料を発生した期間の経費として処理するのが原則です。
このため、資産計上や減価償却の手間が不要で、費用を損益計算書に直接反映できる点が特徴です。企業は、オペレーティングリースを利用することで、初期投資を抑えつつ必要な設備を活用でき、キャッシュフローの管理も容易になります。
ただし、国際会計基準(IFRS16など)の適用により、オペレーティングリースであっても貸借対照表計上が求められる場合があるため、適用基準に応じた仕訳方法の確認が重要です。
- 借手は支払リース料を賃借料として処理するのが基本
- 資産計上や減価償却は不要で節税効果を得やすい仕組み
それぞれ順に解説します。
借手は支払リース料を賃借料として処理するのが基本
オペレーティングリースの会計処理は、基本的に費用を賃借料として処理するのが特徴です。借手企業はリース資産を所有しているわけではないため、資産や負債として貸借対照表に計上する必要はありません。その代わりに、リース料を支払った際には「賃借料」や「リース料」といった科目を用いて損益計算書に費用として計上します。
これにより、購入資産のように減価償却を行う必要がなく、処理がシンプルになる点が大きな利点です。ただし、支払いが複数期にわたる場合には、発生主義にもとづいて期間按分を行い、適切な会計処理を行う必要があります。また、リース契約に付随する保守料やサービス費用がある場合は、リース料と区分して処理するのが望ましいとされています。
こうした費用処理中心の仕訳方法により、オペレーティングリースは経理実務を簡素化できます。
資産計上や減価償却は不要で節税効果を得やすい仕組み
オペレーティングリースは、資産計上や減価償却を行う必要がないため、会計処理や税務面でのメリットが大きい仕組みとされています。通常、資産を購入すれば固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行う必要がありますが、オペレーティングリースの場合は所有権が借手に移転しないため、この処理は不要です。
その代わり、支払うリース料を全額「賃借料」や「リース料」としてその年の損金に算入できるため、課税所得を直接圧縮する効果が期待できます。特に高額な設備や機械を導入する際、購入した場合と比べて資金繰りを圧迫せず、税務上も費用計上による節税効果を得やすい点が大きな利点です。
また、貸借対照表に資産や負債を計上しないことで財務指標が軽く見え(オフバランス化)、金融機関や投資家への印象を良くする側面もあります。機動的で「筋肉質」な経営をオペレーティングリースは実現します。
オペレーティングリースに関する良くある質問
オペレーティングリースについてまだ日本では広く周知されていないこともあるため、ここでQ&A形式での質問にお答えします。疑問点をなるべく潰しながら、顧問税理士や経営コンサルタントと相談して、設備の資金機購入ではなくオペレーティングリース導入の可否を決めてください。
オペレーティングリースのメリット、デメリットそれぞれあるので、導入だけが正解ではありません。疑問点が解消できないならば当面見送るのも自社の経営を守る判断として適切です。
そういうこともあり、しっかりこのQ&Aで疑問点を解消しておきましょう。
オペレーティングリース契約終了後に資産を購入することはできる?
オペレーティングリース契約終了後にリース資産を購入できるかどうかは、契約内容によって異なります。基本的にオペレーティングリースは、資産を所有せず一定期間利用することを目的とした契約であり、リース終了後は返却するのが原則です。
ファイナンスリースのように「所有権移転」を前提とした仕組みではないため、契約終了時に自動的に購入できる制内容にはなっていません。しかし、実務上はリース会社との交渉次第で購入が認められるケースもあります。たとえば、航空機や船舶、不動産関連設備など長期にわたり使用される高額資産では、契約終了後に残存価格で買い取るオプションが個別に取り決められる場合があります。
購入価格は市場価値や残存簿価を基準に設定されることが多く、必ずしも割安になるとは限りません。そのため、導入当初から「契約終了後に取得する可能性があるか」を想定しておくことが重要です。もし利用目的が資産の一時使用にとどまらず、最終的に所有する可能性があるなら、ファイナンスリースやローン購入との比較を行い、コストや会計、財務諸表への影響も比較してください。最初から分割払いでも購入した方が良いかもしれません。
オペレーティングリース資産を貸借対照表に計上する必要はある?
原則、必要ありません。しかし、オペレーティングリースの資産を貸借対照表に計上するかどうかは、適用する会計基準によって扱いが異なります。従来の日本基準では、オペレーティングリースは「資産を所有するのではなく利用する取引」と位置付けられており、借手側は貸借対照表にリース資産やリース債務を計上せず、支払うリース料を費用として処理するのが原則でした。
しかし、国際会計基準(IFRS)や米国会計基準(US-GAAP)では、2019年以降、原則すべてのリース契約を「使用権資産」と「リース負債」として認識することが義務付けられています。これにより、オペレーティングリースであっても契約期間に応じた資産と負債を貸借対照表に計上する必要が生じます。
日本国内の会計基準でも今後は国際的な基準に近づく可能性があり、特に上場企業や国際取引の多い企業は注意が必要です。したがって、適用する基準や契約条件を踏まえ、自社にとってどのような会計処理が必要となるかを確認することが不可欠です。
オペレーティングリースは必ず節税効果があるのですか?
オペレーティングリースを利用すれば必ず節税効果が得られる、というわけではありません。確かに、従来の日本基準にもとづく会計処理では、オペレーティングリースは資産計上や減価償却を行わず、支払ったリース料をそのまま損金算入できるため、費用処理を前倒しできる点で「節税につながりやすい」と言われてきました。
特に高額な設備のリースでは、減価償却ではなく一期ごとに安定して費用を計上できるため、利益の平準化やキャッシュフローの改善効果が期待できます。しかし、これは契約条件や企業の利益状況によって大きく左右されます。
利益が少ない年度に多額のリース料を支払っても、そもそも課税所得が小さければ節税メリットは限定的です。また、IFRSや米国会計基準ではオペレーティングリースも貸借対照表に計上する方式が採用されており、従来のようなオフバランス化による効果は減少しています。したがって、オペレーティングリースの利用=自動的な節税と考えるのは誤りであり、資金繰りや税務計画とのバランスを踏まえて導入を判断することが重要です。
個人事業主でもオペレーティングリースを利用できますか?
個人事業主であっても、一定の条件を満たせばオペレーティングリースを利用することは可能です。オペレーティングリースは法人向けの取引が中心ですが、事業規模や信用力によっては個人事業主も契約できるケースがあります。
たとえば、事業に必要な車両や機械設備、パソコンなどを所有せずに使用したい場合、オペレーティングリースを利用することで初期投資を抑えつつ、毎月のリース料を経費として処理できます。これにより、キャッシュフローを安定させ、資金繰りを安定させる効果が期待できます。
ただし、審査の際には事業実績や売上の安定性、納税状況などが確認されるため、法人に比べて売上規模が小さい個人事業主はオペレーティングリースの契約が難しい場合もあります。
また、対象となるリース商品は高額な設備や不動産よりも、小規模な設備や車両、パソコンなどのリースが中心です。さらに、税務上の効果も事業所得の状況に左右されるため、必ずしも大きな節税につながるとは限りません。
購入した方が最終的に得することも多く、リースしたいものの金額や現在の売上規模、そもそもそれがリースできるものなのかなどを複合的に検討する必要があります。
新リース会計基準導入後は仕訳や税務処理はどう変わりますか?
新リース会計基準(IFRS16など)が導入されると、従来「オペレーティングリース」として費用処理のみで済んでいた契約も、原則として貸借対照表に「使用権資産」と「リース負債」を計上する必要が生じます。これにより、リース取引は実質的に資産を調達して借入を行ったのと同様の仕訳となり、損益計算書でもリース料の単純な費用計上ではなく「減価償却費」と「利息費用」に分けて認識する点が大きな変化です。
例:リース契約開始時の仕訳
使用権資産 XXX/リース負債 XXX
支払期ごとの仕訳
利息費用 XXX/リース負債 XXX
減価償却費 XXX/使用権資産 XXX
税務処理面では、法人税法上は従来通りリース料を損金算入できる仕組みが維持されており、会計上と税務上で処理が乖離する「一時差異」が生じやすくなります。この差異は繰延税金資産・負債として調整が必要となり、実務対応が複雑化します。したがって、新基準導入後は仕訳方法だけでなく、会計と税務の差異管理を徹底することが重要です。
従来の会計基準と新リース会計基準との違いについて表にまとめました。
| 項目 | 適用前(従来会計基準) | 適用後(新リース基準:IFRS16など) |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | 原則、資産・負債に計上しない | 使用権資産とリース負債を計上 |
| 損益計算書 | リース料を支払時に全額費用計上 | 減価償却費+利息費用に分けて計上 |
| キャッシュフロー計上 | リース料の支払いを営業CFに計上 | 元本返済は財務CF、利息は営業CFまたは財務CF(会計基準により) |
| 節税効果 | 支払リース料全額を損金算入可能 | 会計上の費用配分が変わるが、税務上は従来通り損金算入できる場合が多く、一時差異が発生 |
| 会計処理の特徴 | オフバランス化できシンプル | 資産・負債が増加、利益計上タイミングが変化 |
このように、新リース基準導入後は仕訳や損益計算書、キャッシュフローの表示が大きく変わり、会計と税務の整合性管理が必要となります。
少額資産でもオペレーティングリースを活用できますか?
少額資産であっても、条件次第でオペレーティングリースを活用することは可能です。ただし、リース会社側のコストや管理負担を考慮すると、非常に小額の資産では契約が難しい場合があります。
一般的にオペレーティングリースは、初期投資を抑えたい高額設備や車両、機械などでの利用が中心ですが、近年ではIT機器やコピー機、医療機器など中小規模の設備でもリース商品が提供されるケースが増えています。
こうした場合、少額資産でも毎月のリース料を経費として計上できるため、資金繰りの負担を軽減するメリットがあります。また、会計処理の面でも、少額資産を購入する場合は固定資産計上や減価償却が(少額資産の特例を使わない限り)必要ですが、リースであれば費用として一括処理できる点が便利です。
ただし、リース契約には審査や事務手続きが必要であり、少額資産の場合これを踏まえると、購入に比べてコストが割高になる場合もあります。そのため、少額資産での利用を検討する際は、リース料総額と購入費用の比較を行い、総合的に判断することが重要です。

