法人経営の際に、経営者として節税対策を考えるのは当然です。合法的な節税によって税金として取られてしまうものを、自社の経営資源に回せます。
過剰な税金を支払うくらいならば、合法的な節税によってその分を自社の経営に回し、業績アップにつなげられます。あるいは、設備投資や従業員への還元など、会社としての経営改善や社員のモチベーションアップにもつなげられます。
利益が出過ぎたときの節税対策でさまざまなことに使える原資をねん出し、最終的にはそれ以上に売上や利益を伸ばすことが優れた経営者の手腕となります。
今回は税制改正にも対応した法人の節税対策について説明します。「法人の節税対策」ですので、個人事業主やフリーランスの方は使えない対策もあります。その点はご了承ください(個人事業主やフリーランスが使えるものもあります)。それでは解説していきます。
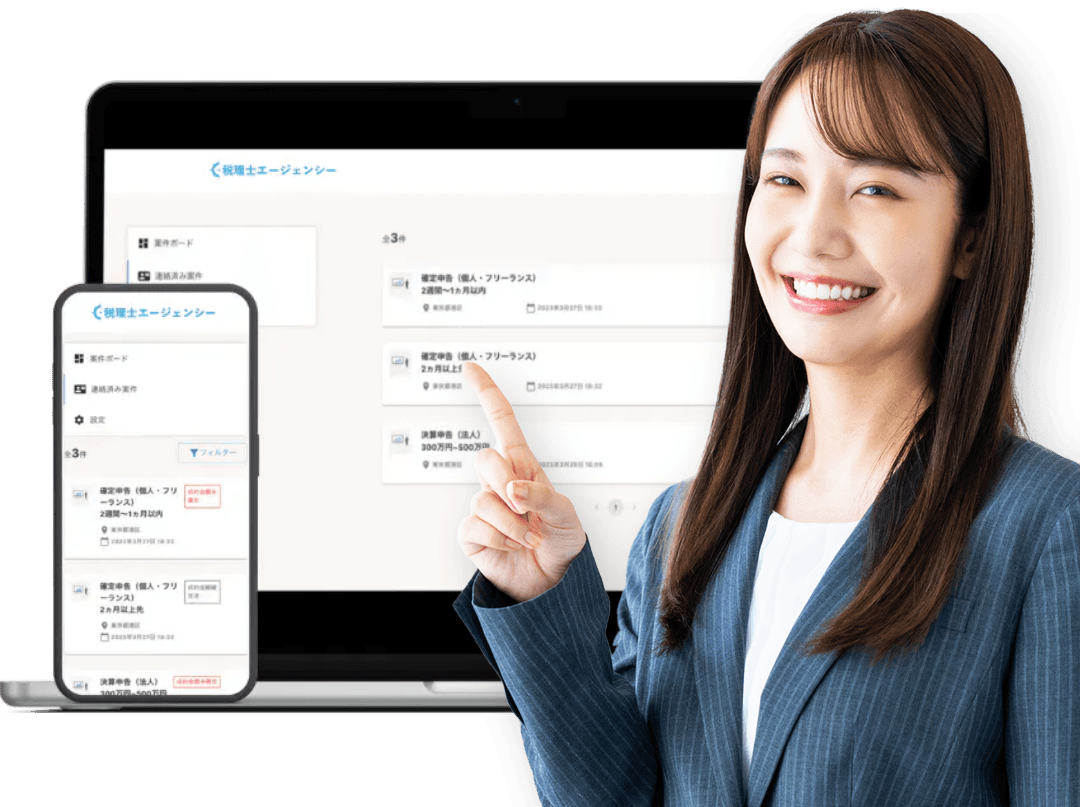
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
法人の節税は合法的な制度活用で税負担を軽減する取組
法人の節税とは、法律に基づいた制度や仕組みを適切に活用し、企業の税負担を軽くするための経営上の戦術、テクニックです。脱税や粉飾、租税回避といった違法・脱法行為とはまったく異なり、節税は認められた範囲の中で経営効率や経営資源を高める手段と言えます。
たとえば、設備投資に伴う各種の税制優遇や、中小企業向けの特別控除制度、福利厚生費の計上など、さまざまな方法が存在します。こうした制度をうまく活用することで、資金繰りを改善し、キャッシュに余裕を持たせ、経営基盤の強化や次の設備投資に資金を振り向けられるようになります。
企業にとって節税は単なるコスト削減策ではなく、事業の持続的な発展を支える経営戦略、経営資源調達の一環と言えるのです。
- 節税と脱税・租税回避の違いを正しく理解する
- 決算前に行動することで節税効果を最大化できる
- 中小企業や高収益法人こそ積極的に活用すべき
それぞれ順に解説します。
節税と脱税・租税回避の違いを正しく理解する
節税と脱税、そして租税回避は似た言葉として扱われがちですが、その本質は大きく異なります。
まず節税とは、法律に定められた制度や仕組みを活用して税負担を軽減する正当で合法的な行為を指します。中小企業向けの各種税控除や設備投資に関する優遇措置、福利厚生費の経費計上などがその代表例であり、国も積極的に利用を認めています。
一方、脱税は法律に反して税金を免れようとする不正行為であり、所得の隠蔽や架空経費の計上などが典型的な手口です。発覚すれば重加算税や罰金、刑事罰に至ることもあります。融資なども受けられなくなるでしょう。
また「パナマ文書」「タックスヘイブン」などで知られる租税回避は法律の条文に形式的には違反していないものの、制度の抜け穴を利用して本来想定されていない方法で税負担を減らす「脱法的行為」を意味します。タックスヘイブン(租税回避地)を利用した事例が知られており、違法でなくても、納税の義務を果たしていないということで社会的批判を受けますし、社会的信用の低下など副作用が大きいです。
したがって法人が目指すべきは、合法かつ健全な「節税」です。節税によって自由に使える資金を合法的に増やし、設備投資や経営改善に充てるのが目標になります。
決算前に行動することで節税効果を最大化できる
節税対策は決算を迎えてから考えるのでは遅く、決算前に具体的な行動を取ることでその効果を最大化できます。なぜなら、税法上の多くの制度や優遇措置は「決算期末までに実行していること」が条件とされているためです。
たとえば、備品や機械設備の購入を決算前に行えば、即時償却や特別償却といった優遇を受けられる場合があります。また、役員報酬の見直しや福利厚生費の計上といった方法も、決算期末前に適切に計画して実施することで税務上の効果が得られます。
さらに、在庫の棚卸しや経費計上の確認を早めに行うことで、申告漏れや過剰申告を防ぐことも可能です。こうした準備を前もって進めておけば、節税だけでなくキャッシュフローの見直しにもつながります。決算前の行動によって節税効果を最大化できるかどうかが決まります。
中小企業や高収益法人こそ積極的に活用すべき
節税対策はすべての法人にとって重要ですが、とりわけ中小企業や高収益法人こそ積極的に取り組むべきものです。中小企業の場合、資金繰りの安定は事業継続の大きな鍵を握ります。節税によって税負担を軽減できれば、浮いた資金を運転資金や新規設備投資、人材育成などに回せて、経営基盤を強化する効果が期待できます。
また、高収益法人にとっても節税は重要な経営戦略です。利益が大きい分、税金の負担も重くなりがちですが、制度を正しく利用することでキャッシュフローを改善し、さらなる事業拡大や株主還元に資金を充てられます。1%の節税が何百万円、何千万円の自己資本を生み出します。
中小企業も高収益法人も、合法的な節税を通じて自由に使える手元資金を有効活用することが、経営改善、持続的な成長、法人の競争力強化に直結します。
利益を圧縮し税金を減らす守備的な法人節税対策5選
法人が節税する方法には、大きく分けて「攻めの節税」と「守りの節税」があります。その中で守備的な(守りの)節税対策とは、積極的に利益を追求し所得を増やすのではなく、経常利益を圧縮することで課税所得を抑え、支払う税金を減らす方法を指します。
これは違法な脱税や制度の隙を突く脱法的な租税回避ではなく、法律で認められた経費の積極的な計上や適切な会計処理を行うことで、正当に税負担を軽減する取り組みです。
ここでは、そうした経費計上などを中心に、守備的な節税対策を5つ紹介します。これらを実践することで、法人にとって資金繰りを安定させ、将来の投資や経営基盤の強化に備えられる余力を得る原資になります。
- 不良在庫や不要な固定資産を処分して損失計上する
- 赤字や欠損金を繰り越して将来の利益を相殺する
- 貸倒引当金や貸倒損失を計上して利益を減らす
- 経営セーフティ共済の掛金を全額損金算入して資金を守る
- 含み損のある株式や金融資産を売却して節税効果を得る
それぞれ順に解説します。
不良在庫や不要な固定資産を処分して損失計上する
法人税の負担を抑える方法の一つに、不良在庫や不要となった固定資産を適切に処分し、損失として計上する手法があります。事業活動を続けていると、販売が難しい商品や売れない在庫、または使用していない設備や備品などが自然と増えます。
これらを帳簿上そのまま残しておくと資産として計上され続け、見かけ上の利益を圧縮できず、結果的に税金が増える要因になりかねません。実質負債なのに資産として計上するので、利益が増えて黒字になる=法人税が増えます。
そこで、資産価値が低下した在庫、不良在庫を廃棄処分したり、市場価値がなくなった固定資産を売却または除却することで、損失として計上することが可能になります。こうした対応は、資産の実態を正しく反映する(貸借対照表の信頼性も上がります)と同時に、過度な法人税負担を軽減できる効果が期待できます。
ただし、処分の際には証拠資料を残すことが重要であり、廃棄証明や売却契約書などの書類をしっかり整備することで、税務調査においても正当性を立証できます。正当な手続きで処分したことの証明も重要です。結果的に、財務の健全化と法人税対策の両面に寄与する有効な手段になります。
赤字や欠損金を繰り越して将来の利益を相殺する
赤字や欠損金の繰越控除を活用することは非常に効果的です。企業活動、事業活動を行っていると、事業環境の変化や一時的な設備投資により赤字が発生することがあります。しかし、その損失は無駄になるわけではなく、税法上、一定期間にわたり将来の黒字と相殺することが認められています。
具体的には、法人税法の規定に基づき、発生した欠損金を翌期以降に繰り越して、利益から控除することが可能です。これにより、黒字が出た年度でも過去の赤字と差し引くことで課税所得を減少させ、法人税の負担を軽減できます。まさに「攻めの節税対策」です。さらに、近年の制度改正により、中小企業の場合は欠損金の控除限度額が比較的広く認められているため、安定した節税効果を得やすい点も魅力です。
ただし、控除を受けるためには確定申告で適切に手続きを行う必要があり、期限を過ぎると繰越控除ができなくなるため注意が必要です。顧問税理士と入念な打ち合わせをお願いします。赤字を戦略的に活用することは、長期的な資金繰り改善にもつながる重要な法人節税対策となります。
貸倒引当金や貸倒損失を計上して利益を減らす
貸倒引当金や貸倒損失の計上も法人節税対策としてあります。取引先への売掛金や貸付金が回収不能となるリスクは、どの企業にも存在します。こうした将来の不確実性に備えるため、会計上では一定の基準に基づき貸倒引当金を計上することが認められています。これにより、想定される損失分を費用として処理でき、当期の課税所得を圧縮する効果が期待できます。
また、実際に取引先が倒産するなどして回収不能となった場合には、貸倒損失として損金算入が可能です。これにより、未回収リスクを反映させながら法人税の負担を軽減できます。ただし、貸倒損失を計上する際には、取引先の破産手続きの開始通知や内容証明郵便による督促記録など、税務上認められる証拠資料を準備する必要があります(勝手に貸し倒れにしない)。適正な手続きを行うことで、税務調査においても正当性が担保され、チェックされるリスクも減ります。
経営セーフティ共済の掛金を全額損金算入して資金を守る
法人税対策として広く利用されている制度の一つが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」です。この制度では、毎月の掛金を支払うことで、取引先が万一倒産した場合に備えるとともに、その掛金を全額損金(経費)として算入することが可能です。最大で月20万円、年間240万円、通算で800万円まで積み立てられ、積立額がそのまま経費扱いとなるため、課税所得を大きく圧縮できます。売掛先が倒産した場合は掛金(最大800万円)の10倍まで(つまり8000万円まで)緊急融資を受けられます。
さらに、共済金は解約すれば原則返戻される仕組みのため、資金を社外に流出させずに手元に置ける点が大きなメリットです。解約返戻金は利益として課税対象になりますが、解約のタイミングを選ぶことで、利益が少ない年度に計上するなど、税負担をコントロールすることが可能です。小規模企業共済とはこの点が異なるので注意ください(小規模企業共済の解約金はより控除が大きい退職所得か年金)。
掛金を損金算入しながら将来の備えも同時に確保できるため、資金繰りの安定化と節税を両立できる有効な法人税対策です。
含み損のある株式や金融資産を売却して節税効果を得る
含み損を抱えた株式や金融資産を適切なタイミングで売却する方法があります。保有している有価証券の価値が購入時より下落している場合、そのまま保有し続けると帳簿上は損失が顕在化せず、課税所得の圧縮にはつながりません。しかし、売却を行うことで損失を実現させ、損金として計上することが可能になります。
これにより、当期の利益と相殺し、法人税の負担を軽減する効果が得られます。特に決算期に近い時期には、含み損のある資産を整理することで、節税と財務内容の健全化を同時に進められる点が魅力です。
ただし、売却後に再度購入するなど不自然な取引を行うと、税務上否認されるリスクもあるため注意が必要です。税務調査で指摘されやすい項目であり、注意してください。また、短期的な節税効果だけでなく、資産運用方針や資金繰り全体を踏まえて判断することが大切です。適切に含み損を活用すれば、法人税額を抑えつつ資産の整理も進められる実務的な手段となります。
将来の事業成長につながる投資型の法人節税対策5選
前項が「守りの法人節税対策」だとすると、こちらで紹介するのは「攻めの法人節税対策」です。課税所得を減らして法人節税するのは同じですが、積極的に法人の成長に関わる支出を増やして、将来への投資を経費として計上します。
良く言われる散財とも言える有名企業の「税金対策」(大きなイベントを行うなど)、疲労い意味では攻めの法人節税対策とも言えるでしょう。そのような攻めの節税対策ができれば、より自社の事業を拡大していけます。
- 30万円未満の減価償却資産は即時償却して全額損金化する
- 設備投資や中古資産購入で減価償却費を効果的に計上する
- 社員旅行や健康診断など福利厚生制度を充実させる
- 決算賞与や給与増額による税制優遇を積極的に活用する
- 自社ホームページ制作など経費計上可能な広報投資を行う
それぞれ順に解説します。
30万円未満の減価償却資産は即時償却して全額損金化する
通常10万円以上の什器備品などは資産として減価償却しなければいけません、20万円のパソコンを買った場合、原則はその年に20万円を経費(損金)にできず、4年にわたって毎年5万円ずつ減価償却費として経費に計上します。
しかし、特例があり、それが「少額減価償却資産の特例」と呼ばれるものです。30万円未満の少額減価償却資産を即時償却し、当期の費用として全額損金に算入する方法になります。通常、パソコンや事務機器、備品などの固定資産は耐用年数に応じて分割して減価償却を行いますが、中小企業等については特例が認められており、取得価額が30万円未満であれば一括で経費処理することが可能です。
これにより、本来は数年間にわたって分散されるはずの費用を一度に計上できるため、課税所得を圧縮し法人税の負担軽減につながります。上記の例では20万円のパソコンは5万円ずつ4年ではなく、その年に20万円経費にできます。年間で即時償却できる上限は300万円までと定められていますが、この枠を有効に活用すれば、設備投資を行いつつ節税効果を享受できます。ただし、制度を利用するには中小企業者等(※)であることが条件であり、青色申告書を提出していることも要件となります。正しく制度を活用すれば、資金繰りに余裕を持たせながら事業基盤を強化できる点で、実務的にも非常に有用な法人節税対策です。
※:従業員が500名以下の中小企業(や個人事業主)
設備投資や中古資産購入で減価償却費を効果的に計上する
法人節税の有効な方法として、設備投資や中古資産の購入によって減価償却費を計上する手法があります。減価償却は、資産の取得費用を耐用年数にわたって費用化する仕組みであり、毎期一定額を損金算入することで課税所得を圧縮できます。特に中古資産の場合は、新品に比べて耐用年数が短く設定されるため、短期間で多くの償却費を計上でき、早期に節税効果を得られるのが特徴です。
中古でも品質の良いものは多く、オークションサイトなどを使えばほぼ新品に近いものも中古資産で手に入ります(自治体の中古品オークションなどもおすすめです)。
また、中小企業向けには上記のように「即時償却」などの優遇措置、特例措置が用意されており、設備投資の時期や内容を工夫することで節税効果をさらに高められます。たとえば、生産効率を高める機械やIT機器を導入すれば、事業拡大に寄与するだけでなく、法人税負担を抑制することも可能です。ただし、資産を取得するだけでは現金流出が発生するため、資金繰りとのバランスを踏まえて判断する必要があります。適切な設備投資や中古資産の活用は、事業成長と節税を両立させる実践的な法人税対策です。
社員旅行や健康診断など福利厚生制度を充実させる
法人節税対策として効果的なのが、社員旅行や健康診断などの福利厚生制度を充実させる方法です。福利厚生費は、従業員全体を対象として公平に提供されるものであれば、原則として損金算入が認められます。たとえば、年1回の社員旅行の費用や、定期健康診断の実施費用は、従業員のモチベーション向上や定着率改善に直結するだけでなく、法人税の課税所得を減らす効果も得られます。最新は「社食」を福利厚生費で計上する会社も増え、上限の拡大も議論されています。
また、社内イベントや慶弔見舞金制度なども福利厚生費として処理できるケースが多く、節税と組織力強化を同時に実現できるのが魅力です。社内イベントの効果を見直す動きもありますが、昔のようなやり方ではなく時代に合ったやり方を探しましょう。
ただし、特定の役員や一部社員だけが享受するような制度は福利厚生費として認められず、役員給与や課税対象の給与と判断される可能性があるため注意が必要です。従業員全員を対象に公平性を保ちながら制度設計を行うことで、健全な節税対策として活用できます。福利厚生の充実は、節税のみならず企業のブランド力を高める投資になります。
※「社食補助」拡大を議論へ 非課税限度額40年超据え置き―税制改正|時事通信 2025年9月7日
決算賞与や給与増額による税制優遇を積極的に活用する
決算賞与や給与増額に伴う税制優遇を積極的に活用する方法があります。まず決算賞与については、決算期末までに支給額を従業員へ通知し、一定の期限内に実際に支給すれば損金算入が可能です。これにより、当期の利益を適切に圧縮しつつ、従業員のモチベーション向上にもつながります。
また、従業員の給与総額を前年より増やした企業に対しては「所得拡大促進税制」(賃上げ税制)と言う制度があり、条件を満たせば増加額の一部を法人税額から控除できます。特に中小企業では適用条件が優遇されているため、積極的な人件費の見直しが節税効果を高める要因となります。
さらに、これらの施策は単なる税負担軽減にとどまらず、人材確保や離職率を減らすといった長期的な経営基盤の強化にも直結します。ただし、要件を満たさない場合は損金不算入や控除対象外となるリスクもあるため、制度内容を正しく理解し計画的に実行することが重要です。社員への給与還元、モチベーションアップと節税を両立できる有効な手段です。
自社ホームページ制作など経費計上可能な広報投資を行う
自社ホームページの制作や運営をはじめとする広報活動への投資を経費計上する方法です。自社サイトの立ち上げやリニューアル、SEO対策や広告掲載費用などは、基本的に販売促進費や広告宣伝費として損金算入が可能です。これにより、将来的な集客力やブランド価値を高めながら、同時に課税所得を圧縮できる点が大きなメリットです。
また、パンフレットや販促用資料の作成、展示会への出展費用なども同様に広報関連費用として処理できます。これらの経費は、単なる節税策にとどまらず、売上拡大や新規顧客獲得に直結する投資であるため、事業成長と税負担軽減を両立できる点が魅力です。
「御社の商品やサービスを教えてください」と問い合わせが来たときに、「このサイトを見てください」よりも「資料を送ります」と言って紙媒体のパンフを送った方が効果的です。作り置きしておくことで、将来の集客にもつながります。
ただし、資産計上が必要なケースや、私的利用とみなされる支出(明らかにプライベートな冊子やサイト作成など)は経費として認められない場合があるため注意が必要です。計画的に広報分野への投資を行い、経費処理を適切に行うことで、法人節税と企業価値向上の双方に貢献できるでしょう。
制度や規定の最適化による継続的な法人節税対策5選
法人節税対策にはこれ以外にも方法があります。法人、会社をめぐる各種制度を熟知し、その規定に沿って社内のシステムを変えることで、節税を実現できます。今までなんとなく行っていたものを、しっかり法制度に沿って整備していくことが、結果的に法人節税対策になり、かつ社内のコンプライアンスも達成できます。
ぜひ制度や規定を変えられるところは動いてください。資金調達しなくてもできることなので、元手がかからず社長の意思表明だけでできるものになります。まずこちらから行うと言う選択肢も十分にあり得ます。
- 役員報酬を最適額に設定して所得分散による節税を実現する
- 役員や従業員の住宅を社宅扱いにして経費化する
- 出張旅費や交通費の支給規程を整備して日当を損金算入する
- 短期前払費用の特例を利用して家賃や保険料を前倒し計上する
- 中小企業退職金共済や法人保険を活用して将来資金を準備する
それぞれ順に解説します。
役員報酬を最適額に設定して所得分散による節税を実現する
法人節税対策として、役員報酬を最適額に設定することで、所得分散による節税効果を得る方法があります。法人の利益が大きくなると、法人税負担が増える一方で、役員報酬を適切に設定することで利益を損金として計上でき、課税所得を圧縮できます。役員報酬は原則として各期同額であることが求められますが、事前に定めた範囲内で増減を調整することで、法人と役員の所得のバランスを最適化できます。
たとえば、法人の利益が大きい年度には報酬を引き上げ、利益が少ない年度には抑えることで、法人税と個人所得税の両面で節税が可能です。また、役員報酬の分散は、家族や親族を役員に登用することで所得を分散させ、総合的な税負担を軽減する戦略とも組み合わせられます。もちろん仕事の実態がない家族を役員にして役員報酬を支給するのはNGです。何らかの内容を伴う仕事をしてもらうことは必須なのでご注意ください。こちらは税理士と良く相談してください。脱税の手法でも用いられるので税務署のチェックは厳しくなります。
税務上の過大・過少報酬は否認されるリスクがあるため、経営実態に即した合理的な額を設定することが重要です。適切な役員報酬の設定は、法人税負担の軽減と資金効率の向上を両立させられます。
役員や従業員の住宅を社宅扱いにして経費化する
役員や従業員の住宅を社宅として扱い、経費化する方法があります。社宅制度を活用すると、企業が賃貸料や住宅取得費用の一部を負担した場合、その支出を福利厚生費として損金算入できます。これにより、法人の課税所得を圧縮し、法人税負担を軽減する効果が期待できます。
従業員や役員にとっても、住宅費(家賃)の負担が軽減されるため、生活の安定やモチベーション向上にもつながります。税務上は、社宅の利用者ごとに「家賃相当額」と「負担額」を明確に区分することが求められ、適正な処理を行うことが重要です。また、社宅費用の一部を役員や従業員の給与として課税する場合もあるため、給与課税とのバランスも考慮する必要があります。適法に社宅制度を活用することで、法人税の節税と人材支援を同時に実現できる実務的な手段です。
言うまでもなく居住実体のある住宅が社宅になります。「セカンドハウス」的なものではないのでご注意ください。
出張旅費や交通費の支給規程を整備して日当を損金算入する
出張旅費や交通費の支給規程を整備し、日当を損金算入する方法があります。法人が役員や従業員に出張を命じた場合、交通費・宿泊費・日当などを支給することが一般的ですが、これらを適正に規程化しておくことで、支給額を経費として法人税の計算上損金に算入できます。
特に日当は、出張中の食事代や雑費などの実費精算が難しい場合でも、あらかじめ規程に基づき支給することで、税務上も認められるケースが多く、課税所得を有効に減らせます。規程には支給対象、金額の上限、精算方法などを明確に記載することが重要で、これにより税務調査時にも正当性を証明できます。会社の経費で多大な飲食費を出すわけではないことを証明します。
また、規程化しイントラネットなどに公開することで社員間の公平性も確保され、業務運営上のトラブル防止にもつながります。適切な出張旅費規程の整備は、法人税負担の軽減と経費管理の透明化を同時に実現できる実務的な節税対策です。
短期前払費用の特例を利用して家賃や保険料を前倒し計上する
法人節税対策の一つとして、短期前払費用の特例を活用し、家賃や保険料を前倒しで経費計上する方法があります。通常、前払費用は発生した期間に対応して費用化しますが、短期前払費用の特例では、支払日から1年以内に費用化される支出であれば、支払い時点で一括して損金算入が可能です。
たとえば、翌年度分の事務所賃料や損害保険料を決算前に支払うことで、当期の経費として計上でき、課税所得を圧縮できます。この方法は、現金の流出がある一方で法人税の負担を減らせるため、資金繰りに余裕がある年度に特に有効です。
ただし、特例の適用には支払日や契約内容、費用の性質など一定の条件を満たす必要があり、むやみに認められるわけではなく税務上の正確な処理が求められます。短期前払費用の特例を適切に活用することで、将来の支出を前倒し計上しながら、法人税の軽減を実現できる実務的な節税手段となり得ます。
中小企業退職金共済や法人保険を活用して将来資金を準備する
中小企業退職金共済(中退共)や法人保険を活用して将来の資金を計画的に準備する方法があります。中退共は、役員や従業員の退職金制度として利用でき、掛金を全額損金算入できるため、法人税の課税所得を圧縮しながら退職金の原資を積み立てられます。これにより、退職時に大きな支出が発生しても資金不足に陥るリスクを軽減できます。
一方、法人保険では、生命保険や損害保険の保険料を活用して損金算入や資産形成を行うことが可能です。特に経営者の死亡保障や退職金準備を目的とした定期保険や養老保険は、将来の出費を見越した計画的な資金確保と節税の両立ができます。ただし、保険商品によって損金算入の扱いや解約返戻金の課税関係が異なるため、制度や商品内容を正しく理解し、計画的に契約することが重要です。中退共や法人保険を適切に活用することで、税負担を抑えながら将来の資金準備を効率的に進められる実務的な法人節税策です。
また、小規模企業共済や中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)についても、所得控除や損金算入が可能です。ただし、増額は比較的容易ですが、減額手続きが少々難しいので、中小企業退職金共済や法人保険を優先していただいて構いません。
決算時に必ず確認すべき法人節税の最終チェック項目
法人の決算が近づくと、利益の圧縮や税負担の軽減を目的とした節税対策が重要になります。しかし、何から手を付けるべきか迷う経営者も少なくありません。ここでは、決算時に必ず確認しておきたい法人節税の最終チェック項目をご紹介します。
具体的には、損金算入できる経費の漏れチェックや売上計上の適切なタイミング、中小企業の各種特例の活用など、合法的かつ効率的に節税効果を最大化するポイントです。これらを確認することで、納税額を抑えつつ、キャッシュフローの健全化にもつながります。経営の安定を守るための申告前の最終チェックリストとしても役立つ内容です。
- 未払費用や未払金を漏れなく計上して課税所得を圧縮する
- 売上計上のタイミングを調整して適正な利益を確保する
- 資本金や決算期の見直しで中小企業特例を最大限利用する
- 必要に応じて分社化や関連会社設立で節税メリットを享受する
それぞれ順に解説します。
未払費用や未払金を漏れなく計上して課税所得を圧縮する
決算時の法人税対策として有効なのが、未払費用や未払金を漏れなく計上することです。未払費用とは、決算日までにサービスの提供を受けているにもかかわらず、まだ支払っていない費用を指します。たとえば、地代家賃や水道光熱費、支払利息などが代表的です。
一方、未払金は、備品の購入代金や外注費など、すでに債務が確定しているにもかかわらず未払いの金額を表します。これらを正しく計上することで、その期の損金に算入でき、結果として課税所得を圧縮する効果が期待できます。
実務上、計上漏れがあると本来認められる損金が反映されず、余計に税負担が増えてしまう恐れがあります。したがって、決算にあたっては請求書や契約書を再確認し、発生しているが未払いの各種費用や買掛金などを洗い出すことが重要です。正確な未払計上を徹底することで、合法的で効果的な法人節税が可能となります。
売上計上のタイミングを調整して適正な利益を確保する
法人の節税対策において、売上計上のタイミングを見直すことは、利益の適正な調整に直結します。具体的には、当期に受け取った収益に次期以降の分が含まれている場合、その次期以降に属する部分を当期の収益から除き、次期以降の収益とする会計処理が例外的に可能です。これを「前受収益」と呼び、サービスの提供が完了していないにもかかわらず、代金を事前に受け取った場合に該当し、適切な期間に対応する収益のみを当期の売上として計上するために行われます。
売上の大原則は「発生主義」ですが、条件を満たすと例外的に売上計上のタイミングを調整できることがあるのです。
もちろん、過度な繰延や意図的な売上操作は、税務上問題となる場合があるため、あくまで会計基準や税法に沿った適正な処理が前提です。また、売上計上のタイミングを調整する際には、資金繰りへの影響も考慮する必要があります。ファクタリングによる資金調達ができなくなる可能性もあります。
このテクニックを適切に実施すれば、無理のない利益確保と税負担の平準化を両立でき、経営判断の安定にもつながります。結果として、決算期ごとの業績を正確に把握しつつ、計画的な節税対策を講じることが可能となります。
資本金や決算期の見直しで中小企業特例を最大限利用する
中小企業にとって、資本金の額や決算期の設定を見直すことは、税制上の特例や優遇措置を最大限に活用するための重要なポイントです。たとえば、資本金1億円未満の中小企業であれば、法人税の軽減税率や交際費の損金算入枠の拡大など、さまざまな優遇制度が適用されます。資本金が300万円の小規模事業者であればさらに適用される特例も多くなるかもしれません。
そのため、資本金を適正に設定することで節税効果を高められます。また、決算期を工夫することで、売上や利益の増減を期末に合わせ、課税所得の平準化や納税負担の分散が可能です。
ただし、資本金の変更や決算期の変更には手続きや会計上の調整が必要であり、安易な変更は税務上のトラブルにつながるリスクもあります。資本金は会社の「血液」、重要な自己資本であり、節税のために減資するのは本末転倒と言う見方もあることは知っておいてください。
必要に応じて分社化や関連会社設立で節税メリットを享受する
法人節税の手法の一つとして、分社化や関連会社の設立があります。事業を複数の法人に分けることで、各社ごとに中小企業向けの軽減税率や各種特例を適用でき、全体としての税負担を抑えることが可能です。また、関連会社間での取引を適正に設計すれば、利益の分散や損益通算(グループ通算制度)による節税効果も期待できます。
さらに、リスク管理の観点からも、事業ごとに法人を分けることで、万が一の損失や債務が他事業に影響するのを防ぐ効果があります。ただし、分社化や関連会社設立には設立費用や運営コスト、税務上の適正な取引管理が必要であり、安易な運用は税務調査のリスクを高める可能性があります。会社が増えれば、それだけ税務調査に当たる可能性も高くなり、その際にはグループ会社についてもチェックが入る可能性があります。
制度を正しく理解し、将来の経営戦略やキャッシュフローも見据えた上で計画的に実施することが、節税メリットを最大化するポイントです。
法人節税対策を行う際に必ず押さえるべき注意点
法人節税対策は「とにかくやれば良い」と言うものではなく、実際に着手する前に必ず押さえておいていただきたいポイントがあります。注意点でもあり、ここを無視して法人節税対策をしてもうまくいかない、経営にとってかえってマイナスになってしまう可能性もあります。
- 節税効果の短期的メリットと将来の税負担増加リスクを理解する
- 証拠資料や領収書を保存して税務調査で否認されないようにする
- 無理な節税による資金繰り悪化や事業成長停滞を避ける
ぜひ以下の注意点については押さえていただき、法人節税を成功させてください。
節税効果の短期的メリットと将来の税負担増加リスクを理解する
法人が節税対策を行う際には、目先の税負担を軽減できると言う短期的な利点に目を奪われがちですが、その一方で将来的に税金が増える可能性があることを理解しておく必要があります。たとえば、短期前払費用の特例や減価償却の加速などは、当期の利益を圧縮し納税額を下げる効果がありますが、翌期以降に計上できる費用が減るため、将来の利益が押し上げられ、かえって課税額が増えるリスクを伴います。
また、生命保険や共済制度を利用する節税策も、解約時や将来の受取時に課税されるケースが多く、実質的には課税の先送りに過ぎない場合も少なくありません。中小企業倒産防止共済については解約時の返戻金は、退職金ではなく益金(売上)になります。
したがって、法人節税は「永続的な節税」ではなく、「一時的な税負担の調整」であることを意識することが大切です。今年節税できても、その分来年は増税になるかもしれません。短期的なメリットだけでなく、中長期の資金繰りや経営計画を見据えることも大切です。
証拠資料や領収書を保存して税務調査で否認されないようにする
法人節税を実施する際には、実際に支出や取引が行われたことを客観的に示せる証拠を適切に保管しておくことが不可欠です。どれほど正しい節税策を講じていても(講じたと思っていても)、裏付けとなる領収書や契約書、議事録などが不足していれば、税務調査で経費算入を否認され、追徴課税や重加算税が課されるリスクがあります。
特に交際費や出張旅費、役員報酬の増額、保険料の支払いなどは「実態が伴っているか」が厳しく確認されやすい分野です。たとえば会食であれば、領収書に加えて参加者や目的をメモしておくと信頼性が高まります。税務調査でも十分説明できます。私的支出を法人経費にしがちな分野は税務署チェックが厳しいのは言うまでもありません。
また、電子帳簿保存法の要件を満たせば、データ形式で保存することも可能ですが、その場合も改ざん防止措置(タイムスタンプ)や検索機能の確保など法令に沿った管理が求められます。節税効果を確実なものとするためには、日常の取引を正しく記録・保存し、後からでも詳しく説明できる状態にしておくことが重要です。
無理な節税による資金繰り悪化や事業成長停滞を避ける
節税効果ばかりに注目して無理な対策を講じると、かえって資金繰りを悪化させたり、事業の成長を妨げたりする危険があります。たとえば、必要以上に多額の保険料を支払ったり、将来使う予定のない資産を購入したりすると、一時的に経費が増えて税金は抑えられるものの、手元資金(自己資本)が減少し、運転資金の不足を招くことがあります。
また、研究開発、人材採用といった本来成長につながる支出が後回しになれば、企業競争力の低下につながりかねません。節税はあくまで経営戦略の一部であり、最優先すべきは安定した資金繰りと事業拡大、利益増です。そのため、実行前に将来のキャッシュフローに与える影響を十分に検討することが重要です。無理のない範囲で節税策を取り入れることで、健全な財務体質を維持しながら長期的な成長を実現できます。
最新税制を活かした法人の節税と投資戦略
法人が持続的に成長していくためには、単に目先の税負担を軽減するだけでなく、最新の税制、税特例をうまく取り入れながら投資戦略と結び付けることが求められます。
近年は、設備投資や研究開発費、人材育成に対する税制優遇措置が拡充されており、これらを活用すれば税負担を抑えつつ事業基盤を強化することが可能です。たとえば、経営強化税制を利用すれば、資金繰りに余裕を持ちながら競争力強化につながる投資を進められます。物価高対策もあり、各種税制度について最新の情報をキャッチすることも経営者として必要です。
節税と事業成長を両立させるためには、最新制度の動向を把握し、経営計画に適切に組み込む視点が欠かせません。
- 法人税が800万円まで15%に軽減される仕組みは2027年まで継続
- 設備投資には経営強化税制による即時償却や税額控除が活用可能
- 企業版ふるさと納税による地方創生支援で税額控除が引き続き使える
- 地域経済を支える事業には地域未来投資促進税制の優遇が効果的
それぞれ順に解説します。
法人税が800万円まで15%に軽減される仕組みは2027年まで継続
中小法人に適用される法人税の軽減税率は、所得800万円までの部分を15%に抑える特例として2027年3月31日まで延長されています。この仕組みは資本金1億円以下の中小法人(中小企業)にとって大きな節税効果をもたらし、手元資金を厚くすることで投資や成長施策に充てやすくなる点が魅力です。
ただし、すべての法人が無条件に恩恵を受けられるわけではなく、グループ通算制度を利用する法人や所得規模の大きい企業は適用対象外となる場合があるため、税理士などへの事前確認が欠かせません。資格がないのに勝手に特例を利用すると、申告漏れ、脱税となってしまいます。
単年所得が10億円を超える法人については軽減税率が(15%から)17%に引き上げられるなど、一定の制限も設けられています。したがって、この制度を活用する際には単なる税負担の軽減だけを目的にせず、将来の資金繰りやキャッシュフロー改善、経営戦略に合わせて効果的に利用することが重要です。節税で確保した資金を設備投資や研究開発、人材育成などに再投資することで、税制の恩恵を持続的な成長へとつなげられます。
設備投資には経営強化税制による即時償却や税額控除が活用可能
法人が設備投資を行う際には、経営強化税制を活用することで大きな節税効果を得ることが可能です。この制度は、生産性向上や収益力強化につながる設備を導入した場合に、取得価額の全額を即時に償却できる「即時償却」や、一定割合を法人税から直接差し引ける「税額控除」のいずれかを選択できる仕組みとなっています。
経営強化税制の対象となる設備は以下です(中古品は対象外、新品に限る)。
- 機械・装置:1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
- 工具・器具・備品:1台または1基の取得価額が30万円以上のもの
- 建物附属設備:一の取得価額が60万円以上のもの
- ソフトウェア:一の取得価額が70万円以上のもの
通常の減価償却では数年に分けて費用化するため、その間は利益が増え、結果的に納税額も増加しますが(課税所得=売上-経費が少なくなる)、即時償却を選べば初年度に一括で経費計上でき、当期の税負担を大幅に軽減できます。一方で税額控除を活用すれば、費用計上とは別に法人税額そのものを減らせ、自己資金を増やしキャッシュフロー改善に直結します。
いずれの方法も適用には経営力向上計画の認定や対象設備の諸要件を満たす必要があるため、税理士相談や商工会議所の経営相談などを行いながら進めてください。節税効果と投資効果を両立させる手段として、経営強化税制は成長戦略と密接に結び付けて活用すべき制度です。
企業版ふるさと納税による地方創生支援で税額控除が引き続き使える
企業版ふるさと納税は、法人が地方公共団体の行う地方創生プロジェクトに寄附をすることで、通常の損金算入に加えて大幅な税額控除を受けられる制度です。制度開始当初は寄附額の3割程度が実質的な負担となっていましたが、見直しにより最大で寄附額の約9割が税制優遇の対象となり、企業にとっては実質的な負担を抑えつつ地域貢献を実現できる仕組みに進化しています。
この優遇措置は引き続き利用可能であり、法人税や法人住民税、法人事業税から控除されるため、キャッシュアウトを伴う寄附でありながら実質的なコストは小さく、会社のイメージアップに寄与します。また、寄附先の自治体によっては企業名の公表や地域との連携プロジェクトへの参加機会が用意されることもあり、社会的評価や新たなビジネス展開にもつながる可能性があります。
個人が行うふるさと納税のように「返礼品」として何かもらえるわけではありませんが、単なる節税策にとどまらず、企業ブランドの向上や持続可能な経営戦略の一部として位置付けることで、企業版ふるさと納税は節税の恩恵と地域貢献を両立できる制度です。
地域経済を支える事業には地域未来投資促進税制の優遇が効果的
地域経済を支える事業を推進する企業にとって、地域未来投資促進税制の優遇措置も法人節税に有効な手段となります。この制度は、生産性の向上や成長分野への投資を後押しするために設けられたもので、「地域経済牽引事業を実施するために必要とされる資産」となる機械・装置、器具・備品、建物・建物附属設備・構築物を導入する場合に、通常の減価償却に加え「即時償却」や「税額控除」の選択が可能となります。
特に、地域に根ざした製造業やサービス業が新しい設備やシステムを導入する際に活用すれば、初期投資の負担を軽減しつつ、収益力強化や雇用創出につなげられます。また、認定を受けた事業計画に基づく投資であれば、金融機関からの融資が受けやすくなるなど、資金調達面でもメリットがあります。
こうした仕組みを利用することで、企業は税負担を抑えながら競争力を高め、地域全体の活性化に貢献できます。単なる節税効果にとどまらず、持続的な成長と地方創生を両立させる戦略として、地域未来投資促進税制は積極的に考えられます。
今すぐ備えたい2026年以降の税制変更と会計対応
2026年以降、法人を取り巻く税制や会計基準には大きな見直しが予定されており、早めの対応が求められます。法人税の特例措置や中小企業向けの優遇制度の期限到来に加え、電子帳簿保存法への完全対応やインボイス制度の定着など、ここ数年で法人を関連の税制も大きく変わりました。
この「激動の時代」にあって、単なる事務負担増にとどまらず、新税制は資金繰りや税負担、さらには経営判断そのものに影響を及ぼす可能性があります。将来の税制改正を見据えて、自社の会計処理や内部統制を確固たるものにして、制度の変化を成長機会として活かすための準備を今から始められれば良いです。
- 2026年から始まる防衛特別法人税により法人税率に4%の上乗せ
- 再資源化設備への投資では取得額の35%を特別償却できる新制度
- 2027年導入予定の新リース会計ルールへの早めの対応が必要
- 海外取引のある法人には国際課税ルール見直しへの備えが必要
それぞれ順に解説します。
2026年から始まる防衛特別法人税により法人税率に4%の上乗せ
2026年4月1日から施行される「防衛特別法人税」は、企業の法人税額に対して4%の上乗せが課される新たな付加税です。
この税制は、防衛力強化のための財源確保を目的としており、法人税額から年500万円の基礎控除を差し引いた金額に4%を乗じて算出されます。たとえば、法人税額が1,000万円の企業の場合、基礎控除500万円を差し引いた500万円に4%を乗じて20万円の追加負担が発生します。
一方、法人税額が400万円の企業では、基礎控除の範囲内で課税標準が0となり、追加負担はありません。
このように、中小企業では基礎控除の適用により防衛特別法人税の負担が発生しないケースもありますが、大企業や高所得法人では実質的な税負担増となる可能性があります。
また、外国税額控除などの税額控除が適用される場合、防衛特別法人税にも適用されるため、適切な申告と計算が求められます。
この新たな税制に対応するため、企業は事前に影響を把握し、必要な申告手続きや会計処理の準備を進めることが重要です。
再資源化設備への投資では取得額の35%を特別償却できる新制度
環境負荷の低減や循環型経済の推進を目的として、再資源化設備への投資に対する優遇税制が新たに導入されました。この制度では、対象となる再資源化設備を取得した場合、取得価額の35%を特別償却として初年度に費用計上することが可能です。
通常の減価償却では数年に分けて経費化されるため、初年度の税負担はそれほど軽減されませんが、特別償却を利用すれば、投資直後から法人税額を抑えられ、キャッシュフローの改善にも直結します。また、対象設備は廃棄物の再資源化やリサイクル工程に使用される機械・装置などが含まれ、企業の環境対策やESG投資とも親和性が高いのが特徴です。
ただし、優遇適用には認定を受けた設備であることや、一定の条件を満たす必要があるため、事前に対象要件を確認した上で計画的に投資を進めることが重要です。これにより、環境配慮と税制メリットを同時に享受できる戦略的な設備投資が可能となります。
2027年導入予定の新リース会計ルールへの早めの対応が必要
2027年から導入が予定されている新しいリース会計ルールでは、従来オフバランス処理が可能だったリース取引も原則として貸借対照表に計上する必要が生じます。これにより、リース資産およびリース債務が資産・負債として認識されるため、企業の財務指標や自己資本比率、負債比率に直接影響を与えることになります。
特に長期リース契約を多く抱える企業や資産管理を重視する企業にとっては、資金調達や投資判断に関わる重要な変更となるため、早期の対応が不可欠です。具体的には、既存リース契約の内容整理や会計システムの改修などを事前に実施し、財務戦略や契約見直しを検討することが求められます。
また、税務上の取扱いとの整合性も確認しておくことで、導入初年度から適切な会計処理と報告が可能となります。2026年以降の税制変更と合わせて、リース会計対応やリース契約の見直しも計画的に進めることが企業の安定経営に直結します。
海外取引のある法人には国際課税ルール見直しへの備えが必要
2026年以降は、国際的な税制ルールの改正が日本企業にも直接影響を及ぼす見込みです。特にOECDの「BEPS2.0」プロジェクトに基づく最低税率制度(グローバル・ミニマム課税)の導入が本格化し、多国籍企業にとっては各国での税負担が均一化される方向に進みます。
海外子会社を持つ法人は、各国での実効税率の把握や二重課税回避のための制度利用など、グループ全体での税務会計戦略の再構築が欠かせません。また、移転価格税制に関する情報開示の厳格化や電子データ提出義務の拡大も想定され、会計部門には国際基準に対応できるシステム整備が求められます。
さらに、海外取引のある企業は、為替リスクや源泉徴収ルールの変動も視野に入れておく必要があります。今のうちから専門家と連携し、グループ内取引の価格設定、会計処理、税務申告体制を見直すことで、将来の追加課税やコンプライアンスリスクを軽減できるでしょう。
法人の節税対策で良くある質問に回答
法人の節税対策を考える際に、いくつか疑問点が出てきます。ここではその中でも良くある質問についてQ&A方式で回答します。法人の節税対策をする前に、ぜひ疑問点について潰しておきましょう。
決算前に利益が出すぎたときすぐできる節税対策は?
決算直前に想定以上の利益が出た場合、適切な節税策を講じることで法人税の負担を抑えられます。まず有効なのが「必要経費の前倒し計上」です。来期以降も確実に発生する地代家賃、保険料、広告宣伝費などを短期前払費用の特例を利用して支払えば、当期の損金に算入できます。
また、老朽化した設備や備品の入れ替えも即効性があります。固定資産を一定額まで一括償却できる制度を活用すれば、購入費用を当期の費用にできる可能性があります。さらに、中小企業退職金共済や企業型保険(法人保険)への加入も有効で、福利厚生を充実させながら損金算入が可能です。
役員賞与増額を利用する場合は事前届出が必要ですが、適切なタイミングで準備すれば効果的です。いずれにしても場当たり的ではなく、翌期以降の資金繰りや経営計画と整合性を持たせて実施することが重要で、税理士と相談しながら進めるのが安心です。安直な設備投資はかえって経営を縛ってしまう可能性もあります。
中小企業でも効果が高い節税対策の優先順位は何ですか?
中小企業が節税対策を行う際には、効果の高い順序を意識して優先的に取り組むことが重要です。まず基本となるのは、利益の圧縮による法人税軽減です。具体的には、経費計上の漏れを防ぎ、短期前払費用や修繕費、消耗品費などを適切に計上することで、課税所得を減らせます。
次に、中小企業向けの税制優遇制度を活用することです。経営強化税制による設備投資の特別償却や税額控除、研究開発税制などは、投資と節税を同時に実現でき、成長戦略と結び付けやすい点で効果が高いです。また、役員報酬の適正化や退職金制度、生命保険や中小企業退職金共済の活用も、将来資金準備と節税を両立させる手段として有効です。
最後に、出張旅費や交際費の損金算入ルールを整理することで、日常的な経費処理の効率化と節税の両立が可能です。中小企業では、無理のない範囲で利益圧縮と制度活用を組み合わせることが、最も効果的な節税戦略となります。
節税目的で法人を設立するのは本当に効果的ですか?
法人を節税目的だけで設立する場合、短期的には個人事業主よりも税率面で有利になることがありますが、必ずしも大きな効果が得られるとは限りません。法人税>所得税になってしまう所得ラインもあるため、法人成りをせず、個人事業主を続けた方が節税になるパターンも知ってください。
法人化に伴う法人税率や中小企業特例を利用すれば、所得が一定水準(約800万円)を超える場合に税負担を抑えられるケースがあります。しかし、法人設立には登記費用や社会保険料、会計・税務処理の負担増(法人の9割には顧問税理士がいる)、役員報酬や決算対応のコストなどが発生します。個人事業主よりも法人の方が税務調査に入られやすいと言う話もあります。
さらに、利益が多くないなら、個人事業主として青色申告控除や経費計上を最大限活用した方が負担が少ない場合もあります。そのため、法人化による節税効果は利益水準や事業規模、将来の成長計画を踏まえた上で判断する必要があります。自分1人の個人事業主やフリーランスの事業主様は、あえて法人化するメリットが薄いかもしれません。
節税だけを目的に法人を設立すると、結果としてコスト負担が増え、資金繰りや事業運営に悪影響を及ぼすリスクもあるため、節税と経営戦略の両面から慎重に検討することが重要です。法人の方が社会的信用度が高いので、事業をどんどん伸ばしたい場合は、(個人事業主より税金が高くなっても)早期の法人化も戦略としてはありです。
法人節税に使える商品や経費の裏ワザは存在する?
法人節税において「裏ワザ」と呼ばれる手法は存在しますが、税務上認められないものや脱税に該当するリスクが高いため、安易に追求するのは危険です。
合法的に節税効果を得られる手段としては、あらかじめ制度化されている中小企業関連の特例措置を活用する方法が基本です。たとえば、中小企業向けの経営強化税制や研究開発税制、設備投資に伴う特別償却や税額控除は、投資と節税を同時に実現できる合法的な手段です。
また、役員報酬や退職金制度、法人保険や中小企業退職金共済を活用すれば、将来資金の準備と法人税軽減を両立できます。さらに、出張旅費や交際費、消耗品費など日常経費の計上漏れを防ぐだけでも、課税所得の圧縮につながります。重要なのは、利益を圧縮する際に必ず証拠資料を残し、税務調査で否認されないよう正確な記録を整えることです。
裏ワザ的な節税を狙うより、制度の正しい理解と計画的な活用が、安全かつ効果的な法人節税の基本となります。「裏ワザ」なのか「ウソテク」「禁忌肢」なのかは税務署が決めることであり、主観的要素、属人的要素も入るので、リスクしかなくおすすめしません。
税金対策で買っておくと良いものは何かありますか?
法人が節税目的で購入を検討する場合、単に物を買えば良いわけではなく、事業に関連し、税務上経費や資産計上が認められるものを選ぶことが重要です。日用品や遊興費に充ててもそれは経費にも損金にもなりません。
まず、事務用品や消耗品、パソコンやオフィス機器など、通常業務で使用する備品や設備は、購入時に経費計上できるため利益圧縮に直結します。次に、将来の生産性向上や業務効率化に資する設備投資は、経営強化税制や中小企業投資促進税制の特別償却や税額控除の対象となる場合があり、節税効果が高いです。
また、事業関連の保険料や研修費、広告宣伝費も、支出時期を調整することで決算前の課税所得を抑えられます。
一方で、個人的な消費や事業と無関係な物品の購入は経費と認められず、脱税に該当するリスクがあるため注意が必要です。社用車を買い替える場合も、プライベートで使っているとNGになる可能性があります。
要は、税法上認められる範囲で「将来の業務や成長につながるもの」を合法的に購入することで、節税と事業強化、経営改善を同時に実現できることです。

