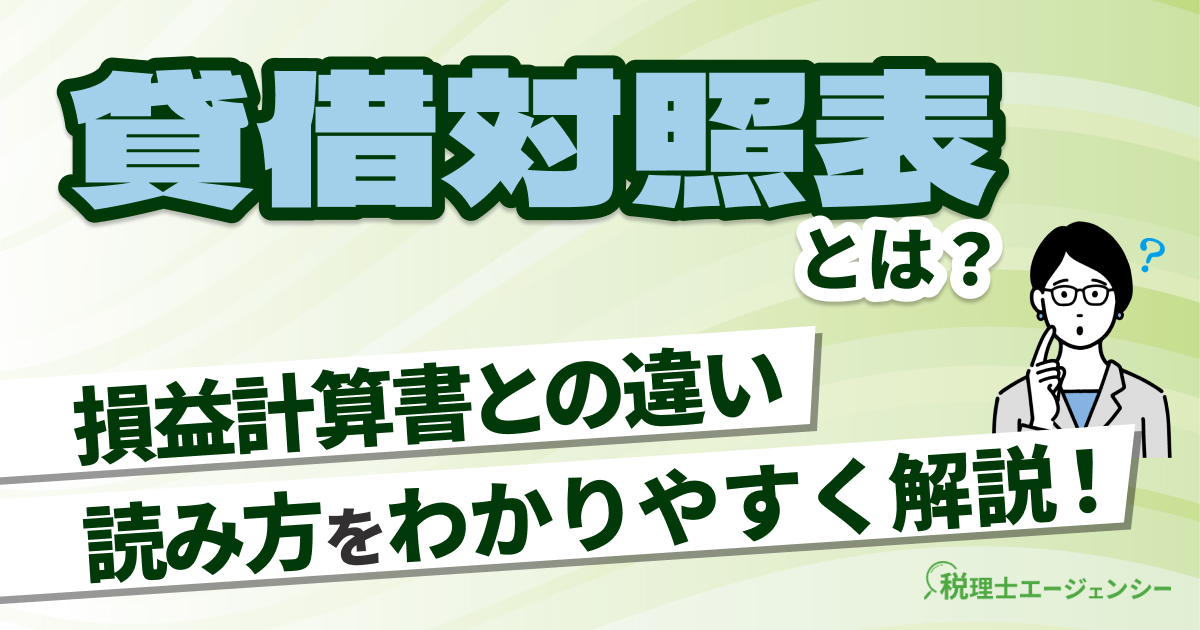会社の経営状態を把握するとき、決算書という言葉を耳にする方は多いでしょう。しかし、その中身である貸借対照表や損益計算書について、実際に理解している方は意外と少ないかもしれません。貸借対照表は企業がどれだけの財産を持ち、どれだけの借金を抱えているのかを一目で把握できる重要な財務諸表です。経営者はもちろん、従業員や取引先、金融機関にとっても、会社の健全性を判断する材料として欠かせません。
この書類を読み解けるようになれば、数字の向こうに見える会社の実態や、経営の安定性、将来性までもが見えてきます。本記事では、貸借対照表の基本的な仕組みから読み方、作成方法、分析のポイントまでを、初めて触れる方にもわかりやすく解説していきます。
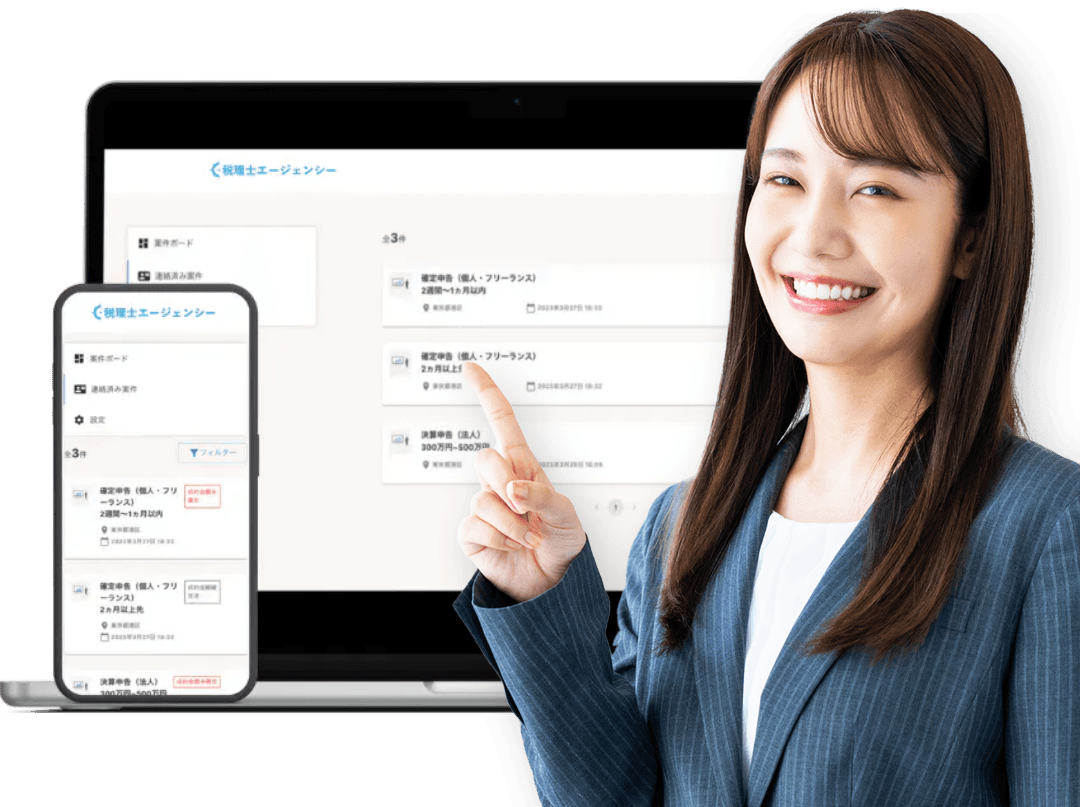
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
貸借対照表とは企業の財政状態を示す決算書
貸借対照表は、ある時点における会社の財政状態をまとめた決算書です。英語ではバランスシートと呼ばれ、略してB/Sと表記されます。決算日時点で会社がどのような財産を持ち、どこから資金を調達したのかを示す書類であり、損益計算書やキャッシュフロー計算書と並んで、財務三表と呼ばれる重要な財務諸表のひとつです。
会社法では、株式会社に対して貸借対照表の作成を義務付けており、公開会社や大会社には開示義務も課されます。また、金融商品取引法では、上場企業など特定の株式会社に対して貸借対照表を含む財務諸表の開示を義務付けています。税務申告の際にも提出が求められます。この書類を通じて、経営者は自社の資金状況を正確に把握でき、投資家や債権者は会社の安全性を判断する材料を得られます。貸借対照表は単なる数字の羅列ではなく、会社の財務的な健康診断書ともいえる存在であり、定期的に確認することで経営の舵取りに役立てられます。
- 貸借対照表は資産・負債・純資産の3要素で構成
- 貸借対照表と損益計算書・キャッシュフロー計算書の違い
それぞれ順に解説します。
貸借対照表は資産・負債・純資産の3要素で構成
貸借対照表は、左側と右側に分かれた独特の形式で表現されます。左側には資産の部が配置され、会社が保有するすべての財産が記載されます。一方、右側には負債の部と純資産の部が配置され、その財産をどのように調達したのかが示されます。
資産とは、現金や預金、商品、建物、機械といった会社が事業活動に使える財産すべてを指します。負債は、銀行からの借入金や買掛金など、将来返済しなければならない義務を表します。そして純資産は、資本金や利益剰余金など、返済義務のない会社自身の正味の財産です。
貸借対照表では、複式簿記の原則に基づき、「資産=負債+純資産」という等式が常に成り立つよう設計されています。この等式が崩れている場合、記帳ミスや漏れがあることを示します。左右の合計金額が必ず一致することから、バランスシートという名前がついているのです。この基本構造を理解することが、貸借対照表を読み解く第一歩となります。
貸借対照表と損益計算書・キャッシュフロー計算書の違い
財務三表はそれぞれ異なる視点から会社の状態を表します。貸借対照表が決算日時点の財政状態という静的なスナップショットを示すのに対し、損益計算書は一定期間における経営成績を動的に示す書類です。損益計算書では、売上高から費用を差し引いて最終的な利益を計算し、会社がどれだけ稼いだのかを明らかにします。
一方、キャッシュフロー計算書は、実際の現金の出入りを営業活動、投資活動、財務活動の3つに分けて記録します。利益が出ていても現金が不足していれば資金繰りに困るため、この書類で現金の動きを把握することが重要です。たとえば、売上が伸びていても回収が遅れれば現金が手元になく、支払いに困る事態が起こりえます。
貸借対照表と損益計算書は密接に関連しており、損益計算書で計算された当期純利益は、貸借対照表の純資産の部に利益剰余金として蓄積されていきます。つまり、貸借対照表は会社の財産の状況を、損益計算書はその財産がどう増減したかを、キャッシュフロー計算書は現金の実際の動きを、それぞれ補完的に教えてくれます。これら三つの書類を組み合わせて読むことで、会社の真の姿が立体的に浮かび上がってきます。
貸借対照表の見方を知れば会社のお金が理解できる
貸借対照表を読み解くことは、会社の財務体質を理解する第一歩です。数字の羅列に見える書類も、その構造と意味を知れば、会社がどれだけ健全な経営をしているか、資金繰りに余裕があるか、借金に依存しすぎていないかなど、多くの情報を読み取れます。
経営者であれば意思決定の根拠として、従業員であれば自社の経営状態を知る手がかりとして、取引先であれば信用判断の材料として活用できるでしょう。貸借対照表の見方を身につけることで、会社のお金の流れが見えるようになり、財務的な課題や改善点を発見できます。ここからは、資産、負債、純資産という3つの要素について、それぞれの意味と見方を詳しく説明していきます。
- 資産は会社が保有する現金や建物・設備などの財産を示す
- 負債は会社が返さなければならない借金や義務を示す
- 純資産は会社に残る自己資本や財務の安全性を示す
それぞれ順に解説します。
資産は会社が保有する現金や建物・設備などの財産を示す
資産の部は、貸借対照表の左側に記載され、会社が事業活動のために保有するすべての財産を表します。資産はさらに流動資産と固定資産に分類されます。
流動資産とは、1年以内に現金化できる、または使用する予定の資産です。具体的には、現金や預金、受取手形、売掛金、商品や製品などの棚卸資産が該当します。これらは事業活動の中で絶えず形を変えながら循環していくため、会社の日常的な資金繰りを支える重要な要素です。現金や預金は最も流動性が高く、いつでも支払いに使えます。売掛金は商品やサービスを販売したものの、まだ代金を回収していないものです。棚卸資産は販売予定の商品在庫や、製造途中の仕掛品などを指します。
一方、固定資産は1年を超えて長期的に保有し使用する資産で、建物、機械装置、土地といった有形固定資産、特許権やソフトウェアなどの無形固定資産、関係会社への出資金や長期貸付金などの投資その他の資産に分けられます。固定資産は事業の基盤となる設備や投資であり、簡単に現金化できませんが、長期的な収益を生み出す源泉となります。製造業であれば工場や機械設備が、小売業であれば店舗が固定資産の中心です。資産の部を見るときは、流動資産と固定資産のバランスに注目すると、その会社の資金の流動性や事業の性質が見えてきます。
負債は会社が返さなければならない借金や義務を示す
負債の部は、貸借対照表の右側上部に記載され、会社が将来返済しなければならない義務を表します。負債も流動負債と固定負債に区分されます。
流動負債は、1年以内に返済または支払いが必要な義務です。代表的なものとしては、買掛金、短期借入金、未払金、未払費用、前受金などがあります。買掛金は商品や原材料を仕入れたものの、まだ代金を支払っていないものです。短期借入金は1年以内に返済期限が来る借入金を指します。未払費用は給料や利息など、すでにサービスを受けたものの支払いがまだ済んでいない費用です。これらは日々の事業活動から生じる支払義務であり、適切に管理しないと資金繰りが行き詰まる原因となります。
固定負債は、返済期限が1年を超える長期的な義務です。長期借入金、社債、退職給付引当金などが含まれます。長期借入金は設備投資などのために銀行から借り入れた資金で、通常は複数年かけて返済していきます。社債は債券を発行して広く投資家から資金を調達したものです。退職給付引当金は、従業員の将来の退職金支払いに備えて計上される負債です。
負債は他人から調達した資金であるため、当然ながら返済義務が伴います。負債が多すぎると財務の安全性が低下し、金利負担も増えるため、経営者は負債の水準を適切にコントロールする必要があります。特に流動負債は短期的な支払能力に直結するため、流動資産との関係を常に注視しておくことが大切です。
純資産は会社に残る自己資本や財務の安全性を示す
純資産の部は、貸借対照表の右側下部に記載され、返済義務のない会社自身の正味の財産を表します。純資産は主に資本金、資本剰余金、利益剰余金から構成されます。
資本金は、株主が会社設立時や増資時に出資した元手となる資金です。会社の基礎体力を示す重要な項目であり、この金額が大きいほど財務的な安定性が高いといえます。資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金で、資本準備金などが含まれます。資本準備金は増資時に資本金に組み入れなかった部分などが積み立てられます。
利益剰余金は、会社が過去から積み上げてきた利益の蓄積です。毎期の損益計算書で計算された当期純利益は、配当として株主に分配されない限り、この利益剰余金として純資産に加算されていきます。逆に損失が出れば、利益剰余金は減少します。利益剰余金が多いということは、過去の事業活動で稼いだ利益を内部に留保し、会社の財産として蓄えてきたことを意味します。
純資産が大きいほど、会社の財務基盤は安定しており、外部からの借入に依存しない健全な経営をしているといえます。純資産がマイナスになる状態を債務超過といい、資産よりも負債が多く、理論上はすべての資産を売却しても借金を返せない危険な状態を意味します。金融機関や取引先は、純資産の額と資産全体に占める割合を重視して、会社の信用力を判断します。純資産比率が高い会社は、不況時にも倒産リスクが低く、安心して取引できる相手として評価されます。
貸借対照表の作り方と中小企業における実務上の注意点
貸借対照表を作成するには、日々の取引を正確に記帳し、それを整理して決算書の形にまとめる作業が必要です。大企業では専門の経理部門が対応しますが、中小企業では経営者自身や少人数のスタッフが担当することも多く、実務上の悩みを抱えるケースも少なくありません。
会計の専門知識がなくても、基本的な手順と注意点を理解していれば、正確な貸借対照表を作成できます。近年は使いやすい会計ソフトも普及しており、自動化できる部分も増えています。ここでは、貸借対照表を作成する際に必要な準備、具体的な手順、よくあるトラブルへの対処法、そして中小企業が活用できる簡略化の制度について説明します。正確な貸借対照表を作成することは、適切な税務申告や金融機関との良好な関係構築にもつながります。
- 準備する資料は試算表や総勘定元帳などの基礎情報
- 作成手順は資産・負債・純資産を整理して転記する
- 金額不一致は仕訳漏れや転記ミスを重点的に確認
- 省略ルールは簡易貸借対照表や附属明細の特例制度
それぞれ順に解説します。
準備する資料は試算表や総勘定元帳などの基礎情報
貸借対照表を作成するには、まず日常的な取引記録が整理されている必要があります。具体的には、仕訳帳や総勘定元帳、試算表といった会計帳簿が基礎資料となります。
仕訳帳は、日々の取引を借方と貸方に分けて記録した帳簿です。すべての取引は発生順に時系列で記録されます。総勘定元帳は、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに転記して集計した帳簿で、各科目の残高を確認できます。現金勘定、売掛金勘定、買掛金勘定といった具合に、科目ごとに取引の動きと残高が一目でわかるように整理されています。
試算表は、総勘定元帳の各科目の残高を一覧にしたもので、借方と貸方の合計が一致するかを検証できます。試算表が正しく作成されていれば、貸借対照表の作成作業はスムーズに進みます。これらの帳簿は、会計ソフトを使用していれば自動的に作成されますが、手書きやエクセルで管理している場合は、転記ミスや計算ミスに注意が必要です。
また、決算時には、減価償却の計算資料、棚卸資産の実地棚卸結果、金融機関の残高証明書、未払費用や前払費用の一覧など、期末の調整に必要な補助資料も準備します。棚卸は実際に倉庫や店舗にある在庫を数えて確認する作業で、帳簿上の在庫と実際の在庫を一致させるために欠かせません。これらの資料を正確に揃えることが、正しい貸借対照表を作成する第一歩です。
作成手順は資産・負債・純資産を整理して転記する
貸借対照表の作成は、試算表から必要な科目を抽出し、決算書の様式に転記していく作業が中心です。まず、試算表の各勘定科目が、資産、負債、純資産のどの区分に属するかを確認します。現金、預金、売掛金などは資産の部に、買掛金、借入金などは負債の部に、資本金、利益剰余金などは純資産の部に分類されます。
次に、決算整理を行います。これは、期末時点の正確な財政状態を反映させるための調整作業です。減価償却費の計上では、建物や機械設備などの固定資産について、使用による価値の減少分を費用として計上します。棚卸資産の評価では、実地棚卸の結果に基づいて帳簿上の在庫金額を修正します。引当金の設定では、貸倒引当金や賞与引当金など、将来発生が見込まれる費用や損失に備えて負債を計上します。未収収益や未払費用の計上では、当期に属する収益や費用を適切に期間配分します。
決算整理が終わったら、整理後試算表を作成し、各科目の最終的な金額を確定させます。そして、この整理後試算表から、資産の部は流動資産と固定資産に、負債の部は流動負債と固定負債に区分して、貸借対照表の様式に転記します。流動と固定の区分は、1年以内に現金化または支払いが予定されるかどうかが基準となります。
最後に、当期純利益を損益計算書から転記して純資産の部に加え、資産の合計と負債・純資産の合計が一致することを確認します。この最終チェックで両者が一致すれば、貸借対照表の作成は完了です。
金額不一致は仕訳漏れや転記ミスを重点的に確認
貸借対照表の作成中に、資産の合計と負債・純資産の合計が一致しないという問題に直面することがあります。これは必ずどこかに誤りがあることを示しており、放置してはいけません。
最も多い原因は、仕訳の入力漏れや入力ミスです。取引を記録し忘れたり、金額を間違えて入力したりすると、バランスが崩れます。また、試算表から貸借対照表へ転記する際に、科目を間違えたり、金額を書き間違えたりすることもあります。借方と貸方を逆に記録してしまうミスも起こりやすい誤りです。
確認の手順としては、まず試算表の段階で借方と貸方の合計が一致しているかをチェックします。ここで不一致があれば、仕訳の段階に問題があります。仕訳帳を最初から見直し、借方と貸方の金額が同じになっているかを確認します。
次に、決算整理仕訳が正しく記録されているかを確認します。減価償却や引当金の計上を忘れると、金額がずれる原因になります。決算整理仕訳は期末に集中して行うため、記録漏れが発生しやすい部分です。
さらに、各科目の残高が正しく分類されているか、流動と固定の区分が適切かも見直します。長期借入金を短期借入金に分類してしまうといった誤りは、分析結果にも影響を与えます。
どうしても原因が見つからない場合は、前期の貸借対照表と比較して、異常に増減している科目がないかをチェックすると、手がかりが見つかることがあります。前期と大きく変動している科目があれば、そこに記録ミスが潜んでいる可能性が高いのです。
省略ルールは簡易貸借対照表や附属明細の特例制度
中小企業の負担を軽減するため、会社法や税法では貸借対照表の作成において一定の簡略化が認められています。会社法では、中小企業は注記表や附属明細書の作成を省略できる規定があります。株式譲渡制限会社で、会計監査人を設置していない場合は、計算書類の注記を簡略化できます。
また、税務申告においても、青色申告を行う個人事業主や中小企業には特例があります。国税庁が公表している青色申告決算書では、貸借対照表を含む財務諸表の様式が簡略化されており、詳細な附属明細を求められません。中小企業庁でも、小規模事業者の経営支援として、簡易な財務管理の方法を案内しています。
ただし、簡略化が認められているからといって、いい加減な記録で済ませて良いわけではありません。金融機関からの融資を受ける際や、取引先との信頼関係を築く上では、正確で詳細な貸借対照表を作成できることが望ましいのです。簡略化の制度は、最低限の法的要件を満たすための措置であり、経営管理のためには、できる限り詳細な情報を記録し分析することが重要です。会計ソフトを活用すれば、専門知識がなくても比較的容易に詳細な貸借対照表を作成できます。
貸借対照表の分析方法は資金繰り改善と経営判断に直結
貸借対照表は作成するだけでは意味がありません。その内容を分析し、会社の財務状態を正しく理解してこそ、経営改善に役立てられます。特に資金繰りの安全性、収益性、成長性といった観点から貸借対照表を読み解くことで、経営上の課題や強みが明確になります。
数字を単に眺めるのではなく、科目間の関係や比率を計算することで、見えなかった問題点や改善の機会が浮かび上がってきます。また、自社の数字を時系列で追うだけでなく、同業他社や業界平均と比較することで、客観的な位置づけを把握できます。ここでは、貸借対照表を使った具体的な分析手法と、それを経営判断にどう活かすかを解説します。財務分析は難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な指標を理解すれば、誰でも実践できます。
- 流動資産と流動負債を比べると資金繰りと財務安定度がわかる
- 自己資本比率や流動比率など主要な財務指標を把握する
- 他社や業界平均と比較すれば自社の経営課題が明確になる
それぞれ順に解説します。
流動資産と流動負債を比べると資金繰りと財務安定度がわかる
短期的な資金繰りの安全性を測る最も基本的な指標が、流動資産と流動負債の関係です。流動資産は1年以内に現金化できる資産であり、流動負債は1年以内に支払わなければならない義務です。流動資産が流動負債を上回っていれば、短期的な支払能力に問題はないと判断できます。
この関係を数値化したものが流動比率で、流動資産を流動負債で割って算出します。一般的には流動比率が100パーセントを超えていれば安全とされ、150パーセントから200パーセントあれば理想的です。たとえば、流動資産が3000万円、流動負債が2000万円であれば、流動比率は150パーセントとなり、短期的な支払いに対して余裕がある状態です。
ただし、流動資産の中身にも注意が必要です。現金や預金、すぐに回収できる売掛金が多ければ問題ありませんが、売れ残った在庫や回収困難な債権が多いと、見かけ上の流動資産は多くても実際の支払能力は低いことになります。在庫が過剰に積み上がっていれば、それは売れ残りを意味し、実質的な価値は低下している可能性があります。
さらに厳しく見る指標として当座比率があり、これは流動資産から棚卸資産を除いた当座資産を流動負債で割ったものです。当座資産には現金、預金、売掛金など、すぐに現金化できるものだけが含まれます。当座比率が100パーセントを超えていれば、より確実に短期的な支払いに対応できる体制といえます。資金繰りに不安がある会社は、この当座比率を重点的にチェックし、改善策を考える必要があります。
自己資本比率や流動比率など主要な財務指標を把握する
貸借対照表からは、さまざまな財務指標を算出して会社の健全性を多角的に評価できます。自己資本比率は、純資産を総資産で割った割合で、会社の財務的な安定性を示す代表的な指標です。この比率が高いほど、借入金などの他人資本に依存せず、自己資金で事業を運営していることを意味します。
一般的には自己資本比率が30パーセント以上あれば健全とされ、50パーセントを超えれば非常に安定した財務体質といえます。逆に自己資本比率が低いと、金利負担が重く、景気悪化時に経営が不安定になりやすいリスクがあります。たとえば、総資産が1億円で純資産が4000万円であれば、自己資本比率は40パーセントとなり、まずまず健全な水準です。
固定比率は、固定資産を純資産で割った比率で、長期的な資金の安定性を見る指標です。固定資産は長期間使用する資産なので、その資金は返済不要な純資産で賄うのが理想であり、固定比率は100パーセント以下が望ましいとされます。固定比率が100パーセントを超えると、固定資産の一部を負債で調達していることになり、返済負担が生じます。
固定長期適合率は、固定資産を純資産と固定負債の合計で割ったもので、固定資産が長期的な資金でカバーされているかを確認します。固定資産への投資を短期借入金で賄っていると、返済期限が来たときに資金繰りに困る危険があります。固定長期適合率が100パーセント以下であれば、固定資産への投資が長期的な資金で支えられており、安全性が高いといえます。
これらの指標を定期的に計算し、推移を追うことで、財務体質の改善や悪化を早期に察知できます。毎月や四半期ごとに指標を計算し、グラフ化して視覚的に把握すると、傾向がより明確になります。
他社や業界平均と比較すれば自社の経営課題が明確になる
自社の貸借対照表を時系列で分析することも重要ですが、同業他社や業界平均と比較することで、より客観的な評価が可能になります。業種によって適正な財務指標は大きく異なります。
たとえば、製造業は工場や機械などの固定資産が多く必要なため、固定資産の比率が高くなる傾向があります。設備投資が大きい分、固定比率も高めになりますが、それは業種の特性として受け入れられます。一方、サービス業や情報産業は固定資産が少なく、流動資産の比率が高くなります。人材が主な経営資源であり、大規模な設備は不要だからです。小売業は在庫を多く抱えるため、棚卸資産の割合が大きくなります。商品を仕入れて販売するビジネスモデルでは、在庫の管理が経営の要となります。
業界平均のデータは、経済産業省の企業活動基本調査や、中小企業庁の中小企業実態基本調査などで公表されています。これらの統計データと自社の数値を比較することで、自社が業界内でどのような位置にあるのかを把握できます。自己資本比率が業界平均より低ければ、借入金の削減や利益の内部留保を増やす必要があるかもしれません。流動比率が低ければ、短期的な資金繰りの改善が急務です。
逆に、平均よりも優れている指標があれば、それは自社の強みとして認識し、さらに伸ばす戦略を考えられます。財務の健全性が高ければ、それを営業活動でアピールして取引先の信頼を得られるでしょう。業界比較を通じて、自社の現状を冷静に把握し、改善すべき点と伸ばすべき点を明確にすることが、戦略的な経営には欠かせません。
金融機関は融資審査で貸借対照表の健全性を重点的に確認する
銀行などの金融機関が融資を検討する際、最も重視するのが貸借対照表の内容です。金融機関は貸したお金が確実に返済されるかを判断するため、会社の財務的な安全性を厳しくチェックします。
金融機関は融資審査において、貸借対照表の健全性を重視します。自己資本比率や流動比率、債務償還年数などの指標を分析し、返済能力や財務の安全性を評価します。債務償還年数は、有利子負債を営業キャッシュフローで割った年数で、現在の借入金を何年で返済できるかを示します。この年数が短いほど返済能力が高いと評価されます。一般的には10年以内が望ましく、5年以内であれば非常に優良とされます。
また、金融機関は前期との比較も行い、資産や負債の増減理由を確認します。急激に借入金が増えていたり、売掛金や在庫が異常に膨らんでいたりすれば、経営に問題がないか質問されるでしょう。売掛金が増えているのは売上が伸びた結果なのか、それとも回収が滞っているのか、その理由を明確に説明できる必要があります。
金融機関の審査では、債務者区分という考え方があり、正常先、要注意先、破綻懸念先などに分類されます。財務内容が健全であれば正常先に分類され、優遇金利で融資を受けられる可能性が高まります。逆に財務内容に問題があれば、融資を断られるか、高い金利を求められることになります。
中小企業が融資を受けやすくするためには、日頃から正確な貸借対照表を作成し、財務体質の改善に努めることが不可欠です。自己資本を増やし、無駄な在庫を減らし、借入金を計画的に返済していく地道な努力が、金融機関からの信頼につながります。
貸借対照表に関するよくある質問に回答
貸借対照表について初めて学ぶ方や、実務で扱い始めた方からは、共通する疑問や質問が多く寄せられます。専門用語が多く、複雑に感じる部分もあるため、基本的な疑問を解消しておくことが理解を深める近道です。
ここでは、貸借対照表の作成頻度、個人事業主やフリーランスにおける必要性、青色申告との関係、他の財務諸表との関連、そして会計の基礎用語である借方と貸方の意味について、実務的な観点から回答します。これらの疑問を解消することで、貸借対照表への理解がさらに深まり、実際の業務や経営判断に活かせるようになるでしょう。
貸借対照表はどのくらいの頻度で作成すべきですか?
法的に義務付けられているのは、決算期ごとの年1回の作成です。株式会社であれば事業年度末に決算を行い、貸借対照表を含む決算書を作成して株主総会での承認を得ます。個人事業主も、確定申告の際に貸借対照表を提出します。
しかし、経営管理の観点からは、年1回だけでは不十分です。多くの企業では、月次決算として毎月貸借対照表を作成し、資金繰りや財務状態の変化を把握しています。月次で作成することで、問題の早期発見や迅速な経営判断が可能になります。たとえば、在庫が急増していれば売れ行きの鈍化を早期に察知でき、対策を講じられます。売掛金が増えていれば、回収に問題がないか確認し、資金繰りに支障が出る前に手を打てます。
金融機関から融資を受けている場合は、定期的な財務報告を求められることもあります。四半期ごとや半期ごとに貸借対照表の提出を求められることがあり、これに応じることで金融機関との信頼関係も深まります。また、会計ソフトを使用していれば、リアルタイムで貸借対照表を確認することも可能です。経営者は自社の状況に応じて、適切な頻度で貸借対照表を確認する習慣を持つことが大切です。
個人事業主やフリーランスでも貸借対照表は必要ですか?
個人事業主やフリーランスの場合、事業規模や申告方法によって必要性が変わります。白色申告を行う場合は、貸借対照表の作成は義務付けられていません。収支内訳書を提出すれば足ります。収支内訳書は簡易的な損益の記録で、収入と経費を集計したものです。
一方、青色申告を選択する場合は、複式簿記による記帳が要件となり、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。青色申告には最大65万円の特別控除が受けられるメリットがあるため、多くの個人事業主が青色申告を選択しています。65万円の控除は税負担を大きく軽減できるため、貸借対照表を作成する手間をかける価値は十分にあります。
貸借対照表を作成することで、事業の財産や借入金の状況を正確に把握でき、資金計画や事業拡大の判断材料になります。自分の事業にどれだけの資産があり、どれだけの負債があるのかを把握することで、健全な経営判断ができるようになります。また、金融機関から融資を受ける際にも、貸借対照表があれば信用力の証明になり、審査が通りやすくなる可能性があります。フリーランスであっても、事業を継続的に拡大していくつもりであれば、貸借対照表を作成する意義は大きいといえます。
青色申告をする場合に貸借対照表の作成は必須ですか?
青色申告には複数の種類があり、それぞれ要件が異なります。青色申告特別控除には10万円控除と65万円控除があり、65万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳と貸借対照表および損益計算書の作成、ならびに電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が必要です。10万円控除の場合は、簡易簿記でも可能で、貸借対照表の作成は必須ではありません。
2020年分の申告からは、65万円控除を受けるためには、電子申告を行うか電子帳簿保存を行うことが追加要件となりました。つまり、複式簿記で記帳して貸借対照表を作成するだけでなく、e-Taxで申告するか、会計ソフトで電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。この要件を満たさない場合、控除額は55万円に減額されます。
青色申告は、最大65万円の特別控除のほか、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除など、さまざまな税制優遇が受けられる制度です。青色事業専従者給与は、家族への給与を経費として認めてもらえる制度で、節税効果が大きいメリットです。純損失の繰越控除は、赤字が出た年の損失を翌年以降3年間繰り越して、黒字と相殺できる制度です。
これらのメリットを享受するためには、貸借対照表をはじめとする正確な帳簿書類の作成が欠かせません。手間はかかりますが、会計ソフトを活用すれば、専門知識がなくても比較的容易に作成できます。クラウド型の会計ソフトなら、自動的に電子帳簿保存の要件も満たせるものが多く、初心者でも安心して利用できます。
貸借対照表と損益計算書をあわせて読むべきですか?
貸借対照表と損益計算書は、必ずセットで読むべきです。両者は別々の書類ですが、密接に関連しており、一方だけを見ても会社の全体像は把握できません。貸借対照表は特定時点の財政状態を示すのに対し、損益計算書は一定期間の経営成績を示します。
たとえば、損益計算書で多額の利益が出ているのに、貸借対照表で現金が減少していれば、売掛金の回収が遅れているか、設備投資に資金を使ったことが推測できます。売上は好調でも、顧客からの入金が遅れていれば、手元の現金は不足します。あるいは、利益を使って新しい機械を購入していれば、現金は減っても固定資産が増えているはずです。
逆に、損益計算書では利益が少なくても、貸借対照表で純資産が増えていれば、過去からの利益蓄積があり、財務基盤は安定していると判断できます。今期は一時的に利益が少なくても、過去に稼いだ利益が内部留保されていれば、会社の体力は十分にあるといえます。
また、損益計算書の当期純利益は、貸借対照表の純資産の部にある利益剰余金に加算されます。このように、二つの書類は連動しているため、両方を合わせて分析することで初めて、会社の真の姿が見えてきます。可能であれば、キャッシュフロー計算書も加えた財務三表すべてを確認することが理想です。キャッシュフロー計算書を見れば、実際の現金の出入りがわかり、資金繰りの実態をより正確に把握できます。
借方と貸方の意味がわからないのですが…
借方と貸方は、複式簿記の基本概念で、取引の二面性を記録するために使われます。資産の増加は借方(左側)に、減少は貸方(右側)に記録します。負債と純資産は逆で、増加は貸方、減少は借方に記録します。
たとえば、10万円の現金を借り入れた場合、現金(資産)の増加として借方に10万円、借入金(負債)の増加として貸方に10万円を記録します。この仕組みにより、取引の両面が正確に記録され、誤りを発見しやすくなります。すべての取引は必ず借方と貸方の両面から記録され、その合計金額は常に一致します。
貸借対照表では、左側が借方、右側が貸方です。左側の資産が増えれば借方に記録され、右側の負債や純資産が増えれば貸方に記録されます。現金で商品を購入した場合、現金という資産が減るので貸方に記録し、商品という資産が増えるので借方に記録します。
借方や貸方という名称は、昔の商習慣に由来するもので、現代では必ずしも意味が直感的ではありません。そのため、借方を左側、貸方を右側と単純に覚えてしまうほうが理解しやすいでしょう。借りる側だから借方、貸す側だから貸方と考えると混乱しやすいため、位置で覚えることをおすすめします。
会計ソフトを使えば、借方と貸方を意識しなくても自動的に処理されますが、基本的な考え方を理解しておくと、会計への理解が深まります。簿記検定などで学ぶ内容ですが、実務では会計ソフトが自動処理してくれるため、細かいルールを暗記する必要はありません。ただし、仕訳の意味を理解していると、エラーが出たときの対処や、財務状態の把握がよりスムーズになります。