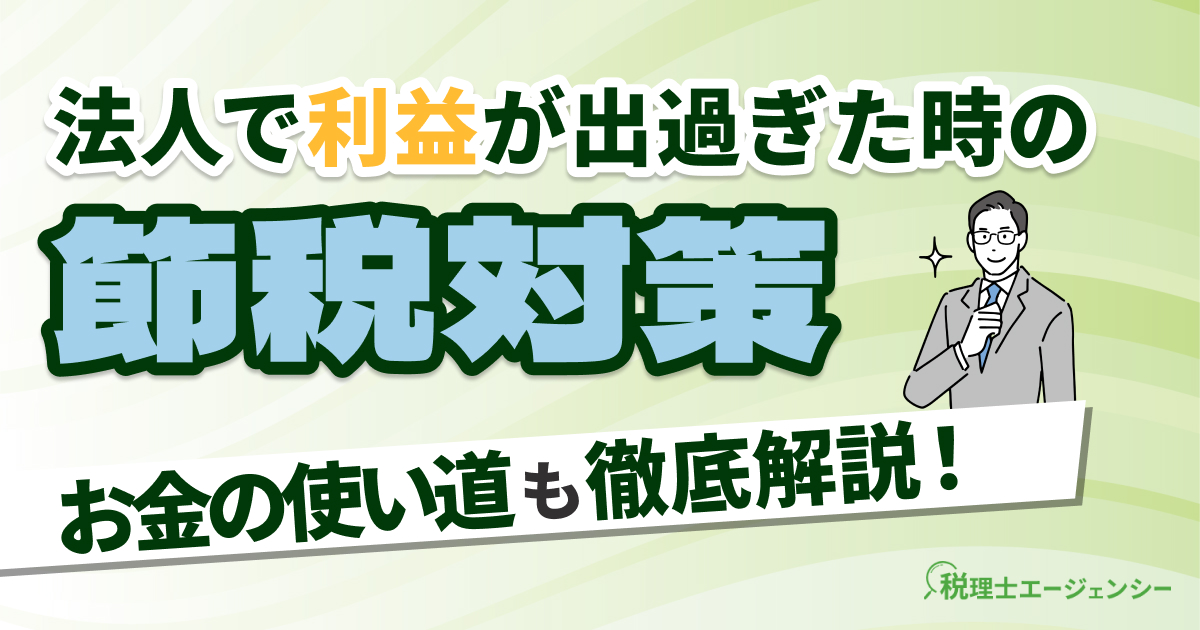事業者が本業を行い利益を出すのは当たり前で、むしろ望ましいことではあります。一方で、そのまま申告してしまうと、確実に法人税等納税額が上がってしまいます。
納税するくらいならば、別の有益なことにお金を使って「節税対策したい」と言う経営者の方もいらっしゃるはずです。そこで、今回は合法的に法人ができる節税対策を紹介します。
もちろん、納税は国民の義務ですので高額納税していただいても良いわけですが、賢い経営者はその前に出た利益を使って自社の経営改善や体質の見直しを図るはずです。
そうした方法について、今回は紹介していきます。
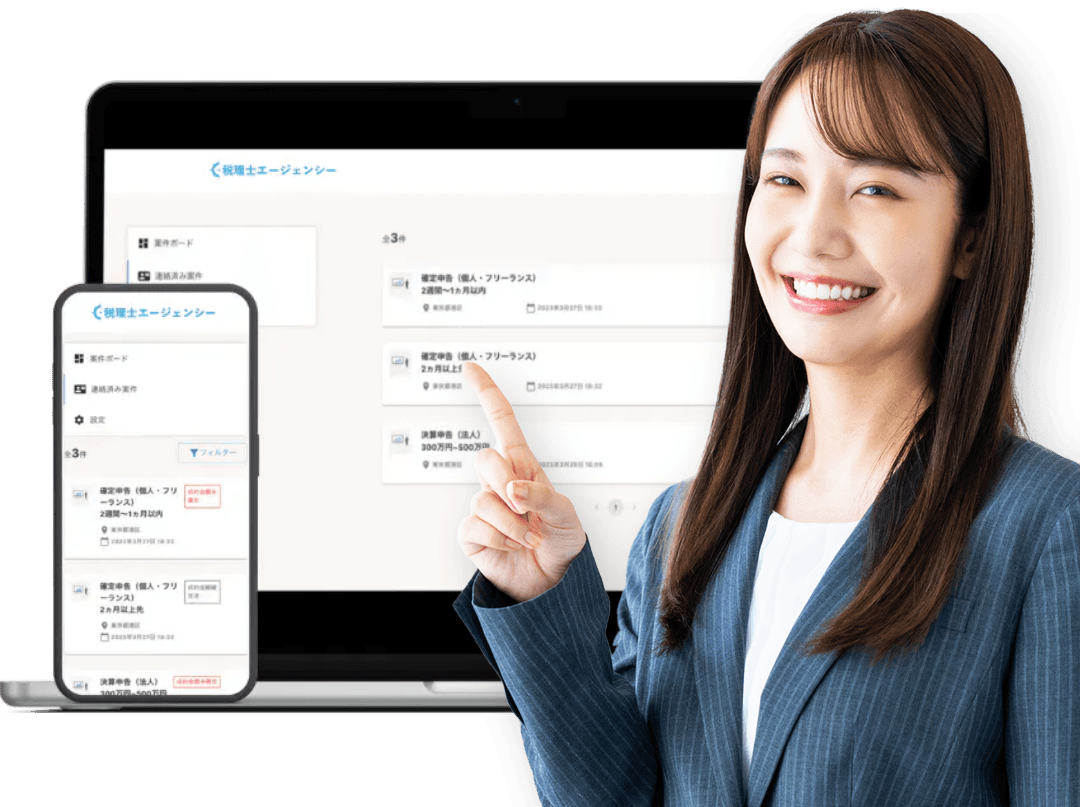
当サービス「税理士エージェンシー」なら専門性の高い税理士と無料でマッチングできます。税務・資金調達に関してお悩みの方は税理士エージェンシーをご活用ください。
法人利益が出過ぎた場合に使える代表的な節税方法6つ
有名企業が、誰も来ないイベントを開催したり、趣味としか思えない箱ものを作ると、「あれは税金対策で作ったもので儲からなくて良い」と言われることがあります。そこまで露骨な例は少ないかもしれませんが、あまり採算性がない支出を増やして、経費、損金として計上して課税所得を減らすと言うのも代表的な節税方法になります。
- 経費を増やして利益を抑える節税対策
- 給与や賞与を増やして利益を分散する節税対策
- 資産の変動を利用した節税対策
- 保険や共済を活用した節税対策
- 引当金や準備金を活用した将来支出への備え
- 税額控除制度を活用して法人税を直接減らす方法
ここでは法人利益が出過ぎたときに使える代表的な節税方法について6つ紹介します。
経費を増やして利益を抑える節税対策
法人の決算時に利益が想定以上に膨らんでしまうと、その分法人税の負担も大きくなります。納税は企業の義務(国民の義務)ですが、適切な節税対策を講じることで、納税額を減らして、その分を将来の資金繰りや事業拡大に備える自己資本にできます。
特に短期間で実行できる方法としては、計上できる経費を漏れなく整理し、しっかり計上し、利益を圧縮することが基本となります。役員賞与や福利厚生費、広告宣伝費、修繕費といった支出の検討や、前払費用の活用、消耗品の購入など、正しく認められる経費を増やすことで、節税効果を得られます。もちろん、独りよがりなものであってはならず、従業員の士気、モチベーションを高め、公正であることも重要です。
本項では、利益が出すぎたときに有効な代表的な6つの節税手法について解説し、決算直前でも取り組める実践的な方法を紹介します。
WEB広告やHP制作など広告宣伝費の活用
法人の利益が大きくなりすぎた場合に有効な方法のひとつが、広告宣伝費の活用です。広告宣伝費は販売促進のための支出であり、売上拡大や会社の認知度向上に直結するため、将来の成長投資として位置付けられます。
具体的には、リスティング広告(検索すると出てくる検索連動型広告)やSNS広告といった最近流行りのWEB広告の出稿、動画広告の制作、あるいは企業ホームページの新規制作やリニューアルといった取り組みが考えられます。これらはすべて経費として処理できるため、決算期直前に実施すれば利益を圧縮しながら事業の基盤強化につなげられます。
また、デザイン刷新やSEO対策などもしっかり組み込むことで、集客力の向上やブランディング強化も期待できます。単なる節税手段にとどまらず、将来の収益を見据えた投資、即効性はないが「未来への種をまく」と言う重要な戦術を稼ぎすぎた利益で行います。
余剰利益を効率的に活用しつつ、次の成長へ備える戦略的な支出として検討する価値があります。
社員旅行・健康診断・社宅制度など福利厚生費の活用
次が、福利厚生費の拡充です。福利厚生費は従業員の働きやすさや生活の安定を支える支出であり、適切に計上すれば経費として認められます。
たとえば、社員イベント(昔のような社員旅行ではなく新時代のニーズにマッチしたもの)を実施すれば社員のモチベーション向上やチームワーク強化につながり、そのうえで経費として処理されるので法人税の圧縮も可能です。
また、年1回の定期健康診断や人間ドックの費用を会社負担とすることで、従業員の健康維持を図りつつ経費計上ができます。さらに、一定の条件を満たした社宅制度を導入すれば、社員の生活支援、自己負担の低減と同時に会社側も節税効果を得られる点が魅力です。最近では福利厚生費で従業員の自己負担を減らした社食も人気です(有名企業の社食は従業員負担が500円を切るなどすごく安いです)。
福利厚生費は単なる経費消化ではなく、「この会社で働きたい」「この会社ならお金が貯まる」と言う直接的な就職希望者の応募意欲にも寄与します。利益を調整しながら企業価値を高める実践的な方法として、福利厚生の充実は検討に値します。
出張手当や日当の適正設定で損金算入する
出張手当や日当の制度を適正に整備し、損金算入する方法が有効です。役員や従業員が業務で出張する際に支給される日当は、旅費規程を明確に定めておけば、給与として課税されずに会社の経費として処理できます。
具体的には、宿泊を伴う出張や日帰り出張に応じて、交通費や宿泊費とは別枠で日当を設定し、実務に即した金額を支給する形です。現在出張時の宿泊代が上限10,000円なら大したホテルに泊まれません。下手すると従業員が自腹を切ることなります。
これを実費精算に変える、15000円上限に変えるだけで、出張のモチベーションも変わります。出張手当増額も同様の効果があり従業員にとっては手取りの増加につながり、会社にとっては利益を圧縮できると言う双方にメリットのある仕組みとなります。
ただし、過度に高額な日当を設定すると、税務調査で否認されるリスクがあるため、一般的な水準を参考にした適正額の設定が欠かせません。社内規程を整備し、運用を徹底することで、節税効果を得ながら従業員満足度の向上にもつなげられる点が大きな利点です。
短期前払費用の特例を利用した費用を計上する
検討したい節税策のひとつが「短期前払費用の特例」の活用です。通常、保険料や家賃、リース料などは支払った期間に応じて月割りで経費化する必要があります。しかし、短期前払費用の特例を利用すれば、翌期以降の費用であっても支払日から1年以内に提供を受けるサービスに関しては、支払った年度に全額を損金算入できるのです。
来期分のオフィス賃料やリース契約料を前倒しで支払えば、今期の経費として処理できるため、利益の圧縮につながります。この制度は税務上正式に認められた方法であり、計画的に活用することで決算直前でも即効性のある節税が可能です。ただし、支払先や契約内容によっては対象外となるケースもあるため、適用条件を確認することが重要です。正しく運用すれば、資金繰りを安定させつつ効果的に税負担を軽減できます。
消耗品やリース料など必要経費の前倒し支出
消耗品やリース料などの必要経費を前倒しで支出することで、法人税の負担を軽減する方法があります。日常業務で使用する文具や事務用品、コピー用紙やPC周辺機器などの消耗品は、購入した年度に全額を経費として計上できます。
また、オフィス機器や車両のリース料も、支払日ベースで経費算入が可能な場合が多く、決算期直前に翌期分を前倒しで支払うことで、当期の利益圧縮につなげられます。この手法のメリットは、税負担を抑えつつ必要な物品やサービスの準備も同時に進められる点です。
ただし、あくまで実務上必要な範囲の支出でなければ、税務上否認されるリスクがあります。また、コピー用紙を数年分まとめて仕入れても、翌年以降はコピー用紙代を経費計上できなくなります。あくまで需要の先食いであり、今年は節税になっても、来年は増税になる可能性が高いです。
計画的に前倒し支出を行い、購入や契約内容を適切に記録しておくことで、節税効果を得ながら資産や設備の整備も進められれば、実務的で即効性のある手法です。
給与や賞与を増やして利益を分散する節税対策
決算期に利益が大幅に出た場合、法人税の負担を軽減する手段として、給与や賞与を増やして利益を分散する方法があります。本来賞与(ボーナス)は利益を従業員へ還元するもので、制度の趣旨に合致します。
役員や従業員に対して適正な範囲で報酬を増額したり、期末賞与を支給したり、臨時賞与を支給することで、会社の利益を圧縮し、同時に従業員への還元も可能です。臨時賞与があれば、従業員のモチベーションアップに直結します。
給与や賞与は損金として計上できるため、法人税の節税効果が得られます。また、従業員満足度の向上や士気の強化にもつながるため、単なる節税手段にとどまらず、会社の成長戦略の一環として活用できます。本項では、利益分散による節税の考え方や注意点、実務での具体的な手法について解説します。
役員報酬の適正化と定期同額給与での設定
役員報酬の適正化を図ることも有効な節税手段です。役員報酬は原則として損金算入できる範囲が決まっており、定期同額給与として適切に設定することで、法人税の圧縮が可能になります。
定期同額給与とは、毎月同じ金額を支給する給与のことで、税務上も損金として認められやすく、臨時に大幅な増額や減額を行う場合と比べて安定した経費計上ができます。これにより、会社の利益を計画的に調整し、法人税負担を平準化することが可能です。
また、役員報酬の額は業績や会社規模に見合った適正水準で設定することが重要で、過大・過少な設定は税務上問題となる場合があります。自分や家族の取締役だけ、高額な役員報酬を設定すれば、税務署からのチェックも受けますし、他の役員や従業員の士気は低下、関連機関へのタレコミなども誘発してしまいます。
適切な報酬体系を整備することで、節税効果を享受しつつ、役員への報酬管理も透明性を持たせられ、企業運営の安定化にも寄与します。
決算賞与を従業員に支給して人材定着を図る
従業員への決算賞与(ボーナス)支給は有効な節税手段となります。決算賞与は、期末に支給する役員や従業員への報酬として損金算入が認められるため、法人税の負担を圧縮しつつ利益を調整できます。さらに、業績に応じた賞与制度を整備することで、従業員の働きがいを高め、モチベーション向上や離職防止にもつながります。
支給額や対象者を明確にし、事前に支給規程を整備しておくことが税務上のポイントで、曖昧な運用は否認のリスクを伴います。計画的に決算賞与を活用すれば、節税効果だけでなく、社員満足度(モチベーションアップ)の向上や人材定着にも寄与でき、企業の安定経営や将来の成長戦略にもつながります。資金繰りに無理のない範囲で実施することが重要です。
福利厚生の一環として従業員手当や奨励金を拡充
福利厚生の一環として従業員手当や奨励金を拡充することも有効な節税策です。手当や奨励金は従業員への報酬の一部として損金算入が認められるため、利益を圧縮しつつ社員への還元が可能になります。
具体例としては、通勤手当や住宅手当の増額、業績連動型の奨励金の支給、特定の資格取得や技能向上に対する奨励金などが挙げられます。これらは単なる経費処理ではなく、従業員の働きがいやスキル向上、離職防止にもつながるため、長期的な企業価値の向上にも寄与します。
支給の範囲や金額は適正な水準で設定し、社内規程や支給基準を明確にしておくことが重要です。計画的に実施することで、税務上のリスクを回避しつつ、節税効果と人材定着の双方を同時に実現できる、実務上有効な施策と言えます。
難関資格を取得した従業員には、資格取得奨励金(報奨金)+今後毎月数万円の「資格手当」を出すようにすれば、節税と優秀な従業員の会社への定着を両方達成可能です。有能な人材が資格手当目当てで転職希望してくるかもしれません。
社会保険料控除も加味した従業員還元の最適化
従業員への還元を検討する際には、社会保険料控除も加味した最適化が重要です。給与や賞与を増額する場合、従業員と会社双方の社会保険料負担も増えるため、単純に報酬を増やすだけでは期待する手取りや節税効果が得られないことがあります。
給料を増やせば、それだけ支払う社会保険料も増額となります。昨今手取りが増えないのは、「目に見えない増税」である社会保険料の増額が影響しているためと認知されつつあります。
そのため社会保険料の影響を踏まえた上で手取りや会社負担をバランス良く調整することが必要です。賞与支給額の調整や手当の種類の見直しを行うことで、経費計上による法人税圧縮効果を維持しつつ、従業員の満足度やモチベーション向上を図れます。実は社会保険料(社会保険、厚生年金)については「従業員と会社が1/2ずつ折半」とされていますが、会社が多めに負担することも違法ではありません。10万円の社会保険料があれば、従業員5万円、会社5万円ではなく、従業員4万円、会社6万円でも良いのです。会社の方が多めに払う分には大丈夫です。
一例として、「超高給企業」「超絶ホワイト企業」で知られる医学書院は、募集要項で「介護保険を含む健康保険料・厚生年金保険料の個人負担分を手当として支給」としています。給与から天引きされた社会保険料と同額を手当として支給されるため、実質社員の自己負担がゼロになります。
医学書院の正社員は、社会保険料について自己負担しなくて済み、額面=手取り+所得税、住民税になります。このような「裏技」も利益が上がっている企業ならば可能なのです。
資産の変動を利用した節税対策
法人の利益が予想以上に増えた場合、資産の変動を活用した節税対策も有効です。具体的には、有形固定資産の減価償却費の計上や、保有資産の評価見直しによる含み損益の調整などが挙げられます。
これにより、決算期の利益を圧縮し、法人税負担を抑えることが可能です。また、将来の投資や設備更新を見据えた計画的な資産購入や処分も、節税効果と事業戦略の両立につながります。本記事では、資産の動きを活用した法人節税の基本的な考え方と実務上のポイントについて解説し、利益調整に役立つ具体策を紹介します。
IT投資・機械導入・社屋改修など設備投資の実施
節税対策として設備投資を行うことは有効です。IT投資や機械導入、社屋の改修などは、将来の事業効率や生産性向上につながる支出であり、減価償却費として計上することで利益を圧縮し、法人税の負担を軽減できます。
たとえば、業務効率化のためのソフトウェアやサーバー機器の購入、生産設備の更新、オフィス環境の改善に伴う内装工事や空調設備の導入などが対象です。
また、計画的な設備投資は企業の資産価値向上にも寄与し、長期的な経営戦略の一環として活用できます。短期的に会社の設備投資を集中的に行い、それが将来への会社のインフラにつながることもあります。
節税効果を最大化するためには、減価償却の方法や耐用年数の設定を適切に行い、投資目的や内容を明確にして会計処理を行うことが重要です。利益調整と事業成長を同時に実現できる、実務上有効な節税手段と言えます。
細かい話ですが「蛍光灯2027年問題」と言うものがあります。従来の蛍光灯は2027年に新規に製造、輸入できなくなり、LEDに全部切り替えなければならなくなります。電球を変えるだけならまだ良いのですが、メーカーではソケット等照明器具全般の取り換えを推奨しています(事故のリスク)。そうなると、事業用電灯については大々的な工事が必要になります。2027年には工事が集中し価格も高騰することが予想され、節税どころか利益が吹っ飛ぶ可能性もあります。
まだ着手している事業者が少ない今、電球のLED化を進めることで、必要な設備投資を前倒しで行い、税務当局も納得できる節税策につなげられます。
少額減価償却資産の購入による即時償却
少額減価償却資産の購入による即時償却は、即効性のある節税策として有効です。少額減価償却資産とは、取得価額が一定金額以下の固定資産で、税務上、購入した年度に一括で経費計上できる制度を指します。これを活用することで、通常は数年にわたり減価償却する資産でも、決算期にまとめて損金算入が可能となり、利益圧縮につながります。
具体例としては、パソコンや事務機器、工具、少額の設備機器など、日常業務で使用する固定資産が対象となります。即時償却を適切に活用すれば、税負担を減らすだけでなく、必要な設備投資を決算期内に効率的に行えます。ただし、制度の対象金額や適用条件を満たす必要があるため、購入計画を事前に確認し、会計処理を適切に行うことが重要です。短期的な利益圧縮と事業投資を両立できる実務的な手法と言えます。
通常10万円以上のものは設備として減価償却しますが、20万円のパソコンを4年にわたり5万円ずつ減価償却(5万円しかその年の経費、損金計上できない)するよりも、少額資産購入の特例を使い、20万円を1年で経費計上した方が良いと言う考え方です。当然経費計上した(買った)年には税金が減ります。
不要な在庫の処分による棚卸資産の圧縮
不要な在庫の処分によって棚卸資産を圧縮する方法も有効な節税策です。棚卸資産は決算時点で評価替えを行い、時価や販売見込みに応じて減損処理することが認められており、これにより利益を調整できます。
具体的には、売れ残りや「不良債権化した」製品、正規品では流通できない傷のある製品などを適正に処分し、簿価を減額することで、当期の利益を圧縮し法人税負担を軽減できます。
また、処分に伴う損失は経費として計上可能で、税務上も認められる方法です。ただし、適正な帳簿管理や証憑の保管が必要であり、任意の過大な評価減は否認されるリスクがあります。計画的かつ透明性のある在庫整理を行うことで、節税効果を得ながら在庫の健全化や資金繰りの改善にもつなげられる、実務的に有効な施策です。
不要固定資産の売却や除却による損失計上
利益が過剰に計上された場合、不要な固定資産の売却や除却による損失計上は、即効性のある節税手段として有効です。使用しなくなった機械や車両、オフィス設備、建物の一部などを売却した場合、売却価格と帳簿価額の差額は損益として計上でき、利益を圧縮することが可能です。
売却が困難な資産については、除却処理を行い、簿価を損失として計上することも認められています。これにより、当期の法人税負担を軽減できるだけでなく、資産の有効活用や、不要資産の維持管理コスト削減にもつながります。
ただし、税務上は適正な帳簿管理や処分記録の保管が求められ、任意の過大な評価損は否認されるリスクがあります。計画的に不要資産を整理し、損失を適切に計上することで、節税効果と企業資産の健全化を同時に実現できる実務的な方法です。税理士と相談しながら適法の範囲で進めてください。
定率法から定額法など減価償却方法の見直し
減価償却方法の見直しも有効な節税手段です。固定資産の減価償却には定率法や定額法など複数の方法があり、それぞれ償却費の計上タイミングや金額が異なります。
減価償却方法は原則として資産取得時に選択し、その後は原則として継続適用が必要です。例外的に税務署への届出を行えば変更できる場合もありますが、恣意的な利益操作は認められません。利益調整を目的に都度切り替えることはできないため、実務上は取得時点での選択が重要です。
ただし、税務上は減価償却方法の変更には原則として適正な理由と届出が必要であり、無計画な変更は否認されるリスクがあります。相応の理由について、税理士と相談し、税務調査に耐えられるようにお願いいたします。
固定資産の取得時期や耐用年数、業務使用状況を踏まえた上で、会計処理を適切に行うことが重要です。計画的に減価償却方法を見直すことで、節税効果を享受しながら資産管理を効率化できる、実務上有効な手法と言えます。
保険や共済を活用した節税対策
法人の利益が大幅に増えた場合、保険や共済を活用した節税対策は有効な手段です。生命保険や損害保険、医療共済などの法人契約に加入することで、支払った保険料を損金として計上でき、利益圧縮につながります(個人の生命保険や家の火災保険などを会社の経費で落とすことはNGです)。
特に、将来の役員退職金や従業員福利厚生の準備として小規模企業共済など活用する場合、資金を確保しつつ税負担を抑えられるため、単なる節税にとどまらず経営リスクの軽減にも寄与します。本記事では、保険や共済を活用した法人節税の基本的な考え方と、実務で注意すべきポイントについて解説し、利益調整に役立つ具体策を紹介します。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金控除
利益が予想以上に出た場合、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を活用した節税は非常に有効です。この共済は、取引先の倒産による売掛金回収不能リスクに備える制度であり、毎月の掛金を損金として計上できます。掛金は最大で月額20万円、年間240万円まで積み立て可能で、支払った分だけ法人税の課税所得を圧縮できます。
さらに、掛金は将来的に取引先倒産時の貸付や解約時の返戻金として受け取れるため、資金繰りの安定にもつながります。解約時の返戻金は益金(売上)処理となりますが、閉業の際なら本業の売上は少なくなっているはずなので、そこまで大きな影響はないでしょう。
中小企業倒産防止共済制度の利用は、決算期直前でも掛金支払いを増額することで即効性のある節税効果が期待でき、利益圧縮とリスク管理を同時に実現できます。一方、掛金減額については一定の条件や手続きが必要になります。
掛金の損金算入には契約の適正性や確定申告時の決まり(確定申告時に「別表10(7)」の提出が必要で提出しないと損金算入できない)の遵守が必要で、計画的な掛金支出と会計処理が重要です。利益が出すぎた年度の節税手段として、実務上活用価値の高い制度と言えます。
小規模企業共済による役員の退職金積立
法人の利益が過剰に計上された場合、小規模企業共済を活用した役員退職金の積立は、有効な節税策となります。小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員が将来の退職金準備を目的に加入できる制度で、掛金は全額が所得控除の対象となります。
誰でも加入できるわけではなく、以下の方々のみ加入できます。
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
あくまで個人事業主やフリーランス、小規模事業所の経営者向けの制度であって、中小企業以上の法人経営者は加入できませんので、ご注意ください。また従業員は当然退職金を積み立てることになります。
法人が役員個人に対して掛金を支払う場合、役員報酬から小規模企業共済掛金を支払うことになります。その分の役員報酬を増額する意味では法人税減税にも関係します。ただし、小規模企業共済は経営者個人の所得税や住民税を減らすためのものであり、法人節税は副次的なものであることにご注意ください。
法人向け医療保険・がん保険の福利厚生利用
法人の利益が想定以上に増えた場合、法人向け医療保険やがん保険を福利厚生として活用することは、節税と従業員満足度向上の両面で有効です。法人が契約者となり、従業員や役員を被保険者とした保険料を支払う場合、その保険料は損金として計上でき、法人税の課税所得を圧縮できます。
医療保険やがん保険に加入することで、従業員が病気や入院した際の経済的リスクを軽減でき、安心して働ける環境を提供できます。また、福利厚生制度の一環として導入することで、従業員のモチベーションや定着率向上にもつながります。
ただし、保険契約内容や対象者、保険料負担の割合によっては税務上の取り扱いに注意が必要です。計画的に保険を選定・導入することで、利益圧縮による節税効果と、従業員の健康・福利厚生の向上を同時に実現できる実務的な施策と言えます。
病気になり保険を請求するかどうかは、従業員個人のプライバシーにもかかわることなので、会社への報告義務を課すなどはコンプライアンス面で注意も必要になります。
養老保険・長期平準定期保険の節税効果と制限
法人の利益が大幅に増えた場合、養老保険や長期平準定期保険を活用した節税策は、将来の資金準備と法人税負担の圧縮を両立できる手段です。養老保険は満期保険金や死亡保険金が一定額支払われる商品で、保険料の一部を損金算入できるため、決算期の利益圧縮に役立ちます。
長期平準定期保険は、保険期間中の保険料を一定水準に保ちながら、保障期間終了時に資金を受け取れる商品で、同様に経費計上が可能です。ただし、保険料の全額が損金算入できるわけではなく、契約条件や税法上の制限により控除対象となる金額には上限があります。
また、過度な積立型保険の活用は税務上否認されるリスクがあるため、税理士としっかり相談しながら進めてください。適切に運用すれば、利益調整による法人税の節税効果を得つつ、将来の退職金や資金準備としても活用できる、実務上有効な手法です。
福利厚生型の保険加入で従業員満足度も向上
福利厚生型の保険加入は節税と従業員満足度向上を同時に実現できる有効な手段です。法人が契約者となり、従業員や役員を被保険者とする医療保険や就業不能保険、傷害保険などの保険料を支払う場合、その費用は損金として計上でき、利益圧縮による法人税の軽減効果が期待できます。
加えて、従業員は病気やけがに備えた保障を受けられるため、安心して働ける環境が整い、モチベーションや定着率の向上にもつながります。福利厚生として保険を提供することで、企業の魅力向上や人材確保にも寄与し、単なる節税策にとどまらず長期的な経営戦略の一環として活用可能です。
ただし、保険の種類や契約内容、対象者や保険料の負担割合によっては税務上の取り扱いに注意が必要で、適正な契約設計と会計処理が求められます。計画的に導入することで、利益圧縮と従業員還元を両立させる実務的な節税策と言えます。
引当金や準備金を活用した将来支出への備え
法人の利益が大幅に増えた場合、引当金や準備金を活用することで、将来の支出に備えつつ節税効果を得ることが可能です。引当金とは、賞与や退職金、修繕費用など将来発生する見込み支出に対して事前に計上する会計処理で、一定の条件を満たせば損金として認められます。
また、準備金を活用すれば、事業拡大や設備更新など将来の投資資金を確保しながら、当期の利益を圧縮できます。適切に設定することで、税負担の軽減と資金計画の安定化を同時に実現できるため、企業経営の戦略的手段として有効です。本記事では、引当金や準備金を活用した節税の基本的な考え方と、実務上のポイントについて解説します。
貸倒引当金の計上で将来のリスクに備える
貸倒引当金を計上することは、将来のリスクに備えつつ節税効果を得る有効な手段です。貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの債権が将来回収できなくなるリスクに備えて、あらかじめ損失見込み額を計上する制度です。税務上、一定の計算方法や基準にもとづき適切に設定すれば、損金として認められ、当期の利益圧縮につながります。
これにより、法人税の負担を軽減しつつ、未回収リスクに対する資金を確保できます。また、債権管理や与信管理の一環としても機能し、経営の安全性を高める効果があります。ただし、過大な引当や恣意的な設定は税務上否認されるリスクがあるため、過去の回収実績や業界動向を踏まえた適正な計上が重要です。計画的に貸倒引当金を活用することで、利益調整と将来リスクへの備えを同時に実現できる、実務的に有効な節税手段と言えます。
賞与引当金の活用で支給予定を費用化
賞与引当金を活用することで、支給予定の賞与を事前に費用化し、利益圧縮による節税効果を得ることが可能です。賞与引当金とは、決算期末時点で従業員に支給予定の賞与額を見積もり、損金として計上する会計処理です。これにより、賞与支給前でも経費として扱えるため、当期の課税所得を減らせます。
支給額の算定には、過去の実績や会社規程にもとづいた合理的な見積もりが必要で、恣意的な金額設定は税務上否認されるリスクがあります。また、賞与引当金の計上により、従業員への還元も同時に計画的に実施でき、彼らのモチベーション向上や人材定着につながります。適切に運用すれば、決算期直前でも即効性のある利益調整が可能で、節税と従業員満足度の向上を同時に実現できる実務上有効な手法です。
退職給付引当金の積立で将来支出を前倒し
退職給付引当金を積み立てることで、将来の退職金支出に備えつつ節税効果を得ることが可能です。退職給付引当金とは、従業員や役員が将来退職する際に支払う退職金の見込み額を、あらかじめ損金として計上する会計処理です。これにより、実際の退職金支払い前でも経費計上が認められ、当期の利益を圧縮できます。
積立額の算定には、退職金規程や勤続年数、過去の支給実績などをもとに合理的に見積もることが求められ、恣意的な設定は税務上否認されるリスクがあります。また、計画的な積立は、将来の資金繰りを安定させると同時に、従業員に対する安心感や企業の信頼性向上にも寄与します。退職給付引当金の適切な活用により、利益調整と将来支出への備えを同時に実現できる、実務上有効な節税手法です。
圧縮記帳や特別償却準備金を使った一時的な節税
法人の利益が大幅に増えた場合、圧縮記帳や特別償却準備金を活用することで、一時的に法人税を軽減する節税策が可能です。圧縮記帳は、補助金や助成金を受け取った際に、取得資産の帳簿価額を減額する方法で、取得費と受取額の差額を損金として計上でき、当期の利益を圧縮できます。
一方、特別償却準備金は、特定の設備投資に対してあらかじめ償却費を計上できる制度で、一定の条件を満たせば損金算入が認められます。これらの制度を活用することで、設備投資や助成金活用に伴う利益増加を調整し、法人税負担を一時的に抑えることが可能です。ただし、税務上の適用条件や計算方法が明確に定められており、恣意的な操作は認められません。計画的に制度を活用することで、利益圧縮と将来の資金運用を両立させる、実務上有効な節税手法と言えます。
税額控除制度を活用して法人税を直接減らす方法
法人の利益が増えた場合、節税の手段として税額控除制度を活用する方法があります。税額控除とは、計算された法人税額から直接差し引きできる制度で、経費計上による間接的な節税(所得控除)とは異なり、法人税そのものを減額できる点が特徴です。
代表的な制度には、研究開発税制や設備投資促進税制、雇用促進税制などがあり、対象となる支出を行うことで法人税額を直接減少させることが可能です。これにより、利益圧縮だけでは得られない即効性のある節税効果を享受でき、投資や人材育成など企業の成長施策と両立させることも可能です。本項では、税額控除制度の基本的な仕組みと活用のポイントについて解説します。
研究開発税制で試験研究費を法人税から控除する
研究開発税制を活用して試験研究費を法人税から控除することは、即効性のある節税策として有効です。研究開発税制は、企業が新製品や新技術の開発に要した試験研究費を法人税額から直接控除できる制度で、対象となる費用には人件費、試験材料費、外注費などが含まれます。
これにより、単なる経費計上による利益圧縮に加え、法人税そのものを減額できるため、税負担を大幅に軽減することが可能です。また、税額控除の対象となる試験研究は、将来の事業成長や競争力向上にも直結するため、節税とイノベーションを同時に実現できます。適用にあたっては、支出内容の証憑管理や計算方法の遵守が求められ、税務上の確認手続きも重要です。計画的に試験研究費を計上し、研究開発税制を活用することで、利益圧縮と法人税軽減を効率的に両立できる、実務上非常に有効な節税手段です。
中小企業経営強化税制で設備投資に特別償却や控除を使う
中小企業経営強化税制を活用して設備投資に特別償却や税額控除を適用することは、即効性のある節税策として有効です。この制度では、一定の設備投資を行った中小企業が、取得価額の一定割合を当期の損金として計上できる特別償却、または法人税額から直接控除できる税額控除を選択できます。
特別償却を活用すれば、設備の取得費用を早期に経費化することで利益を圧縮でき、法人税負担を軽減できます。一方、税額控除を選択すれば、計算された法人税額から直接減額されるため、より即効性の高い節税効果が得られます。対象となる設備や控除率は法令で定められており、適用には申告書への記載や証憑書類の整備が必要です。計画的な設備投資と税制活用を組み合わせることで、利益圧縮と将来の生産性向上を同時に実現できる、実務上非常に有効な節税手段です。
所得拡大促進税制で給与増加分に応じて法人税を減らす
所得拡大促進税制を活用して給与増加分に応じた法人税の軽減を図ることが有効です。この制度は、従業員の給与総額を一定期間内に増加させた場合、その増加額に応じて法人税額から一定割合を控除できる仕組みです。給与を増やすことで、法人税の負担を直接減らせるだけでなく、従業員の所得向上やモチベーションの維持・向上にもつながります。
適用にあたっては、増加分の給与額や基準年度との比較、控除対象となる要件を正確に把握し、証憑や帳簿を適切に管理することが重要です。また、短期的な増額だけでなく、持続可能な給与体系の設計と組み合わせることで、節税効果と人材定着効果を同時に享受できます。計画的に所得拡大促進税制を活用すれば、利益圧縮による法人税の節減と、企業の成長戦略を両立できる実務上有効な施策です。
エネルギー環境税制で省エネ投資や再エネ導入の負担を抑える
エネルギー環境税制を活用して、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用に伴う負担を軽減することは、有効な節税策です。この制度では、省エネルギー性能の高い機械・設備や太陽光発電、蓄電池などの再生可能エネルギー設備に対して、特別償却や税額控除が認められます。
特別償却を活用すれば、設備の取得費用を早期に経費として計上でき、利益を圧縮し法人税の負担を軽減できます。一方、税額控除を利用すれば、計算された法人税額から直接減額されるため、即効性のある節税効果が得られます。適用には、対象設備の性能基準や取得証明書の提出など、法令で定められた要件を満たす必要があります。計画的に省エネ・再エネ投資と税制活用を組み合わせることで、利益圧縮による法人税軽減と、環境対応投資の推進を同時に実現できる、実務上非常に有効な手法です。
いずれも適用基準が厳格であり、どの制度も必ず利用できるものではありません。自社の今後の事業計画、経営改革などを照らし合わせて、利用できそうなものがあれば考える、くらいの認識でいてください。
法人で利益が出過ぎたときに避けるべきNG節税
法人で利益が想定以上に増えた場合、節税を意識するあまり、法令や税務上認められない手法に手を出すことはリスクが大きく避けるべきです。あるいは合法的な「節税」でもやりすぎると、却って自社の経営を悪化させてしまういわゆる「NG節税」もあります。経費に計上すれば納税額は減るかもしれませんが、要らないものを勝手もそれを有効に利用し、事業拡大につなげられなければ、無用の長物になってしまいます。
「本当にこれ、仕事に必要なんですか?」税務調査で問い詰められ、否認されれば追徴課税や加算税の対象となります。また、過剰な保険加入や引当金設定も、適正な根拠がなければ税務上問題となる場合があります。個人で考えると、生命保険株式会社控除があるからと言って、5つも6つも生命保険に入っても節税にはなりますが、掛け金に見合ったリターンはよほどのことがない限りあり得ません。そうしたことが法人節税にも起きる可能性があります。
- 不要な資産購入による資金繰り悪化に注意
- 過剰な経費利用でキャッシュアウトを招く危険性
- 脱税リスクのあるグレーな節税手法
本章では、法人が利益過多の状況で誤って陥りやすいNG節税の具体例と、リスク回避のポイントについて解説します。正しい知識をもとに計画的な節税を行うことが重要です。
不要な資産購入による資金繰り悪化に注意
法人の利益が大幅に増えた場合、節税のために設備投資や資産購入を急ぐケースがありますが、不要な資産購入は資金繰り悪化のリスクを伴うため注意が必要です。節税効果を狙って過剰に固定資産や消耗品を購入しても、将来的に使用する予定がない場合は資産が遊休化し、無駄な維持コストや減価償却費の負担が発生します。
また、購入資金を短期的に支出することで、手元資金が不足し、運転資金や仕入れ資金の確保が難しくなる可能性があります。特に中小企業では、キャッシュフローの安定が経営の生命線となるため、節税のためだけの資産購入は逆効果となりかねません。手持ち資金がなく、購入した不動産を担保に融資を受けては本末転倒です。
さらに、税務上も実態の伴わない過剰投資は税務調査で指摘されるリスクがあります。節税目的での資産購入は、実際の業務上必要性や将来の投資計画にもとづき、計画的に行うことが重要です。資金繰りや事業運営に支障を来さない範囲での投資を心がけ、節税効果と経営の健全性のバランスを両立させることが、実務上最も安全で効果的なアプローチと言えます。
過剰な経費利用でキャッシュアウトを招く危険性
法人の利益が過剰に出た場合、節税を目的として経費を増やすことは有効ですが、過剰な経費利用はキャッシュアウトを招く危険性があります。不要な消耗品や備品の大量購入、実際の業務と関係の薄い広告宣伝費の前倒し支出などを行うと、帳簿上は損金として計上できても、現金は実際に支払われるため、手元資金が減少します。節税のため余計なものを買い、手持ち資金がショートするのは避けてください。
特に中小企業では、運転資金や仕入れ資金の確保が経営の安定に直結するため、無計画な支出は資金繰りを圧迫し、日常的な事業活動に支障を来す可能性があります。また、経費の過大計上は税務上否認されるリスクもあり、追徴課税や重加算税の対象になる場合もあります。
節税目的での経費支出は、あくまで実務上必要かつ合理的な範囲で行うことが重要です。現金の流出を伴う支出は、資金計画やキャッシュフローの状況を十分に確認した上で判断し、節税効果と資金の健全性を両立させることが、企業経営における最も安全で実務的なアプローチと言えます。
脱税リスクのあるグレーな節税手法
節税を意識するあまり、脱税リスクを伴うグレーな手法に手を出すことは非常に危険です。絶対に避けてください。架空の経費計上や架空取引の作成、実態のない役員報酬や賞与の設定、過大な引当金や保険料の損金算入などは、税務調査で容易に発見され否認され、追徴課税や重加算税の対象となります。節税ではなく申告漏れを超えた「脱税」「犯罪」です!
また、節税効果だけを狙った短期的な資産移動なども、税務上問題視されることがあります。これらの手法は一時的に法人税を圧縮できる場合があるものの、長期的には会社の信用失墜や資金リスク、役員個人への責任問題にもつながりかねません。節税はあくまで合法的な範囲で行うことが基本であり、法令(税法など)や税務通達に沿った方法を選ぶことが重要です。計画性のある合法的な節税策を優先し、リスクの高いグレー手法には絶対に手を出さないことが、健全な企業経営を維持する上で不可欠です。
法人利益が出過ぎたときのよくある質問
法人の利益が予想以上に増えた場合、経営者や経理担当者からは節税や資金運用に関する疑問が多く寄せられます。利益が出過ぎると法人税の負担が大きくなる一方、節税策の選択や実行方法に迷うことも少なくありません。
頻出しそうな質問に回答していきますので、ぜひ参考にしていただき、顧問税理士との相談材料などにしていただければと存じます。また、税理士だけではなく税法に強い弁護士と相談することも時には必要になるかもしれません。ぜひ専門家に相談しながら進めてください。
法人利益が3,000万円を超えた場合の税率はどうなる?
法人利益が3,000万円を超えた場合、中小企業に適用される法人税率は所得金額によって段階的に設定されており、利益が増えるほど全体の税負担が重くなります。中小企業の場合、所得800万円までは軽減税率(15%)が適用され、800万円を超える部分は通常の法人税率(23.2%)が適用されます。
さらに、法人住民税や事業税などの地方税も加算されるため、実効税率はおおむね30%前後になります。利益が3,000万円を超えると、軽減税率の適用部分は限定的で、標準税率部分が大きくなるため、法人税負担が顕著に増加します。
以下は中小企業の概算税率イメージです(法人税+地方税を含む実効税率の目安):
| 所得金額(課税利益) | 法人税率(国税) | 法人住民税 | 実効税率合計 |
|---|---|---|---|
| 800万円以下 | 15% | 約10% | 約25% |
| 800万円超〜 | 23.2% | 約10% | 約33% |
利益が3,000万円を超える場合について考えます。3000万円の利益だとすると3000万円=800万円+2200万円に分けて計算します。
- 800万円×15%(法人税)+10%(法人住民税)
- 2200万円×23.2%(法人税)+10%(法人住民税)
法人税は、800万円×15%=120万円+2200万円×23.2%=510.4万円=120+510.4=630.4万円が課税されます。
法人と個人事業主で利益過多の節税方法はどう違う?
法人と個人事業主では、利益が過剰に出た場合の節税方法に大きな違いがあります。法人の場合、経費計上や設備投資による特別償却、税額控除制度の活用、退職給付引当金や賞与引当金の計上、保険や共済の活用など、多岐にわたる節税手段が利用可能です。
特に、法人税は累進課税ではなく所得金額に応じた税率区分と地方税が加わるため、利益が増えるほど実効税率が高くなり、計画的な利益圧縮が重要となります。また、法人は資金を法人内に留保したまま運用できるため、節税効果と資金活用を両立しやすい点も特徴です。
一方、個人事業主の場合、所得税は累進課税で最大55%前後まで課税されるため、利益過多による税負担の増加が法人よりも顕著です。経費計上は可能ですが、法人のように引当金や退職金制度を利用した節税は基本的にできません。
また、青色申告特別控除や小規模企業共済など一部制度は活用可能ですが、資金を事業内に留保しても個人所得として課税されるため、節税策の自由度は法人に比べて制限されます。そのため、個人事業主は経費の適正計上や控除の最大活用を中心に、利益圧縮を図ることが実務上の基本となります。法人は多様な制度を組み合わせた戦略的節税、個人事業主は所得圧縮を中心とした実務的節税、といった違いがあるのが特徴です。
法人で利益を出過ぎたら内部留保はどこまで残すべき?
法人で利益が過剰に出た場合、内部留保の適正な水準は経営の安定性や将来の投資計画に応じて判断することが重要です。内部留保とは、法人税や配当、役員報酬などを差し引いた後に会社内に残す利益のことで、将来の設備投資や運転資金、研究開発費、事業拡大資金として活用できます。過剰に留保すると税務上「利益の蓄積過多」とみなされ、株主への配当圧力や社会的批判の対象になることがあります。
一方で、手元資金が不足すると運転資金や突発的な資金需要への対応力が低下し、経営リスクが高まります。そのため、内部留保は短期的な運転資金の確保に加え、3~6か月分の運転資金や予定される設備投資、研究開発費など将来支出の見込みにもとづき設定するのが目安です。
また、余剰資金は適切な配当や役員賞与、従業員還元、退職金積立などの合法的な方法で利益を分散させることで、節税効果と資金活用を両立できます。内部留保は「残すだけで節税になる」と誤解されがちですが、実際には節税効果はありません。資金の流動性、投資計画、税負担を総合的に考慮して適正水準を判断することが、健全な経営と長期的な成長を支えるポイントです。
節税をしすぎると税務署に目を付けられますか?
節税を行うこと自体は合法的な経営判断ですが、過度な節税や常識的に考えて不自然な利益操作を繰り返すと、税務署から注目されるリスクが高まります。税務署は、企業の利益水準や経費計上の傾向、過去の申告実績などをもとに、不自然な取引や過剰な経費、過大な引当金設定などがないかをチェックしています。
特に、節税目的だけで行われる過大な経費計上や不必要な保険契約や過剰な役員報酬設定などは、税務調査で容易に否認され、追徴課税や重加算税の対象となる可能性があります。架空取引などが発覚すれば、脱税、犯罪行為です。
また、短期的な利益圧縮を目的に無理な経費計上を繰り返すと、会社の信用や金融機関からの評価にも悪影響を及ぼすことがあります。節税はあくまで法令や通達の範囲内で行うことが基本であり、利益調整や経費計上は実務上必要かつ合理的な範囲で行うべきです。常に税理士と相談しながら適法な範囲で節税してください。
計画的で透明性のある節税策を講じることで、税務リスクを回避しながら法人税負担を抑えることが可能です。節税の効果だけを追求せず、税務署に不自然だと判断されないことを意識した運用が重要です。